Dear everyone,
こちらは、
ふらふら彷徨う「さまよい人」による
『さまよいブログ』
= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。
今回も、
『天理教事典』(1977年版)に記載された
各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。
私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)
最新版👇
このシリーズを始めた理由については、
当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。
前回は、
教会番号55番「佐野原大教会」の『天理教事典』記述を書写して
その歴史を勉強しました。
今回は、
教会番号56番「高岡大教会」について勉強します。
高岡大教会(たかおか だいきょうかい)

佐々木兼太郎入信の頃(明治21年〜明治22年)
明治21年(1888)
高知大教会 初代会長・島村菊太郎は 大阪で入信、
郷里・高知に帰り、布教を始めていた。同じ頃、大阪・芦津の真明講より、
佐野久米治、湯川政太郎、土居嘉七も 高知に渡り、
高知を中心に 近郷村落へ 布教に出ていた。明治22年(1889) 2月27日 (陰曆 正月28日)、
佐々木兼太郎 (高岡初代会長) は、長女・島の病気を救けられて入信。
「我が家の東に向かって倒れる」夢を 三晩 続けてみたことから、
「佐々木家は 断絶するいんねん」と悟り、
「一家の財産を神様にお返しして道一条に進もう」
と決心した。
真明講 摺木組の結成(明治22年頃)
当時、高知に近い高岡郡高岡村のこの地方では、
各村ごとに天理教の講元があり、
それぞれ 真明講 町組、芝組、塚地組、蓮池組などと、
皆、真明講を名乗り、各講 分立していた。(佐々木)兼太郎は、(入信後)
「真明講・摺木組」を結成。
その講元となり、池 馬之助 (義弟) を講脇に、池 亀太郎、池 重次等を周旋人として、熱心な布教を始めた。
佐々木兼太郎の生い立ち〜入信(弘化元年〜明治22年頃)
佐々木兼太郎は、
弘化元年 (1844) 12月13日、
高知県 高岡郡高岡村摺木で、
父・佐々木兼七、母・駒の長男に生まれた。信心深い母に育てられ、
生来 仕事熱心で信仰心厚く、
入信をした46歳の年までに、四国八十八箇所 の霊場巡拝を3回もし、
「御詠歌の兼さん」と綽名される程であった。家業の農業のかたわら、紙漉業、製紙原料仲買商等も手がけ、相当の財産を築いていた。
(佐々木兼太郎の) 夫人は、名を 亀といい、
同じ(高岡村の) 摺木の、池 市蔵の長女だった。夫婦の間には 男子3人女子4人の子供を授かったが、
入信の頃には 男子二人を亡くしており、
長男・平蔵と女子二人があり、3女・芳 (後の2代会長夫人) を妊娠中であった。長女・島に続き、長男・平蔵が 黒痘瘡を救けられるにおよび、
夫婦揃っての 熱心な信仰に入ったわけである。
佐々木兼太郎による驚嘆の報恩行動(明治22年〜明治25年頃)
(佐々木兼太郎は)
入信の年(明治22年) の 5月、
母方の叔父に当たる 幡多郡 清松村中の浜 (現、土佐清水市) の 坂本庄次郎に教えを伝えに出かけた。
(そして、そこに) 3日間滞在して、(いきなり) 12軒の講社を結成した(のだった)。これが、高岡の伝道線が (高知県)高岡村から 県西部へのびる 第一歩となった。
(また、佐々木)兼太郎は、
明治23年(1890) 高知集談所設置の際の負債15円を
「神様が借家住まいでは申し訳ない」と(引き受け) 片付けた。(そして) (高知)集談所では 毎日 御供え物がいるだろうから 水田を献納したい、と申し出た。
(しかし) 高知(集談所)では
「(そこまでしてもらうのは) 前例がないので 本部にお伺いして…」
と、受取ってもらえなかった。しかし、(佐々木兼太郎は)
その年(明治23年) その水田の収穫は「一旦 神様にと心定めしたものだから」と、
全部精米をして 高知集談所へお供えした。明治24年(1891) 3月(陰曆正月)、
教祖5年祭に当たり、(佐々木)兼太郎は、
池 馬之助、市村喜太郎、中平弥太郎、中平亀之助等と共に 初めて土佐から おぢばへ帰り、別席を運んだ。この時、ぢばの理の尊さ、教祖の御恩をしみじみと悟り、
池 馬之助と共に 田畑を売り、池 重次の協力も得て、
230円を 高知集談所を通して 本部へお供えした。初代真柱直筆の領収証の保存書によれば、「土佐ヨリ献納始メ」と記されている。
この信仰態度は、
高知に教会を願う上にも、また 高岡に教会を願う上にも、
他の先輩をおいて 高岡地方の各講元のまとめ役に推され、
(佐々木)兼太郎が「高岡」の初代会長となる 基ともなったのである。明治24年10月23日、 (佐々木)兼太郎は、おさづけの理を拝戴した。
(また) 明治25年、高知分教会 移転建築に際して (佐々木)兼太郎は、
前年の明治24年から 県西部の幡多郡に大工棟梁を連れて出向き、用材の買出し伐採に力をつくし、
また、高知の用材を整えた後、再び 幡多郡佐賀村に出かけ原木を買い、6寸月5寸角の柱75丁を造り、
(それを) おぢばへ運んで 本席に献上。本席宅 普請に役立てた。
高岡支教会の設置(明治25年)
さて、高知分教会の設置をみたことが、
そのまま 高岡地方に分立した各講元の団結をうながすことになった。(島村菊太郎) 高知 初代会長より「高岡に教会を願うように」とのお言葉があり、
(高岡地方に分立した講元一同は)
(高知県) 高岡村 走下(はせより) に適当な建物を定め、
佐々木兼太郎を出願の代表として、教会設置を願い出た(のだった)。(そして) 明治25年(1892) 9月27日、
佐々木兼太郎を会長として、
(高知県) 高岡郡 高岡村町分410番地411番地に、
高知分教会部内「高岡支教会所」として 設置の許しを受けた。続いて 地方庁に出願し、(明治25年) 10月18日、地方庁の認可も滞りなくすませた。
同年(明治25年) 11月13日 鎮座祭、(11月)14日 開筵式を (盛大に)つとめた。
佐々木兼太郎 初代会長時代(明治25年〜昭和4年)
この時 (=高岡支教会開設時)、すでに 教会役員は 40数名を数え、
愛媛県西部へは 布教師を送り込む という伝道態勢も 確立していた。
教会の移転建築(明治27年〜明治29年)
明治27年(1894) 2月28日、
教会移転建築の議が起こり、
「高知部下 高岡支教会 地所買求願」と併せて「山開きの御願」、
更に、同年(明治27年) 4月30日、
「高知分教会部内 高岡支教会所 前 四百十二番地に有之候所 今回 山泉寺 五百八拾番地に移転之上 図面通りに建物御許願」をなした。そうしたところ、すべて許され、
建物は 古家の移築だけで終わり、
将来のために充分な地所を確保するという 先を見通した教会移転が、設置から 3年でなされた。明治29年12月25日には「敷地買添え」の願が許可され、
現在の教会屋敷となっている土地の確保が着実に進められた。
高岡の道の広がり(明治25年〜明治31年頃)
高岡(支教会) の教線は、
明治25年9月 教会設置に先立って、
布教者を仁淀川沿いに 四国山脈を踏み分け県境を越え、
愛媛県西部の地に送り出したことにより、高知、愛媛 両県西部にのびた。また 同年(明治25年) 8月、
池 馬之助が 若い中平亀之助を伴い、
越知村から仁淀川沿いに 内子村を経て、大洲から卯之町を通り、宇和島に出た。その後、2人3人と組んで 交互に出かけたことにより、
現在の同地方の高岡部内教会の基が 定まった。明治26年から翌27年にかけ、その他の地方にも 伝道の足掛かりができ、
中平亀之助は (愛媛県) 宇和島に、
池直馬は (愛媛県) 卯之町に、
岡林米太郎は (愛媛県) 大洲に、
井上幸吉は (愛媛県) 内子に、
池 鶴馬は (愛媛県) 八幡浜に、
瀬戸内海を渡り中国筋に入った 福留村次は (山口県) 岩国に…
と、それぞれ 布教の地を定め、熱心な布教を始めた。明治27年6月4日、
窪川 (矢野徳次)、越知 (池 馬之助) がそろって、
同日(6月4日)付で 出張所の許しを得た。続いて
(明治)28年 10月13日 清松 (坂本吉太郎)、東宇和 (平井卯太郎)、
(明治28年) 同月(10月)21日 岩国 (福留村次)、
同年(明治28年) 11月11日 宇和島 (市村喜太郎)、
翌 明治29年 1月17日 大洲 (岡林米太郎)、
同年(明治29年) 11月8日 西宇和 (池鶴馬)、
同年(明治29年) 12月4日 内子 (中平亀之助) …
と、現在の直轄教会が それぞれ許しを得て設置された。明治31年(1898) 末までには、32ヵ所の出張所を設置した。
その分布範囲は、
高知県 9、愛媛県 21、山口県 1、大分県 1 となっている。
上級・高知分教会の高陽事情への対応(明治31年)
明治31年8月、(上級の) 高知分教会に「高陽事情」が起こった。
この時 (佐々木)兼太郎は、
「高岡30余ヵ所の教会が たとえ どういうふうになろうとも…」
と誓って 活動を展開し、
その年(明治31年) 12月、
すでに債権者の手に渡っていた 高知分教会北側の屋敷を買い戻した。問題解決後、高岡(支教会) の教勢は 大きくのび、
教会屋敷内の付属建物等を 次々と整備していった。
高岡分教会への昇格(明治41年)
明治41年(1908) 6月4日、
教祖殿(15坪) 客殿 及 会長室 (35坪) 2棟の 新築の許しを得て、
翌年(明治42年) 春までに これを完成している。明治41年、天理教の一派独立が認められ、独立による名称改称で、
明治42年 (上級の) 高知分教会が 大教会となった。
それとともに、高岡(支教会) は「分教会」に昇格。
(高岡)分教会 改称奉告祭を 同年(明治41年) 11月27日 執行した。(奉告祭の) 当日は、高知より力士を招き 3日間の大相撲を打つなど、
町始まって かつてない(程の) 盛大な祭典 及び 祝賀行事であった。
高岡分教会 分離昇格の頓挫〜身内出直しの節(明治43年頃〜大正4年)
明治43年、本部神殿 (現 北礼拝場) 普請に当たり、
高岡(分教会) では、建築用材として 愛媛県 東宇和郡 多田村で 檜柱材を買い求め、
長浜港より積出し 献納した。明治44年5月17日、
高知(大教会)2代会長・島村国治郎の会長就任奉告祭があり、
この時「高岡分教会」分離昇格の正式申し渡しを受けた。喜び勇んだ高岡(分教会) の人々は 早速 出願準備にとりかかり、
同年(明治44年) 6月、願書を提出した。ところが、
明治45年1月、分離に関する話が もつれて、
前年(明治44年) 提出した(分離昇格の)願書は、上達されずに終わった。(その後) 大正2年(1913) 7月5日、
(なんと) 会長後継者と頼む (佐々木)兼太郎の養子・幸嗣 (浜田分教会前会長・大谷金太郎2男) が 出直し(てしまう という悲しい節が高岡を襲っ)た。
(それにとどまらず) 続いて、
残された孫千代、幸雄も、翌年(大正3年) 1月と6月に、後を追うように出直してしまった。この(うち続く) 不幸に、
(高岡)部内全般に陽気さは失われ、教勢は伸び悩むようになった。(そうした悲しみが打ち続く中でも、高岡一同は、長年培ってきた信仰心をもって この節を見事に乗り越え)
翌年(大正4年) 5月(には)、
朝鮮在住の 神崎家から 4男・真通を (佐々木家に) 養子として 迎えた。そこに及んで、
(高岡分教会は) ようやく 明るさをとり戻した(のであった)。
ご本部 敷地買収への伏せ込み(大正13年〜昭和初期)
大正13年3月4日、教会東屋敷の買収がなり、役員住宅とした。
この年(大正13年) の2月、
(天理教教会)本部では 新別席場6棟の完成をみているが、
(高岡分教会では) この敷地買収を 高知大教会の教祖年祭へのつとめとして これに当たった。(すなわち) 高岡(分教会) として 教会屋敷建物を抵当に金策をすることになり、
教会在籍の会長、役員家族は、皆、裸になって(伏せ込んだ。そのことにより)目的をはたした(のだった)。だが(それは、) 以後、7年に及ぶ負債となっ(て 関係者一同を苦しめ)た。
佐々木兼太郎 初代会長の出直し(昭和4年頃〜昭和6年)
昭和4年(1929) 5月、
(佐々木)兼太郎(初代会長) が、
丹毒にかかり 危篤状態に陥(るという大きな節が生じ)たが、
不思議な御守護を頂いて 持ち直した。しかし、(佐々木兼太郎初代会長は) すでに86歳の老齢に達していたので、
(昭和4年) 7月25日 会長を辞任した。(そして) 2代会長に 佐々木真通が就任した。
初代会長・佐々木兼太郎は、
昭和6年6月2日発病し、同月(6月)11日、出直した。(佐々木)兼太郎は、発病後、人事不省に陥りながらも、うわ言に
「柱、柱、あすこに柱がある、ここに柱が……」
と、折柄 進められていた(天理教)教会本部の建築 (昭和普請) の御用を思いながら、
40余年にわたる、ぢば、上級を思う孝心一条の偉大な信仰生活の手本を残し、
齢88歳の生涯を終えた。この時、部内教会数は 93ヵ所に及んでいた。
佐々木真通2代会長時代(昭和4年〜昭和44年)
佐々木真通の生い立ち(明治22年〜大正10年頃)
2代会長・佐々木真通は、
明治22年10月19日、
父・神崎一蔵、母・キク の4男として、福岡県 山門郡山川村に生まれた。(天理教の) 信仰は、母親の入信 (現、府内大教会系) と共に、郷里・福岡県在住の時からで、
若くして朝鮮に渡り、
たまたま単独布教で朝鮮にいた 西宇和 2代会長・出水吉蔵と行き合い、その布教に協力したことが縁となり、佐々木家の養子に迎えられた。(佐々木真通は)
大正7年(1918) 2月14日 教校別科卒業、
同年(大正7年) 7月2日 弘岡宣教所長になっている。この年(大正7年)、高知大教会 詰所移転が発表された。
(佐々木)真通は 委員となり、高知詰所の移転改築に当たった。大正10年(1921) 12月25日、弘岡宣教所 神殿落成奉告祭をつとめ(たが)、この普請に(は多くの)負債を残し 苦しんだ。
(しかし) その解決は、後に起きた 大教会 屋敷問題解決の試金石となった(のだった)。
佐々木真通2代会長就任の頃(大正15年〜昭和4年)
大正15年(1926) 7月25日に (佐々木)真通は、
高知大教会長・島村国治郎より
「初代会長 老齢につき、佐々木真通を 高岡分教会長 職務執行者として信任する」
との辞令を受けた。昭和4年(1929) 5月、(佐々木兼太郎) 初代会長が 丹毒で危篤の時、
(佐々木)真通は、神屋敷の清浄化 (役員住宅を東別屋敷へ移すこと)、
真のたすけのための 窪川支教会長 免職処分の 2案を提案。
(そして) 研究を重ねたところ、(佐々木)兼太郎 初代(会長) の平癒をみた。この年(昭和4年) 7月、役員住宅取り壊しの日に、6ヵ年にわたる負債解決の手だてがつき、抵当権もとかれた。
ただちに財団編入の手続きを終え、目標であった教会屋敷の清浄化がなった。(そして) この月(7月)の25日、(佐々木)真通は、高岡分教会2代会長に就任したのである。
(昭和4年) 10月2日、就任奉告祭を執行(した)。
佐々木真通2代会長就任後(昭和4年〜昭和12年)
(昭和4年10月2日) この日(=2代会長就任奉告祭日)、神殿建築の議が決定し、発表した。
(そして)、同月(昭和4年10月) の内に 起工式を挙行した。(その一年半後の) 昭和6年4月(に) 神殿(が)完成し、4月20日 鎮座祭を執行した。
昭和12年5月30日、社会福祉事業として「暁保育園」を開設した。
高岡大教会への昇格(昭和14年〜昭和15年)
昭和14年12月、高知大教会長より「高岡」分離の申し渡しを受けた。
(申し渡しを受け、早速) 分離出願の準備にかかり、
翌年(昭和15年) 3月9日、
越知支教会 部内29ヵ所の教会を高知に残し、大教会昇格の許しを得た。同年(昭和15年) 12月8日、
2代真柱を迎えて (高岡)大教会 昇格奉告祭を執行した。
昭和中期、高岡大教会の諸活動(昭和16年頃〜昭和26年頃)
昭和16年5月には「暁保育園」を発展拡張し「高岡隣保館」を建設し、隣保事業を始めた。
また 同年(昭和16年) 9月、旧 尾道分教会 詰所建物を買収して、(高岡)詰所を開設した。
昭和17年には「高岡隣保館」を主体として「軍人遺家族授産所」を開設している。
昭和21年10月21日、天理教青年会、婦人会の「復元」により、
青年会 高岡分会、婦人会 高岡支部の 合同結成式を挙行(した)。
佐々木太郎が 青年会 高岡分会委員長に、
佐々木 芳は 婦人会 高岡支部長に就任した。昭和22年になって「軍人遺家族授産所」などを閉鎖、
「あかつき保育園」と改称(し)、保育事業のみにした。昭和26年3月21日、教会創立60周年記念事業として 客殿建築の議が定まった。
同日(3月21日) 起工式を執行。
旧客殿の移動より始め、(昭和)27年3月、教会敷地拡張予定地 (教会前水田約3千坪) の買収がなり、客殿も完成した。同年(昭和26年) 12月4日、2代真柱を迎え、中山家御分霊 鎮座祭。
(12月)5日、(高岡)大教会 創立60周年記念祭を執行し、併せて、客殿落成祝賀行事を催した。
(創立60周年記念祭)当日(は) 2千余名の参拝者があり、盛大をきわめた。(また) この時、始めて「若人会」の手により『大教会史』(略史)の出版をみている。
佐々木真通2代会長の辞任〜出直し(昭和28年〜昭和44年)
昭和28年(1953) 4月27日、2代会長・佐々木真通は 会長を辞任。
同日(4月27日)付で、3代会長に佐々木太郎が就任した。同年(昭和28年) 11月10日には、2代真柱を迎えて (3代)会長就任奉告祭を執行した。
2代会長・佐々木真通は、昭和44年 5月23日 出直した。享年80歳。
佐々木太郎3代会長時代(昭和44年〜)
佐々木太郎の生い立ち(大正6年〜昭和23年頃)
3代会長となった佐々木太郎は、
大正6年(1917) 4月30日、
2代会長・佐々木真通、芳の長男として生まれた。幼少の頃から (佐々木兼太郎) 初代会長の薫陶を受け、
天理中学より中央大学経済学部に進み、現役軍人として 満州部隊に配属。敗戦後 シベリア抑留となり、幾多の辛酸を経て、
昭和23年(1948) 7月27日、帰還した。
佐々木太郎3代会長就任後(昭和28年〜昭和48年頃)
昭和28年4月、(佐々木太郎)3代会長就任の時、
北米に「ハイシアトル教会」(会長、平井定利) を設立した。昭和34年2月26日、(高岡)詰所 付属建物 一部移転改造の許しを得て、
風呂場、炊事場、食堂などの一連の詰所整備にかかり、(昭和34年) 10月 工事を完成した。昭和36年7月22日〜10月1日、佐々木太郎は 命を受けて欧米各地を視察した。
昭和37年1月20日、(高岡)大教会 創立70周年記念事業として、
教祖殿 屋根葺替、大教会 炊事場 食堂建築の議が起こった。
(昭和37年) 5月起工、同年(昭和37年) 11月 これを完成し、
同月(11月)14日、高岡大教会 創立70周年記念祭を執行した。昭和39年12月20日、高岡大教会史『土佐高岡の道』 (本文131頁、年譜20頁、200部) を出版した。
昭和44年5月21日、(高岡)大教会 信者宿泊所「よのもと会館」を (高岡)大教会 創立80周年記念事業として工を起こし、同時に 教会屋敷 拡張工事、客殿増築 敷地造成にも着工(した)。
昭和47年1月までに (高岡)大教会の面目を一新する 画期的な普請を終えて、
同年(昭和47年) 3月7日、真柱を迎え、(高岡)大教会 創立80周年記念祭を執行した。また、この年(昭和47年) の正月には、
おやさとやかた (北棟) 普請のため、(高岡)信者詰所 移転建築の命を (天理教教会)本部より受け、(高岡大教会として)「母屋」普請を決意。同年(昭和47年) 8月27日 第30母屋 起工式をつとめ、鉄筋コンクリート5階建 延面積 4,950平方米を完成した。
(そして) 翌年(昭和48年) 10月、真柱を迎え、第30母屋 (高岡大教会 信者詰所) 開所式を執行した。現在、部内教会、よふぼく信者が一丸となって たすけ一条に奔走している。
〔現住所〕〒781-1102 高知県土佐市高岡町乙 244
(『天理教事典』1977年版 P,475〜478)
〔電話〕 088-852-0056
おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。
56回目の今回は、
「高岡大教会」初期の歴史を勉強しました。
当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。
とても古い資料なので、
記載内容も 1970年代以前までとなっており、
かなり昔の歴史にとどまっています…
しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。
十分 私のニーズは満たされるので、
そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道~天理教伝道史を歩く』(道友社編) という本の中にも 佐野原大教会に関する記述がありましたので、自己覚え書きとして書写します。
明治二十二年、高岡郡 摺木村(現・土佐市)の 佐々木兼太郎(高岡初代)が 長女・島の胸痛の身上をたすけられて 信仰を始めた。
間もなく 三晩続けて夢を見て 一家断絶のいんねんを悟り、財産を神様にお返ししよう と決心した。
妻・亀は なお決心がつかなかったところ、黒疱瘡にかかった息子・平蔵が 三日三夜の願いでたすけられ、一家あげて道一条になった。
『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,86
高岡大教会は、高知大教会から分かれた大教会ですね。
高知大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。
高岡大教会初代会長である佐々木兼太郎先生は、
長女(島)様の身上をたすけられて 入信されたのですね。
興味深いのは、
入信後 間もなく、「三晩」続けて「我が家の東に向かって倒れる」夢を見られた、というお話。
佐々木兼太郎先生は、その夢から「一家断絶のいんねん」を悟られた。
そして、道一条の腹を決め、一家の財産を神様にお返しすることを決断された。
娘の身上をご守護頂いて感激しているところに、三晩も続けて同じ夢を見たら、
確かに、これは 目に見えない所からの何らかのメッセージに違いない…と感じるだろう
という気がします (^^)
ただ、「これは何かある…」ということを感じるところまでは 誰もが同じでも、
その「何か」が何なのか、という部分の悟りは、千差万別でありましょう。
『天理教事典』解説文によれば、
佐々木兼太郎先生は、その夢から思案を重ね、そこから「一家断絶のいんねん」を悟られた。
そして、いんねんを納消するために 一家の財産を神様に「お返し」する、という決断に到達された。
私は、この部分を読んで、
「お返しする」という発想が、もう既に 信仰を重ねた「高徳の魂」であられることを示している、
そのように感じたのでありました。
私たちは、神様に何かを捧げる時には、普通は「お供えする」という表現を使うように思います。
しかし、佐々木兼太郎先生は、長女の身上をご守護頂いてお道のお話を聞き始めたばかりのこの時点で、既に「お返しする」という表現を使っておられる。
財産を「お供えする」のではなく「お返しする」‼︎
これは、すなわち、
今 自分が持っている財産は「借りた物」だということを悟られた、
ということを現していると言える と思うのであります。
天理教、お道にご縁を頂いた者が繰り返し教えられる「かしもの・かりもの」の教理。
佐々木兼太郎先生は、
教えを聞き始めたばかりの時点で、もう既に それを 腹に納められている!
『天理教事典』解説文の中に、
「(佐々木兼太郎は) 信心深い母に育てられ、生来 仕事熱心で信仰心厚く、入信をした46歳の年までに、四国八十八箇所 の霊場巡拝を3回もし、『御詠歌の兼さん』と綽名される程であった。」
と 書かれてありました。
すなわち、佐々木兼太郎先生は、
この時点、つまりお道に出会った時点で、既に 非常に高い【霊格】を備えておられた、
と言ってよいのではないでしょうか。
そして、だからこそ、
上級・高知集談所の負債を「神様が借家住まいでは申し訳ない」と一手に引き受けられたり、
毎日御供物がいるだろうから…と 高知集談所に「水田」を献納しようとしたり…
というような 常人離れ(!)した 「報恩」活動を 入信早々 実践することが可能だったのではありますまいか。
(常人には、いきなりそのような実践は無理‼︎ )
お道(天理教)に引き寄せられた者は、
十のものなら九つまでは 既にこれまでに教えて頂いている、残りの最後の一点を教えて頂いているのが この道=『最後の教』だ、
そのように、折に触れ 聞かせて頂きます。
佐々木兼太郎先生は きっと、この道に出会う前に、既に 十のうち九つは身につけておられたのに違いありません。
そして だからこそ、この道に出会った際、
「直感的に」お道の教えには「最後の一点」が含まれている と感じられたのではないか、
それで、迷うことなくこの道を突き進むことが出来たのではないか――
私は、そんなふうに感じたのでありました。

また、高岡分教会が高知大教会から分離昇格しようとした際、話がもつれて 昇格話が 頓挫、
そして、それに追い打ちをかけるようにして 後継予定の方や その他 親族が出直す という節が生起――以上の話も、印象に残りました。
そのようにして大きな節が立て続いた際には、もしかしたら、
佐々木兼太郎 初代会長が あんなに全身全霊込めて「一家断然のいんねん」の納消につとめたのに、佐々木家のいんねんはまだ切れていなかったのか!
と、愕然としたかもしれない。
しかし、高岡の皆様は それを乗り越え、
今、私達の前に 輝かしい隆盛の姿を見せてくださっています。
そこに至るには、おそらく、並々ならぬご苦労があったことでありましょう。
きっと、初代の心を思い返し、懸命に、歯を食いしばって いんねん納消につとめ、節を乗り越えていかれたのに違いありません。
今の高岡大教会の まるでお城の如き壮大な神殿の姿は、
神一条の精神で見事にいんねんを乗り越えた高岡の皆様の苦難の結晶として さまよい人の目には映るのでありました。

いずれにしても、
今回の書き写しも 知らないことばかりでした。
これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても有難いことでした。
「人に歴史あり」
組織にも歴史あり…
歴史を踏んで今がある――
だからこそ、
今を輝かせるためには
「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。
ということで――
今回は「高岡大教会」初期の歴史の勉強でした。
人生、死ぬまで勉強。
今後も、勉強し続けていきたいと思います。
ではでは、今回はこのへんで。
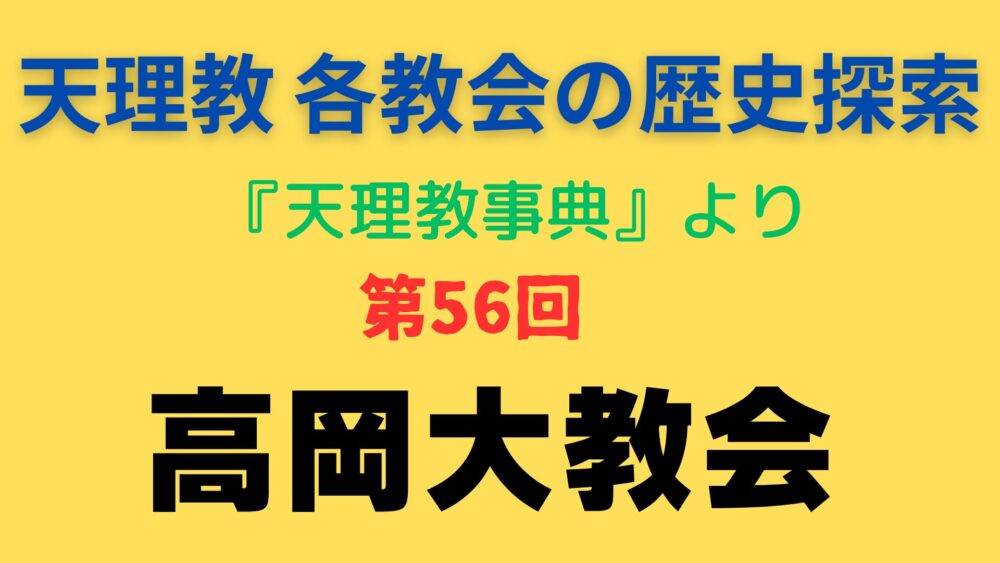

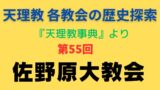
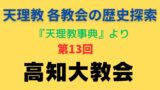
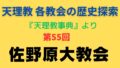
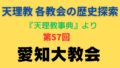
コメント