Dear everyone,
こちらは、
ふらふら彷徨う「さまよい人」による
『さまよいブログ』
= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。
今回も、
『天理教事典』(1977年版)に記載された
各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。
私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)
最新版👇
このシリーズを始めた理由については、
当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。
前回は、
教会番号82番「八木大教会」の『天理教事典』記述を書写して
その歴史を勉強しました。
今回は、
教会番号83番「洲本大教会」について勉強します。
- 洲本大教会(すもと だいきょうかい)
- 洲本大教会 初代会長・松村五三郎
- 松村家の入信(明治3年)
- 松村五三郎 不思議なご守護、たすけ一条の道を決意(明治22年頃)
- 松村五三郎の熱烈な淡路布教(明治25年頃〜明治27年頃)
- 洲本出張所の開設(明治27年)
- 洲本出張所の教会新築費 上級お供えに伴う一時的混乱 〜 それを乗り越えての教会ふしん完成(明治28年〜明治29年)
- 洲本支教会へ昇格、新築落成 & 改称奉告祭(明治29年)
- 松村五三郎 初代会長 井筒家入りに伴い辞任、田口市松 役員の逃亡(明治29年)
- 洲本支教会の敷地建物買い戻し、松村隆一郎2代会長の就任(明治34年)
- 広がる洲本の道(明治33年頃〜明治40年頃)
- 洲本分教会へ昇格前後(明治42年頃)
- 松村隆一郎、洲本2代会長と高安4代会長の兼務開始(大正4年)
- 松村隆一郎 洲本2代会長 & 高安4代会長の出直し(大正6年)
- 松村よしゑ3代会長の就任(大正6年)
- 松村よしゑ3代会長の奮闘 〜 教勢の伸展(大正6年頃〜昭和12年頃)
- 松村よしゑ3代会長の辞任 〜 出直し(昭和14年〜昭和21年)
- 松村隆行4代会長の就任(昭和14年)
- 洲本大教会へ昇格(昭和16年)
- 洲本布教線の拡大(昭和14年頃〜昭和20年代)
- 洲本大教会の移転建築ふしん 〜 神殿落成奉告祭(昭和32年頃〜昭和38年)
- 信者詰所の変遷
- おわりに
洲本大教会(すもと だいきょうかい)

洲本大教会 初代会長・松村五三郎
洲本大教会 初代会長・松村五三郎は、
明治7年(1874) 10月24日、
河内国中河内郡 南高安村大字教興寺1番地、松村栄治郎の3男として生まれた。
高安大教会 初代会長・松村吉太郎の 弟にあたる。母・さくは、大和国平群郡 平等寺村、小東政吉の長女で、
教祖の長男・秀司の妻・松枝の姉にあたる。
松村家の入信(明治3年)
松村家の天理教への入信は、
明治3年(1870) の秋、
さくが「たちやまい」という難病にかかった時に始まる。(松村家では、さくの「たちやまい」を何とかたすけて頂こうと) 八方 手をつくしたが、(どこへ行っても) 全快おぼつかなしといわれ (万策尽きた感じであった。
そのような中) 翌・明治4年正月2日、
(松村さくは) 裏山を越えて 平等寺の実家へ帰り、(正月)10日頃、駕籠にのせてもらって、おぢば へ参拝した。教祖は「よく帰って来ておくれた」と喜ばれ、永らく入浴しないで汚れている さくを風呂へ入れ、髪を梳り、いたわられた。
その時、髪の中の多くの虱を教祖は取りのけられたという。この時、さらに
「あんたは 私の 4代前のお母さんやった。しかし、年の若い者をお母さんというのもおかしかろうから、姉さんと呼ばしてや」
と 仰せになったということである。このようにして (教祖は) 親身にまさる愛情の中で親神の話を諄々と説かれ、生命おぼつかなしといわれた (松村さくの)難病は 3日の後には全快。
(不思議なたすけを見せられて) 夫・栄治郎も 共に信仰することになった。
『天理教教祖伝逸話篇』
23. たちやまいのおたすけ
松村さくは、「たちやまい」にかかったので、生家の小東家で養生の上、明治四年正月十日、おぢばへお願いに帰って来た。
教祖は、いろいろと有難いお話をお聞かせ下され、長患いと熱のためにさくの頭髪にわいた虱を、一匹ずつ取りながら、髪を梳いておやりになった。
そして、更に、風呂を沸かして、垢付いたさくの身体を、御手ずから綺麗にお洗い下された。
この手厚い御看護により、さくの病気は、三日目には、嘘のように全快した。
松村五三郎 不思議なご守護、たすけ一条の道を決意(明治22年頃)
(松村)五三郎は、この信仰的な家庭に生まれ (生まれながらにして)自然に (この道の教えに) 感化されていたが、
(松村五三郎自身が) 実際に信仰に入った(と言える)のは、やはり病気からだった。(松村五三郎自身) 16歳の時、ひどく痔を患った。
その折、母・さくから 親神の話を聞いた。
(母から親神の話を聞いた 五三郎の痔疾は、なんと) ただちに不思議な守護のもとに全快した(のだった)。
(不思議なご守護を頂いた松村五三郎自身は) たすけ一条の道に進む決心をした(のだ)が、(ただ、当時は) 少年だった事もあり、(すぐ) 実行に移すまでには至らなかった。
松村五三郎の熱烈な淡路布教(明治25年頃〜明治27年頃)
明治25年(1892) 11月15日、
(松村)五三郎 (当時19歳) は、
長兄・(松村)吉太郎の指示により、安堂鶴造を伴い 淡路に渡った。安堂(鶴造)は すぐ引き返したが、(松村)五三郎は 洲本常盤町で 8畳1間を借りて布教生活に入った。
はじめの 6ヵ月は 文字通りのどん底の苦労と不自由の連続で、いわば教祖のひながた そのままの布教生活であった。土地不案内な山地を 1日40キロの道も苦とせず、生麦をかじりながら、ほとんど淡路島内に(松村)五三郎の足跡の及ばない所がないほどの 熱烈な布教活動であった。
(松村五三郎の) この熱心な布教は 至る所で不思議なたすけとなり、1夜に 50戸の信徒加入があり、改式させたこともあった。
洲本出張所の開設(明治27年)
(松村五三郎の熱烈な布教により) 教勢は著しく発展した。
(それと共に) 教会設置の要望が強くなり、(ついに)「洲本出張所」設置の出願をすることになった。
この時、信徒・増田たねの寄付で、洲本常盤町に 44坪5勺の家屋を買い求め、出願の運びとなった。(そして) 明治27年(1894) 11月5日、
(天理教教会)本部より「洲本出張所」設置の許しを得、
(松村五三郎の熱意は) 布教開始以来 2年目に(して) 早くも実を結ぶこととなった。
(そして) 引き続き、同年(明治27年) 12月5日、地方庁の認可があった。
洲本出張所の教会新築費 上級お供えに伴う一時的混乱 〜 それを乗り越えての教会ふしん完成(明治28年〜明治29年)
以来、(洲本出張所の) 教勢の発展著しく、
明治28年(1895) には 部内布教所が数ヵ所になった。(教勢の発展に伴って) (洲本)出張所の建物も狭くなったため、教会新築の工事にとりかかることになった。
(教会新築工事に着手するにあたって) 第1回、第2回と資金の募集を行い (一同の真実が集ま)った。
しかし、その2回とも、全部を上級教会に「理の伏せ込み」とした。(ただ、その上級への伏せ込みは、自分達の教会ふしんへと思ってお供えした人々の理解を得ることが なかなか難しく)
そのため、(松村)五三郎は、一時、役員・信徒に対して 非常に苦しい立場に追い込まれた。
しかし (そのような一時的なごたごたも、松村五三郎を中心とした一同の神一条の精神により 無事 乗り越えて)、
明治29年(1896) 早々から (自教会の新築)工事に着手。
同年(明治29年) 8月、無事落成するに至った。この時の「伏せ込みの理」が、その後の (洲本の)発展の基礎をつくったといえよう。
洲本支教会へ昇格、新築落成 & 改称奉告祭(明治29年)
教会(施設)の建築中、(洲本出張所は)
(明治29年7月11日付で) 支教会に昇格した。(また) 同年(明治29年) 8月21日に、
新築落成奉告祭を兼ねて 改称奉告祭を執行した。
松村五三郎 初代会長 井筒家入りに伴い辞任、田口市松 役員の逃亡(明治29年)
(出張所から支教会へ昇格し新しい教会施設も完成して、洲本の道は順調な発展を遂げていた。)
ところが、明治29年11月、
(松村)五三郎(初代会長)が、ようやく基礎のできあがった洲本を去って、当時の芦津分教会 (大阪市西区新町) の井筒家へ むこ養子として行くことになった(のである)。
(松村)五三郎、23歳の時である。(松村)五三郎(初代会長)の後を、洲本支教会役員・田口市松が引き受けることになった。
しかし、田口(市松)は 教会の他の役員とうまくいかず、かつ 教会の敷地建物が自分の名義になっているのを奇貨として、正井八郎に売却し (なんと)逃亡してしまった。これを聞いた上級・高安(分教会)の会長、松村吉太郎は 急いで洲本にかけつけたが、僅か1日の違いで 既に登記も済んでしまっていた。
洲本支教会の敷地建物買い戻し、松村隆一郎2代会長の就任(明治34年)
(松村吉太郎は) 訴訟などに1年余り奔走の結果、
ようやく(洲本支教会の)敷地建物を買い戻すことができ、
(松村吉太郎の) 弟・(松村)隆一郎を (洲本支教会の)後任(会長)とした。(ちなみに)
(松村)五三郎 (洲本大教会 初代会長)は、
明治30年4月28日、芦津分教会(2代会)長に就任。
明治42年1月11日 芦津大教会長となり、
大正8年(1919) 11月8日、46歳で出直した。
松村隆一郎2代会長の経歴
2代会長・松村隆一郎は、初代会長・(松村)五三郎の弟にあたる。
明治12年(1879) 3月19日、松村栄治郎の4男として生まれた。(松村)隆一郎は、豪毅英邁で進取の気性に富み、
早くから青雲の志を抱き、渡米を計画していたといわれている。明治32年(1899) 9月1日、
高安 初代会長(長兄・吉太郎) の命をうけて淡路に渡り、布教活動を行っていたが、明治34年(1901) 6月10日、
兄・(松村)五三郎の後を継いで、洲本支教会長に就任した。
広がる洲本の道(明治33年頃〜明治40年頃)
(松村隆一郎が2代会長に就任した) この頃、(洲本支教会の)教勢の発展は著しく、
教線は 淡路島を出て阪神地方にも及び、さらに遠く 北海道にまで伸展していた。
(洲本部内の) 教会が (全国津々浦々に) 続々と設置されている状況であった。北海道の道は、
明治33年(1900) の秋、
山本初右衛門 (当時45歳) の渡道に始まった。山本(初右衛門)は 熱烈な信仰に燃え、「おさづけの理」を路銀として
懐中無一文で はるばる遠い旅を続けて北海道に渡った。
(そして) 鵡川の 山本鹿蔵宅に落着いて 布教を始めた。後年の 胆振分教会、統北分教会の基礎は ここで築かれたのである。
洲本分教会へ昇格前後(明治42年頃)
(松村)隆一郎は、熱烈な布教のかたわら、
兵庫県 教会組合事務所 主事としても活躍した。この間、明治42年(1909) 1月18日、
洲本支教会は 分教会に昇格。その後も、
さらに伸展をつづけた。明治42年8月、朝鮮半島に教線を伸ばすに当り、
(松村)隆一郎は出張を命ぜられ、管理所 及び 宣教所設置に 種々努力した。
松村隆一郎、洲本2代会長と高安4代会長の兼務開始(大正4年)
大正4年(1915) 1月、
長兄・(松村)吉太郎 (高安初代会長) が 本部の教務多忙のため、高安大教会長の職を (松村)隆一郎に譲った。(そのため、松村)隆一郎は、洲本分教会 (2代会)長と 高安大教会 (4代会)長とを兼務することになった。
松村隆一郎 洲本2代会長 & 高安4代会長の出直し(大正6年)
(松村)隆一郎は、当時の天理教内の 雄弁家の三羽鳥のひとりと たたえられ、天理教発展の上に大活躍を期待されていたが、
大正6年(1917) 9月2日、病気となり、惜しくも出直した。
(当時、部内教会は 20ヵ所余)。
松村よしゑ3代会長の就任(大正6年)
(洲本分教会)3代会長・松村よしゑは、
2代会長・松村隆一郎の妻女である。(松村)隆一郎の出直によって、
同年(大正6年) 11月4日、(松村よしゑが) 洲本分教会長の後任として 許しを得た。
(洲本分教会3代会長のお許しを頂いた 松村よしゑは) 幼い子どもたちをかかえて、洲本に着任した。
松村よしゑ3代会長の経歴
よしゑは、明治14年(1881) 2月23日
大阪府南河内郡千早村の豪家・仲谷与十郎の長女として生まれた。同家(仲谷家)の信仰は、よしゑの 持病の胃けいれんのご守護から始まった。
その後、仲谷家の信仰は とみに進み、財をつくして 道一条に進むことになった。
高安大教会に伏せ込み、郷里に 千早支教会を 設置するに至った。
父・(仲谷)与十郎は、一時、高安の会長の重職についたこともあった。(松村)隆一郎が 高安大教会長を兼務した時期には (仲谷家の)家族は 高安に居住しており、よしゑは 婦人会・高安支部長として活躍した。
松村よしゑ3代会長の奮闘 〜 教勢の伸展(大正6年頃〜昭和12年頃)
(松村)よしゑは 3代会長として洲本に着任したが、
(そこは松村よしゑにとって) 未知の土地であり、
(松村よしゑには) 布教の経験がなく苦しい道中であった。しかし、(松村よしゑは) 不撓不屈の精進を続け、
大正10年(1921) の教祖40年祭の提唱以来、教勢は伸展し、部内教会が続々と新設された。(洲本の) 教勢は 遠く樺太にまで伸びるに至り、磐石の基礎がつくられた。
教祖50年祭・立教100年祭の折の活躍は めざましいものがあった。
松村よしゑ3代会長の辞任 〜 出直し(昭和14年〜昭和21年)
昭和14年(1939) 10月29日、
(松村)よしゑ (3代会長)は、長男・隆行に 会長の職を 譲り渡した。
(当時 洲本部内教会は 60余になっていた)。(松村よしゑは) その後は、日夜「おたすけ」に精励し、前会長として 部内教会一般から深く敬慕された。
昭和21年(1946) 1月12日、
(松村よしゑ3代会長は) 惜しまれつつ 出直した。
松村隆行4代会長の就任(昭和14年)
昭和14年(1939) 10月29日、
(松村)隆行が、母の後を継いで 洲本分教会 (4代会)長に就任した。
(昭和15年1月10日 地方庁認可)
松村隆行4代会長の経歴
4代会長・松村隆行は、
明治43年(1910) 9月15日、
(松村)隆一郎2代会長の長男として、高安大教会で生まれた。
(父・隆一郎は、高安大教会長を兼務し、家族は 高安に居住していた)。
洲本大教会へ昇格(昭和16年)
昭和16年(1941) 3月11日、
洲本分教会は、
真柱の声で高安大教会より分離して 本部直属となり、大教会に昇格した。(だいぶ先の話になるが)
(松村)隆行(4代会長)は、昭和43年(1968) 6月26日、兵庫教区長に就任している。
洲本布教線の拡大(昭和14年頃〜昭和20年代)
この間、
(洲本の) 教勢は (大いに)伸展。
満州 (現・中国東北部) に(まで) 教線が伸び、教会の設置をみるに至った。(また) 終戦後(には)、東京方面にも教会が新設され、
さらに 沖縄でも 戦前からの布教が実を結びつつあり、教会設置の準備が進められている。
洲本大教会の移転建築ふしん 〜 神殿落成奉告祭(昭和32年頃〜昭和38年)
(洲本大教会の) 神殿は、
長い間、(松村五三郎)初代会長当時のまま (洲本市常盤町)であったのだが、
教勢の伸展に伴い 狭隘になってきた。(それを受け)
昭和32年(1957) 1月22日の春季大祭において、
(松村隆行4代会長より) 移転建築計画の発表が行われた。同年(昭和32年) 6月12日、(兵庫県) 洲本市 宇山3丁目に 約4,000坪の敷地を買収し、翌・昭和33年から 土盛工事に着手(した)。
昭和35年(1960) 10月23日、
神殿建築の起工式を行い、(工事は順調に進んで 無事完成した。)昭和38年(1963) 11月20日、
2代真柱と現(3代)真柱を迎えて
(神殿落成)奉告祭が (盛大に) 執行された。
信者詰所の変遷
(洲本)信者詰所は、
洲本分教会が高安より分離して大教会に昇格してからは、
最初 玉江詰所の一部を借り、次に 大江詰所に配属され、後に 中和詰所に併置となった。その後、安東詰所の一部を借り受けていたが、
昭和26年(1951) 土地を買収し (天理市川原城町400番の1)、
昭和27年1月(に) (信者詰所を) 新築(すること)に 決定。同年(昭和26年) 2月28日、
(天理教教会本部の) 許しを得て (信者詰所建築に)着工。
昭和28年(1953)、(無事) 完成をみるに至った。その後、教祖70年祭、80年祭を迎えるにつれて 部内教会は増加。
信者数の増加に伴って詰所が狭隘になり、対策が検討された。(そして)
昭和48年(1973) 1月27日、
現在地 (奈良県天理市川原城町3552番地) に 第33母屋として起工式を行い、
翌・昭和49年 4月28日 竣工(した)。
同年(昭和49年 5月)17日、真柱の臨席を得て、開所式を執行した。現在、(洲本大教会) 部内教会、よふぼく・信者は、
心を一つに(合わせ) 世界たすけに邁進している。
〔出版物〕『洲本月報』(昭和44年11月)
〔現住所〕〒656-0012 兵庫県洲本市宇山3丁目1番1号
〔電話〕0799-22-0487(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)
(『天理教事典』1977年版 P,451〜453)
おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。
83回目の今回は、
「洲本大教会」初期の歴史を勉強しました。
当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。
とても古い資料なので、
記載内容も 1970年代以前までとなっており、
かなり昔の歴史にとどまっています…
しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。
十分 私のニーズは満たされるので、
そのまま書写し続けております (^_-)-☆

洲本大教会は 高安大教会から分かれた大教会ですね。
高安大教会については、以前勉強して 記事を投稿しました。
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】83回目の当記事では『天理教事典』の中の「洲本大教会」についての記述を書き写したわけですが、今回も、本当に知らないことばかりでした。
洲本大教会 初代会長の 松村五三郎先生は、
高安大教会・松村吉三郎初代会長の 弟だったのですね。
松村吉三郎先生と 松村五三郎先生の 母親の 松村さく先生は、中山秀司先生の奥様・まつゑ様のお姉様。
すなわち、中山家と松村家は、文字通り濃い親類縁者。
それでもって、
兄である松村吉三郎先生といえば、
高安大教会の初代会長にして、天理教一派独立の大黒柱。
初期天理教の 重鎮中の重鎮の大先生。
…そう考えていくと、
松村五三郎先生は、天理教のサラブレッドと言って差し支えないのではないか… と思ったりもします (^^)

その 松村五三郎先生は、19歳の時に、兄である松村吉三郎先生の指示で淡路へ布教に出られた。
それが 洲本大教会の元一日というわけですね。
淡路島の伝道に関して『道〜天理教伝道史をあるく』という本の中に 少しだけ記述がありましたので、自己覚え書きとして書写します。
淡路島へは 高安系の歩みが大きく実を結んだ。
明治二十四年、この地で布教していた樫原清吉は 天一講を結び 高安所属講社になり、二十五年、松村吉太郎の実弟・五三郎(十八歳) が出向いた。
彼は 一日 四十キロの山道も苦にせず歩き、全島 足跡の及ばぬところはない といわれた。
(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,83)
生麦をかじりながらの布教で、一夜に 五十戸の信者が加入したこともあった。
もともと、樫原清吉という先生が布教して 天一講という高安系の講社があった淡路島の道を拡大すべく、当時 高安分教会長であった松村吉三郎先生の指示で その弟の 松村五三郎先生が派遣された、
そういうことだったのですね。
「(松村五三郎の) 全島 足跡の及ばぬところはないといわれた。生麦をかじりながらの布教で、一夜に 五十戸の信者が加入したこともあった」
と『道〜天理教伝道史をあるく』に書かれてあります。
一夜の間に 五十戸の信者が加入‼
(°o°)
松村五三郎先生の布教が如何に凄まじかったのかが うかがわれます。

そんな 松村五三郎先生の熱烈な布教が結実し「洲本出張所」開設。
教会施設のふしんにも取り掛かり 支教会へも昇格し、
順調な発展を遂げているかのように見える洲本支教会でした。
…なのに、明治29年、
突然、松村五三郎 (洲本)初代会長は 芦津分教会の井筒家へ 婿養子へ入られることとなり、洲本を去っていかれることに…
その部分を読んだ時、
『天理教事典』「洲本大教会」解説文にはその背景が書いておらず、どういう経緯でそのようになったのかがわからないので、
思わぬ展開に「え?」と驚いてしまいました。
上記のような史実を知って、以下のようなストーリーが 私の頭の中に浮かんできました。
当時、芦津の井筒梅次郎先生に男児の後継者不在で娘様の婿養子を探しておられた。
そのような状況の中、淡路で猛烈布教している松村五三郎先生の評判が耳に入ってきた。
それで「ぜひ ウチの娘の婿に…」ということで、松村五三郎先生に 白羽の矢が立った。
その後、話がまとまって、松村五三郎先生が芦津に婿入りされた…
もしかしたら、そのような やり取りがあったのではなかろうか…
不謹慎にも、一人勝手にそのような想像をしたのでありました (^^;)
以上は『天理教事典』「洲本大教会」解説文だけを元にした勝手な妄想で、何の根拠もありません。
この空想は、何の意図もない ただただ素朴なつぶやきに過ぎませんので、
万が一、不快な思いをされた方がおられましたならば、深くお詫び申し上げます。
どうかご容赦下さい。
それにしても、
芦津側は、素晴らしい先生が来てくれて万々歳ですが、
その一方、
初代会長が突然いなくなってしまった「洲本支教会」の方は 非常に困惑したのではないか…
と想像するのですが、どうなのでしょうか。
そういえば、
『天理教事典』「洲本大教会」解説文の中に、
洲本出張所を開設して教会建物を新築することとなり その費用を集めた際、集まった資金を全て上級教会に伏せ込んだ、
その時に 松村五三郎先生と役員・信徒の間に一時的な心の擦れ合いがあった、
と 書かれてありました。
もしかしたら、
そういった人間関係のもつれも、松村五三郎先生が洲本を離れて芦津入りする要因の一つとなった…
そんな背景もあったのでしょうか…
全くわかりません。
が、まぁそのようなことは、個々の信仰の上にはどうでもよいことですし、
ここまで書いておいて、
これ以上、野次馬的にあれこれ詮索するのは不謹慎だとの思いが強く湧いてきました。
このあたりで控えたいと思います。(>_<)

その他にも、
松村五三郎 初代会長が去った後、田口市松 役員が勝手に教会の敷地建物を売却し逃亡した、という話も衝撃的でした。
そんなことある⁉ というか、そんなことが出来るの⁉
と、びっくり仰天、言葉を失いました。
上級・高安の 松村吉太郎 会長が奔走して何とか教会の敷地建物を買い戻すことが出来たとのことなので、大事には至らず良かったですが、
それにしても、教会の長い歴史の中にはいろんなことがあるんだなぁ…
ということを改めて感じさせてくれる史実でありました。
また、
松村家の長兄である 松村吉三郎先生が 本部の教務多忙のため 高安大教会長を辞した際、
洲本の2代会長となった (松村吉三郎先生の弟の) 松村隆一郎先生が 高安大教会の4代会長も兼務した、
という話も、(そういう方面の知識が皆無だったこともあり) 私には ちょっと驚きでした。
へぇ~、そんな歴史があったんだ、部内教会の会長が上級の会長を兼務したりすることもあるんだ… みたいな感じで。
天理教では、昨今、会長不在の教会が増えているという話をよく耳にします。
天理教の教会をこれ以上減らしたくない、何とか存続させるんだ、という方針を維持するのならば、
これからは、やりたくない人をどこかから引っ張り出してきて無理やり据える等ということはせず、天理教の会長にふさわしい先生が、複数の 会長職を兼務する、というやり方もアリなんじゃないのかな…
松村隆一郎先生が 洲本大教会長と高安大教会長を兼務していた時期がある という史実を知って、
そんなことを思ったりもしました。

いやぁ~、「洲本大教会」の歴史は、(私にとって) いろいろ驚きが詰まっていました。(°д°)
これ以上書くのは、ただ長くなるばかりなので、もう終わりにしようと思うのですが、
洲本大教会といえば、北海道布教が有名ですので、最後に少しだけそのことに触れて終わりたいと思います。
『道〜天理教伝道史をあるく』という本の中に、洲本大教会の 北海道布教に関する記述がありましたので、自己覚え書きとして書写します。
洲本支教会の布教師・山本初右衛門は、明治三十三年、会長の命で北海道布教を志し、淡路の阿万付近からの移住者が多い 日高の地をめざした。
宿の女将から、筋向かいの山本鹿蔵が 同郷 同信の人と聞いて 訪ねた。
鹿蔵の養子・角蔵がトラホームなので、早速おたすけした。
徳島から厚真へ入植していた 笹田実蔵の二男・佐蔵は 脳と胃腸病を患っていて、これも たすけた。ほどなく膽振出張所 設置の話が起こり、鹿蔵名義で 認可された。
その後、布教地を定めることになり、初右衛門の後任として来た 西尾広吉は 日高へ、角蔵は 厚真へ、佐蔵は 室蘭へ出かけた。初右衛門と広吉が 引き揚げた後、鹿蔵らが 膽振の道の伸展に努めた。
三十五、六年ごろ、角蔵は 札幌方面へ出て、札幌郡豊平村月寒を拠点に布教した。
四十一年、札幌区北一条東四丁目に 統北宣教所を設置。膽振は のち 笹田佐蔵が担任となった。
(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,123)
淡路島にある洲本大教会が なぜ北海道?という漠然とした疑問を持っていましたが、
洲本支教会の布教師・山本初右衛門先生が、会長の命で 北海道布教を志したところから 洲本の道が付いた…
そういうことだったのですね。
「北海道 天理教」でネット検索すると、天理図書館 天理教文献室・早田一郎先生の『天理教伝道史の諸相~北海道の天理教』というファイルがヒットしました。
後学のため、その中の、洲本大教会に関連のある部分を コピペさせて頂きます。
北海道で最も多くの教会を持つのは 洲本大教会である。
勇払郡 むかわ(鵡川)町にある 膽振分教会と 札幌の 統北分教会を合わせると 60ヵ所近くになり、うち 49ヵ所が北海道にある。
他の洲本系をあわせると 54ヵ所になる。淡路出身の山本鹿蔵夫婦と養子の角蔵は、撫養系信仰者だった。
明治24年には 鵡川に住み、商売をしていた。明治33年に 淡路出身の洲本系布教師・山本初右衛門が鵡川に来て、鹿蔵宅に住みながら布教を始めると、鹿蔵、角蔵も初右衛門と共におたすけを始め、遠方へは 馬にのり颯爽と出掛けたと言う。
初右衛門は、鵡川の北、厚真村の笹田佐蔵をおさづけでたすけた。
笹田の母も 撫養系信者だった。
佐蔵は信仰に懐疑的だったが、おたすけをうけ5万坪の土地をお供えし 布教師の心を固めた。これから 山本初右衛門、山本鹿蔵、角蔵、笹田佐蔵の猛烈な布教が始まり、
明治33年に 初右衛門を所長に 膽振布教所 (現 分教会) が設立された。
布教所設置に際し、信仰の元である撫養との間で問題が生じかけたが、本部の裁定を得て、洲本部属となった。翌年、初右衛門が淡路へ帰った後を 鹿蔵が継いだ。
明治35年、角蔵は思うところあって札幌に出て布教を始める。おたすけ中、川を渡る船賃がないという苦労の中、妻を迎え夫婦でおたすけに励み、
(天理図書館天理教文献室・早田一郎『天理教伝道史の諸相(27)~北海道の天理教②』より)
明治41年、札幌にて統北布教所 (現 分教会) を設置した。
この前に 角蔵は、膽振を離れ 洲本直轄になっていた。
北海道で最も多くの教会を持つのは 洲本大教会なんですね。
淡路島の大教会が北海道で最も多くの教会を持っているというのも、不思議な感じがします。
この世に偶然はない と言われますから、このような現象にも 人間にはわからない深い由縁があるのでしょうね (^^)
その他にも、これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても勉強になりました。
有難いことでした。

今回の【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】においても また、
歴史を知ることで 今の現象をより立体的に感じる、
という体験をすることが出来ました (^^)
「人に歴史あり」
組織にも歴史あり…
歴史を踏んで今がある――
だからこそ、
今を輝かせるためには
「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。
ということで――
今回は「洲本大教会」初期の歴史の勉強でした。
人生、死ぬまで勉強。
今後も、勉強し続けていきたいと思います。
ではでは、今回はこのへんで。
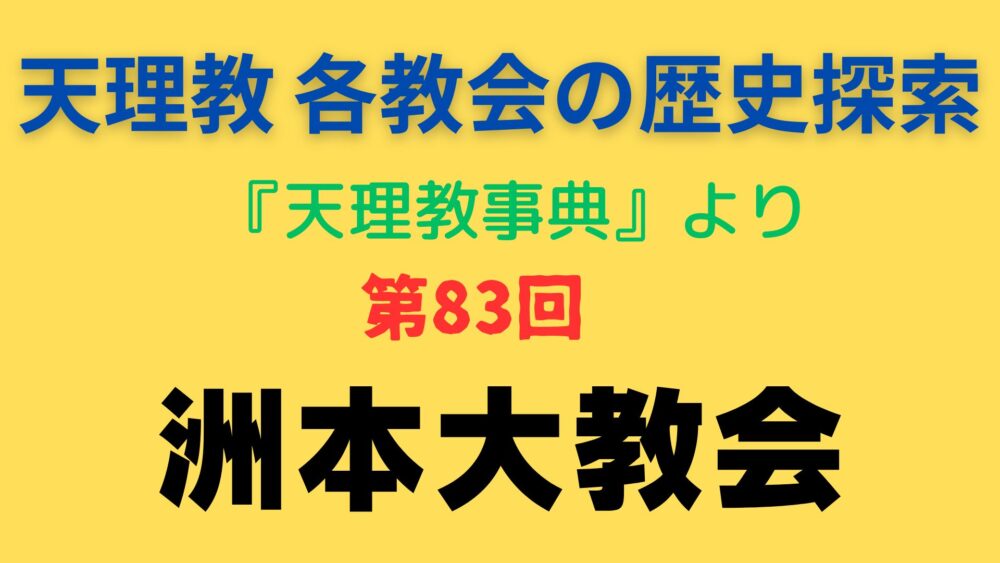

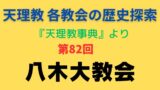
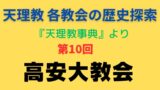
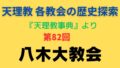
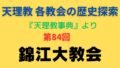
コメント