Dear everyone,
こちらは、
ふらふら彷徨う「さまよい人」による
『さまよいブログ』
= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。
今回は、【YouTube文字起こし】紹介シリーズの中の、
天理教養徳社運営「陽気チャンネル」
茶木谷吉信先生による【逸話篇の世界を旅する】動画シリーズの続き、
「【逸話篇の世界を旅する14】茶木谷吉信先生「人がめどか」ご逸話をめぐって」
のご講話を【文字起こし】して勉強します。
今回の動画では、
『天理教教祖伝逸話篇』123番「人がめどか」のご逸話を元にした話で、
「人をめどとすることなく、神様をめどにして歩む」ことの大切さを再確認すると共に、
そこから話題を広げて語られた「心の3階層説」というものについて学ぶ機会を与えて頂きました。
いつもながらですが、とても勉強になるお話でした。
ということで、今回のさまよい人【自己学習ノート】は、
【逸話篇の世界を旅する14】茶木谷吉信先生「人がめどか」ご逸話をめぐって
という動画を通しての学びを綴ります。
- 今回紹介する動画について
- 茶木谷吉信先生講話「人がめどか」のご逸話をめぐって【文字起こし】
- 過去動画「目に見えん徳」内の訂正箇所に関して
- 『天理教教祖伝逸話篇』123番「人がめどか」というご逸話
- 誰がこんな意地悪なことを言ったのか
- 梅谷四郎兵衛先生が決して「食い詰め左官」などではないことは、周知のことだった
- 梅谷四郎兵衛先生に対する陰口は、何らかの意見の対立から出てきたものかもしれない
- 似たような光景は、私たちの身近でも繰り広げられている
- 熱心な人の集まりでは「一所懸命比べ」をしてしまいがち
- 信仰すればするほど積む場面が増える怖いほこり=「高慢のほこり」
- 自分の努力だけでは止めようがないほこり=「腹立ちのほこり」
- 茶木谷式「心の3階層」説(feel➡think➡consider)
- 「腹立ち」は【feel】=「反射」だから、コントロールしきれない
- 「思う=think」&「思案=consider」を天の理に添わせる努力を重ねることで、それが「感じる=feel」へ波及し、結果として、腹立ちのような【反射】現象も、より親心に添った姿に変えて頂ける
- ありがとうございました
- 茶木谷吉信先生講話「人がめどか」のご逸話をめぐって【文字起こし】
- 動画を視聴しての感想
- まとめ(今回の動画を通しての学び)
今回紹介する動画について
今回、紹介【文字起こし】するYouTube動画は、
【逸話篇の世界を旅する】動画シリーズ
>【逸話篇の世界を旅する14】茶木谷吉信先生「人がめどか」ご逸話をめぐって
という動画です。
動画公開日: 2022年2月12日
動画概要欄: 「なぜ梅谷四郎兵衞先生は心ない陰口を言われたのか。そのナゾに迫りつつ、人が誰しも持つ「腹を立てる」ことの意味について考える」
この動画を新しいタブで視聴したい方はこちらからどうぞ↓
https://www.youtube.com/watch?v=2aLaieZH0Ng
茶木谷吉信先生講話「人がめどか」のご逸話をめぐって【文字起こし】

ハイ。皆さん、こんにちは。
今日も、『逸話篇』をめぐってですね、色々と、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
過去動画「目に見えん徳」内の訂正箇所に関して
今日、取り上げるご逸話の話をする前に、ちょっと皆様方に、お詫びをしなきゃいけないことが、実はあります。
実はですね、私、以前 に、「目に見えん徳」っていう山中こいそさんのお話をさせて頂いたんですけど、その一番最後にですね、ぜひ、ご自分で「山中こいそ」さんのことを調べてみて下さいって(言いました)、
(そうすれば)このご逸話が、もっとグッと心に響いてきますよ、って申し上げたんです。その時に、ヒントとして 『天理教事典』に書いてあります、っていうふうに、僕、言ってしまったんですけど、その後ですね、 何人かの視聴者の方からお声がありましてね、
『天理教事典』に「山中こいそ」ってどこにもないぞ、っていう…(笑)で、私、エェッ!?と思ってビックリして調べてみたら、本当にありませんでした。
すいません。申し訳ございません。私の勘違いでした。正確にはですね、敷島大教会が出している『山田こいそ伝』っていう本があります。
そこに詳しく書いてありますので、ぜひ、これは、 何かの伝手をね、利用してお読みになって頂くか、あるいは、天理図書館に行けばありますので、ちょっと、ぜひ、ご自分で調べて頂きたいと思います。
調べる楽しさって、やっぱり、あると思うんですね。
ぜひ、これは、 皆さんで味わって頂きたい、っていうふうに思います。私がね、一番言いたいのはね、
やっぱり、『逸話篇』の中に出てくる先人の先生方のエピソードっていうのは、長~い人生の、ワンシーンなんです。
だから、そのワンシーンが、こぅ出てくるために、この逸話に出てくる先人の方は、どういう人生をたどってきたのかっていうのは、すごく、私は、大事な部分だと思ってるんですね。だから、これはおやさまの『逸話篇』ですけれども、登場人物の、その人生を、 やっぱり、しっかりと読んでいくということが、とても大切だと思います。
今日のお話も、実は、そういうお話なんです。
では、今日の話に移っていきたいと思います。
『天理教教祖伝逸話篇』123番「人がめどか」というご逸話
今日取り上げるご逸話は、『逸話篇』123番の「人がめどか」というご逸話です。
これ、私、読んで、すごく、最初不思議に思ったんです。
まぁ、何はともあれ、この逸話をですね、皆さまも味わってみてください。そして、不思議だなと、僕はどこでそう思ったのかっていうのを、ちょっと想像しながら、お聴きたいと思います。
それでは、このご逸話を、いつものように味わってみて下さい。
どうぞ。
123 人がめどか
教祖は、入信後間もない梅谷四郎兵衛に、
「やさしい心になりなされや。人を救けなされや。癖、性分を取りなされや。」
と、お諭し下された。
生来、四郎兵衛は気の短い方であった。
明治十六年、折から普請中の御休息所の壁塗りひのきしんをさせて頂いていたが、
「大阪の食い詰め左官が、大和三界まで仕事に来て。」
との陰口を聞いて、激しい憤りから、深夜、ひそかに荷物を取りまとめて、大阪へもどろうとした。
足音をしのばせて、中南の門屋を出ようとした時、教祖の咳払いが聞こえた。
「あ、教祖が。」
と思ったとたんに足は止まり、腹立ちも消え去ってしまった。
翌朝、お屋敷の人々と共に、御飯を頂戴しているところへ、教祖がお出ましになり、
「四郎兵衛さん、人がめどか、神がめどか。神さんめどやで。」
と、仰せ下された。
ハイ、 いかがでしたか?
私が、どこが不思議だなと思ったのか。ただ読んでしまったら、「フーン」と読んでしまって、「フーン」で終わってしまうんですけど…
誰がこんな意地悪なことを言ったのか
私は、この逸話のどこに疑問を持ったのか、っていうか、不思議に思ったのか、っていうのは…、
実はですね、誰がこんな意地悪なことを言ったんだろう、っていう、その一点なんです。
だって、そうじゃないですか。
これ、明治16年 の中南の門屋からご休息所に移った時、ご休息所という所を作っている時の、ひのきしんの活気のある、そういう場面での出来事です。
みんなも喜び勇んでですね…。
当時、おやさまは、中南の門屋という所にお住まいになっていました。が、官憲が来て、ドンドンドンと、こぅ、扉をたたく、そのすぐ横にですね、おやさまはご起居なさっていたんですね。
だから、当時の信者さんとしては、もぅ悲願ですよね。
夜ぐらいは、せめてゆっくりお休み頂きたい、という思いで、ちょっと奥の方に、ご休息所っていうのを建てて、もぅ、みんな勇んでひのきしんをしてる、と。ぜひですね、これ、お知りになりたかったら、実際に、記念建物として、今、残っています、教祖殿の裏側にですね。
で、あの建物の…、建物の位置関係というのは、当時の縮尺をそのまま移築してありますので、あれを見て頂くと、 どこにご起居なさっていたのか、おやさまがどこに移られたのか、といった、そういう位置関係、距離関係も分かりますので…。ハイ。
ぜひ、一回、そういう目で、あの記念建物を拝観して頂きたいと思いますが…。ハイ。
ぜひ行って下さい。ハイ。で、ドンドンドンドンって叩く、ここに寝起きなさっている、
それを、少し奥の方に、ちょっと静かな所にお休み頂きたいっていう、もぅ、ホントね、熱誠あふれる、ひのきしん精神で、みんな集まって来ているわけですね。で、もちろん、梅谷四郎兵衛先生も、そこに行かれたわけですよ。
ところが、「大阪の食い詰め左官は大和三界まで…」っていうふうな悪口を言われてしまう。
なんでそんなこと言ったんだろう。誰が言ったんだろう…
あの…、誰がっていうのは…
実は、もうほとんど(笑)、ほとんど…特定されておりますが、 2説あるんですよね。私ね、これね、誰に聞いてもね、 これ、ちょっと詳しくは言えませんけど、言えませんけど…と(言いながら)言っちゃいますけど…(笑)。
ヒント。
ある女性じゃなかったのか、っていう…。
たぶん、誰に聞いても、そうお答えになるんです。
僕も、そう思い込んでたんです。そうしたらね、ある先生に聞いたら、「いや、違う 違う…」と仰るんですよね。
あれは…、名前は言えませんから…、
まぁヒントとしては、 男性だったという…そういう説もあるんですね。ハイ。…でも、まぁ、ほぼ…、この、誰が言ったのかっていうのは…、
ほぼ、このお二人に絞られてるっていう…、まぁ、話なんですけれども。
梅谷四郎兵衛先生が決して「食い詰め左官」などではないことは、周知のことだった
まぁ、その…、そもそも、梅谷四郎兵衛先生って、食い詰め左官でも何でもないんですよ。
この、梅谷四郎兵衛先生の話を少ししますけど、
お生まれになったのは、弘化4年1847年なんです。そして、14歳からね、左官の弟子に入られて、めきめき腕を上げられてですね、
そして、慶応元年1865年に「左官四郎」っていう棟梁の…、棟梁を引き継がれるわけです。これ(生まれた年と棟梁を引き継いだ年を)引き算してみて下さい、これ。
18。満18歳で…。
若いでしょ?「左官四郎」の棟梁になられたんです。
それっくらい腕のいい、左官の棟梁さんなんですよ、この人。その後、事情がありましてね。
実は、この方、養嗣子に入られる…浦田家というところに養子に入られるんですけれども…、
そこでちょっと、お家騒動 みたいなことに巻き込まれて、
で、奥さんのおタネさんと一緒に独立なさるんですよね、その「左官四郎」を出てですね。で、そういう経歴のある方なんですけれども、
その、みんな一所懸命やってるのに、なんで、そんな悪口を言われなきゃいけないのか。
食い詰め左官でも何でもないのに…。で、そのことは皆知ってたはずなのに…。大阪の超有名な…。
あのね、左官の棟梁って、どういう仕事をするかっていうと、これ、ただの壁塗りだけじゃないんですよ。
例えば、棟梁ともなると、床の間の、例えば、床柱があるでしょ?
で、床柱のこの色に対しては、この壁の色が合いますね、とか、ね。
この壁の色だったらこの掛け軸が似合いますよ、とか、
そういうことがアドバイスできるぐらいの文化人でなかったら、左官の棟梁なんかできないんですよ。それだけのプライドを持って、大阪でやっておられたこの梅谷四郎兵衛先生に、
「大阪の食い詰め左官が…」って言っちゃった人がいるわけです。
梅谷四郎兵衛先生に対する陰口は、何らかの意見の対立から出てきたものかもしれない
ここはね、僕、全然わかんなかったんですよ。
食い詰め左官でもなんでもない。「をやこでもふう/\のなかもきよたいも みなめへ/\に心ちがうで」
これ、『おふでさき』5号の8番なんですけど、
だから、みんなそれぞれ、心が違う、違うんですよね。だから、人が2人いたら、意見のぶつかり合いは、当然あります。ハイ。
だから、ここで、この場でも、何かの意見がぶつかったんじゃないかと、僕は、実は思ったんです。
だからこそ、そういうトラブルに巻き込まれてしまった…、と、僕はそういうふうに思ったんですね。
で、実は、みんな一所懸命に、おやさまのために、と思ってやってるわけでしょ?
これね、実は、一所懸命だからこそ、ぶつかるんです。
そういう場面ってありませんか? 一所懸命だからこそ、ぶつかってしまう。
例えば、この梅谷四郎兵衛先生だったら、
大阪の棟梁ですから、超有名な左官さんですから、やっぱり材料とか使う時も、やっぱ、こぅ…、ちょっとこぅ…何ていうんでしょう…、
大和のね、本当は、そんな立派な建物(笑)っていうか…、
それほどこだわらなくても…材料にこだわらなくてもいい…
(と考える人が多いと思われる中で…)でも、梅谷四郎兵衛先生にしてみたら、最高の材料を使って、最高の仕事をするのが、やっぱり、何よりのひのきしんだと思っておられるわけですね。
梅谷四郎兵衛先生っていうのは、入信は明治14年なんです。
明治14年2月なんです。で、なんと、その同じ年、明治14年の4月には、かんろだいの石曳きのひのきしんを任されておられる。
すごいんですよ。山のてっぺんからね、麓(ふもと)までは、真明組の井筒先生かな…。
それから、麓からお屋敷までは、明心組の梅谷四郎兵衛先生が任されてる…。
入信2ヶ月目ですよ。かんろだいの石曳きのひのきしんって、1人や2人じゃ出来ないですよ。
たった2カ月で、それだけの人を集めて、それだけのことが出来るっていう、やっぱり、力量を持っておられたんですね。
そういう、人が、やっぱり集まってくる魅力を持っておられたんだと思うんです。だからこそ、入信 2ヶ月目で、そういうひのきしんを任せられるぐらいの、もぅとにかく、日の出の勢いで、やっぱり、こぅ…やってる人ですよね。
だから、そういう人が、一所懸命一所懸命、こぅ、やってるわけですよ、プロの腕にかけて。
ところが、ホラ、『逸話篇』さっき朗読聞かれたと思うんですけど、
「四郎兵衛は、生来、気が短い方であった」って書いて あったでしょ。
この方、気が短い人なんです。だから、例えば、当時、壁塗りに関していえばですよ、
壁塗りに関していえば、当然、やっぱり、梅谷四郎兵衛先生を中心に、ひのきしんが回っていったはずですよね。あとはみんな、そんな、壁を 塗ったこともないような人が、ひのきしんに来てるわけですから。
ところが、生来、気の短い梅谷四郎兵衛先生が、ついつい、何かこぅ、厳しい事を言ったりする場面がありはしなかったのか。
「あ、そこはそういうふうに塗るんと違う。あ、それ、壁土、もっとこういうふうに捏ねてもらわんと困る…」とか、
そういう、こぅ、“アァ~”って、こぅ、言っちゃった場面がなかったのか、っていうことですね。それを、例えば、こぅ、聞いた…
だって、アレですよ、これ(梅谷四郎兵衛先生が)14年に入信して2年目ですよ。中南の門屋からご休息所に移られる、そのご休息所のふしんっていうのは明治16年の話ですから。入信2年目なんですよ。
ところが、文久年間から先に入信していた人は、もぅここで20年の差があるわけです。
20年も昔から信仰してて、オギャーと生まれた子供が成人する、それぐらいの長い年月信仰している人と、たった入信して2年目で…、(その)2年目の人が一緒のひのきしん現場をやってる。
しかも、音頭を取ってるのは、梅谷四郎兵衛先生。(それは)やっぱりね、いろんな、こぅ、感情のね、こぅ、行き違いとかそういうのが、やっぱ、あったんじゃないかと、僕、思うんですね。
だからこそ梅谷四郎兵衛先生は、そういう、こぅ、心ないことを言われたのかもしれん…。
本当はですね、その言った人だって、そういうことを言うつもりで言ったわけじゃないかもしれない、と僕思ったんです。
例えば、ある人が、
「あの梅谷さんからこんなん言われた」って来た人を、なぐさめるための言葉だったのかもしれない。「そぅ言うな、言うなって…。もぅねぇ…。大阪あたりで、もぅ食い詰めてここに来てんねやから…、もぅ、そんな気にすんな…」
って、言ったのかもしれない。ウン。でも、それが耳に入って、カ~ッと、こぅ怒られた、っていうこと…なのかもしれない。
いろんな場面が想定されるんだけれども、想像できるんだけれども、
結局は、やっぱり、いろんな、その悪口言われた裏にあるエピソードというか、ドラマというか、そういうのがやっぱり、あったんじゃないかと思うんですね。だからこそ、一所懸命だからこそ、ぶつかってしまう。
これは、あるんですよ。
似たような光景は、私たちの身近でも繰り広げられている
あぁ、なるほど、そうか、って。
そういうことがあるなぁ…と、僕思った時に…
やっぱり、似たようなね、光景が、僕らの教会の中にも、やっぱりあるんですよ。例えば、あるね、小料理屋の女将さんに「にをい」が掛かったとしますよね。
例えば、こぅ、小料理屋の女将さん、つったら、
入信してすぐ、自分の最高のひのきしんが出来る場っていうのは、
例えば、月次祭の直会のお料理をお出しするとか、ね、
そういう所では、やっぱ、小料理屋の女将さんは、「あぁ、私の出番だわ」っつって、こぅ、くるわけですね。で、こぅ、パッと、こぅ、口出しちゃうわけですね。
「あ、そこちょっと、もぅちょっと、この味、お酢入れた方がいいかも…」とか、
「あぁ、盛り付けはね、もぅちょっと、こうしたら、こぅ、綺麗に見えるかも…」とか。ね。そうしたら、ホラ、20年も前からそういうことをやってる奥様は、ね、
表面上はね、
「あー、ホントありがとう」って、
「やっぱり、さすがプロだねぇ、プロだわぁ」とか言ってて(笑)、
心のどこかで、「何よ、新参者のくせに。昨日今日(来たばっかり)のくせに…」って(思うかもしれない…)(笑)(…信仰歴の長い方はそんな口の悪いこと言わないと思うけど…(笑)仮に、)言ったとしますやん。
で、それが…ウン、その小料理屋の女将の耳に入ったとするじゃないですか。
女将さんにしてみたら、そりゃもぅ…(おさまらない)
「私、最高のひのきしんをね、一所懸命させてもらおうと思ってんのに、なんでそんなこと言われなきゃいけないの!?」
って言って、会長さんの所へ
「こんなん言われました!」
って来る。ね。そん時に、会長さんは、
「人がめどうか神がめどうか」って…(笑)
言うかどうかわかんないけど(笑)言うかどうかわかんないけど…ウン。
そういう場面と、これ、ぴったり合うんです。
熱心な人の集まりでは「一所懸命比べ」をしてしまいがち
僕らのまわりにも、これは、起こり得ることなんです。
だから、「一所懸命比べ」をしてしまうんです、ぼくらは。
特に、ひのきしんの場面とか、あるいは、おつくしの場面とかでね。
やっぱり、こぅ、「一所懸命比べ」をしてしまう 。「私、こんだけ一所懸命やってるのに、あの人何よ」
みたいなことを言ってしまう。一所懸命「ひのきしん」してりゃ良いのに、
一所懸命信仰すればするほど「ほこり」を積んでしまう場面がありはしないか、
ということです。これはね、僕らの心に、やっぱり、しっかりと、
何ていうのかな、いつもいつも、僕らの心を…見とかなきゃダメだと思うんですね。
信仰すればするほど積む場面が増える怖いほこり=「高慢のほこり」
だから、「高慢のほこり」っていうのは、ね、
「私、一所懸命やってるのに、あの人は何よ」
っていう、その「高慢のほこり」っていうのは、これは、他の「ほこり」と違うんです。他の「ほこり」はね、一所懸命信仰したら取れていくんです。
(しかし)「高慢のほこり」だけは、信仰すればするほど積む場面が増えてくるって…、
これ、怖い「ほこり」なんです。ハイ。だから、これはね、「高慢のほこり」っていうのは、やっぱり、信仰していて積んでしまうんです。
自分の努力だけでは止めようがないほこり=「腹立ちのほこり」
もう一つ。
この「ほこり」に関して言えば、
この場面でもう一つ、重大な「ほこり」を、梅谷四郎兵衛先生が積んでいる。
それは何か。「腹立ち」です。
「カーッ」とくるでしょ? 「カーッ」と。
これ、やっぱり「腹立ちのほこり」として、やっぱり、神様は戒めておられるんですけど…。だから、この「高慢のほこり」と、それから「腹立ちのほこり」っていうのは…
やっぱり、これはね、それぞれ、人は心が違うので、これ、積んでしまうっていうのはしょうがないんです。じゃあ、どうすればいいんだ? ね。
例えば「高慢のほこり」。
これ、今までずっとお話してきて、「高慢のほこり」は、まぁ、そういうふうに思ってはいけないんだねっていうふうに思って頂いたと思うんですけど…。
でも、この「腹立ちのほこり」って、これはね、止めようがないんですよ。
私、日頃から思ってることがあって…
体、身の内借り物でしょ?これ、自分の自由になるんだけど、心は自由に…(なるけど、体は)自由にならないっていうか、熱が出たら手も動かない(くらいにいなる事もある)んだけど、
心だけは自由を許されてて、心だけは自由に使えるよ、って神様からお許し頂いてる、
っていうふうに聞かせて頂くんですけど…。僕ね、ちょっと(笑)疑問に思うんです。
だって、心、自由になりませんもん。
何か言われて「カーッ」ってくるのは、これはもぅ、自由にならないんです。
もぅ、腹立つ時は立つんですよ。ムカつく時はムカつくんですよ。で、そん時に、「あぁ、またムカついてしまった…」とかね、「あぁ、また切れてしまった」とかね、思ってしまう。
それで、また自分が嫌になってきて、 何かもう、自己嫌悪に陥ってしまう。
そういう経験ないですか?
私、しょっちゅうあります。ハイ。
茶木谷式「心の3階層」説(feel➡think➡consider)
で、私ね、どういうふうに考えることにしたのかっていうと…
これはね、あくまでも、あくまでも、講師の意見です(笑)
(画面に『※あくまでも講師の意見です!』というテロップが出る)あくまでも講師の意見ですけど…、
僕ね、心に「3段階」あると思ってるんですよ。「感じる」、いわゆるフィール(feel)の部分ですね。
フィール(feel)。感じたことをどういうふうに「思って」…=シンク(think)、
シンク(think)ですね。シンク(think)して、
そして「思案」する=コンシダー(consider)ですね。
落とし込んでいく、と。これが、僕は、心の、何か…一つの動きだと、僕、思ってるんです。
心には3階層あるんじゃないか。
感じて(feel)
→思って(think)
→思案(consider)
(というふうに)。で、そういう目で見ると、
『おふでさき』って、非常に厳格に、の3つを使い分けられてるんじゃないか、と、僕思ってます。ハイ。
あくまで講師の意見ですけど(笑)例えば、
「をやこでもふう/\のなかもきよたいも みなめへ/\に心ちがうで」
って…(いう)、この(『おふでさき』の)心が、
僕は、このフィール(feel)の部分だと思うんです。『おふでさき』の中で、「心」っていうのが出てくるのは、フィール(feel)の場面もあるし、
「心を定める」とか、そういう、ちょっとこっち(thinkやconsider)の方の心も使われているんですけど、
この、これ(=先ほどの『おふでさき』の中の心)に限って言えば、
「心ちがう」の「心」は、
これ、僕は、フィール(feel)だと思うんです。感じ方は違うんですよ。
「をやこでも ふう/\のなかも…」。
夫婦が違うのはわかりますよ、所詮、他人だから。でも、親子でも違うし、兄弟も違うんです、フィール(feel)の部分は…。
感じてる部分…。でも、それぞれ違うフィーリング(feeling)を持って、違う感受性を持ってる。
それを、どういうふうに、その、起こった出来事を、思って、シンク(think)、考えて、
それをどぅ、コンシダー(consider)、思案の部分まで持っていくかっていうのが、これが、心の使い方で…僕、ここ(感じる(feel))までは、
フィジカル(physical)じゃないかと思うんです。
「腹立ち」は【feel】=「反射」だから、コントロールしきれない
脳の…、
だって、ニューロンの反射でしょ? ね。パッ と見て「カーッ」と、「カチン」とくるっていう、「ムカッ」とするっていうのは、
これ、反射だもの、しょうがないじゃないすか。だから、それをクヨクヨするよりも、
僕は、あ、これも「反射」だから、ここの脳細胞の「反射」だから、これは体の一部なんだから、しょうがない、と思って…、その…、実は、それを「思って」「思案する」っていう、
こっち
(思う(think)+思案(consider))
の方に重きを置いていった方が、
僕は、いいんじゃないか、と思う…。そうすると、必ず、
このフィール(feel)の部分が鍛えられて、変わってきます。つまり、「カチン」と来てたことが「カチン」と来なくなるっていう…(ふうになっていく)
例えば、ホラ、ウサインボルトがね、足が早い…ね。
あれ、生まれつきね、100m 9秒台で走れたかっていうと、そんなことはないですよ。
あれはもぅ、血のにじむようなトレーニングを重ねてるから、あれだけの反射神経が育つわけです。例えば、ドーンと鳴って、パッと足を動かすまでが0.3秒だったとしますよ。
これを、何回も何回もトレーニングすることによって、これが0.2秒になり0.1秒になっていくっていう…この反射神経がね。
ニューロンの、要するに、こぅ…反射が…。
「思う=think」&「思案=consider」を天の理に添わせる努力を重ねることで、それが「感じる=feel」へ波及し、結果として、腹立ちのような【反射】現象も、より親心に添った姿に変えて頂ける
それと同じで、
この「感じる」って、
その、生来気が短い梅谷四郎兵衛先生みたいな方でも、一所懸命信仰を重ねて、
「思う」(think)「思案」(consider)って、
この「思案」(consider)をずっと重ねていくことによって、
ここ(「思案」=consider)から、
ここ(「感じる」=feel)へ影響が及んで、
「反射」の部分が、実は変わっていくっていうことがあるんじゃないか、
と僕思ってるんです。それが、「何を聞いても、腹が立たんのが心が澄んだんや」って仰る、
おやさまの、何か、意味じゃないか、と思ってて…だから、私たちは、
別に、「感じる」の部分で「カチン」ときてしまっても…、
まぁ、いいとは言いませんけど…それはある意味、しょうがないっていうふうに、僕は、思い変える方が、僕はいいんじゃないかと思ってるんですよ。
その方が、もっともっと、何か良い精神性っていうかな、信仰生活を送れていくんじゃないかって思っています。
あまり、ここ(どう感じるか=feel)にこだわらない方がいいと思います。
だからといって、ムカついてもOKって、そういう意味ではありませんので…(笑)
それはやっぱり、少しずつね、こぅ、信仰生活で、その辺は少しずつ変えていかねばなら ない部分…(だと思います)。
また変わっていきます、自然に。
やっぱり、一所懸命おたすけをさしてもらったり、信仰生活続けていくと、
必ず、ここ(どう感じるか=feel)の部分は、やっぱり変わってくるんじゃないか、
というふうに思っています。
ありがとうございました
今日はですね、『逸話篇』 123番「人がめどか」っていうお話から、
また、いつものように(笑)、こういうところ(心の3階層説)まで話を 広げて…、話をしてみましたけれども…まぁ、何かの参考にして頂けたらいいかなぁ、というふうに思っています。
今日の話も、この本(『世界たすけに活かすおやさまご逸話』)に載っています…(笑)
(と言って、自著本(『世界たすけに活かすおやさまご逸話』)を掲げる)ハイ。今日も、最後までお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
じゃあ、これで今日は終わります。
陽気チャンネル>茶木谷吉信先生「人がめどか」ご逸話をめぐって
ありがとうございました。

今回も、ご逸話の背景を掘り下げて下さる、素晴らしいお話でした。
以上、「【逸話篇の世界を旅する14】茶木谷吉信先生「人がめどか」ご逸話をめぐって」
というYouTube動画の【文字起こし】でした。
動画を視聴しての感想

茶木谷先生の【逸話篇の世界を旅する】動画シリーズでは、『天理教教祖伝逸話篇』の中の様々なご逸話について解説して下さっているわけですが、
先生のお話を聴く前と後で、同じご逸話でも全く異なる景色が広がって見えるような気がします。
「人がめどか」というご逸話については、
私は、陰口を叩かれて腹を立て立ち去ろうとした梅谷四郎兵衛先生を、おやさまが優しく諭されたご逸話、程度の認識しか持っておりませんでした。
しかし、今回、茶木谷先生による、このご逸話の登場人物や当時のおやしきの状況等の背景を深掘りするお話を伺って…
それまで見えていなかった、当時のおやしき周辺の人間模様が、急にリアルに、私たちの眼前に立ち上がってくるように感じられました。
茶木谷先生のお話を元に、改めて、当時のおやしきの環境をイメージしてみます。
梅谷四郎兵衛先生は、決して「食い詰め左官」などではなく、大阪の高名な左官の棟梁だった。
その時の梅谷四郎兵衛先生は、まだ入信2年目。
信仰歴は浅いながらも、自身の特技を活かせる場ということもあり、10年20年といった長い信仰歴を持つ人々の中に混じって、御休息所ふしんのひのきしんに取り組んだ。
入信2年目と信仰歴は浅いながらも、ふしんの作業にあたっては、職歴上、音頭を取る立場になった。
しかし、当時のおやしきでひのきしんに励んでいたのは、大半が、のどかな大和の農家の人々。
生来短気な性格で、しかも大阪の高名な左官の棟梁である梅谷四郎兵衛先生と、古くからおやしきに勤めているその他の人々とでは、気質や考え方が大きく異なる。
異質な空気を持つ梅谷四郎兵衛先生が、長年おやしきでひのきしんに励んでいた人々に指図をするにあたっては、
梅谷先生の信仰歴の浅さも手伝って、長い信仰歴を持つ人々との間でいろいろ摩擦が生じやすい状況だった…
茶木谷先生のお話から、以上のような当時のおやしきの状況が浮かび上がってきます。
そのような環境だったということを踏まえて、改めて、この「人がめどか」というご逸話を読んでみます。
すると…
本当に、お話が立体的に感じられますよね。
当時、おやさまの周りで勤めておられた先生方は、その多くが、道の先人として、「後に」天理教コミュニティにおける指導的な立場に立たれた方々。
しかし、本教において「元なるぢば」と崇められる聖地を抱えるおやしきであっても、
その当時は、決して、世俗から遊離した聖なる場所などではなかった。
生き神様「おやさま」がおられはするものの、
それを取り巻く周囲の人々は、悟りを開いた聖人君子ではなくて、複雑な人間関係に絡み取られ、泣いたり笑ったりしている、今の私たちと変わらぬ、悩み多き「迷える子羊」だった…。
茶木谷先生の解説を伺って、僭越ながら、そんな感想を抱きました。
しかし、決して私たち一般人と別世界の話ではないからこそ「このご逸話は尊い」と言えるのだとも思います。
たとえどんな「聖地」「スピリチュアルスポット」「パワースポット」に身を置いたとしても、
その者の心が、その「聖地」を取り巻く【人間】の方を向いたままで、その聖地を「聖地」たらしめている所以=【神】の方へ向いていなかったら、
その聖地、パワースポットから湧き出る「エネルギー」を受け止めることは出来ない。
茶木谷先生の「人がめどか」というご逸話をめぐるご講話を通して、
改めて、私は、そのような学びを得ました。
時代の経過と共に、天理教には多くの人が寄り集うようになり、組織が巨大化しました。
ですから、それに伴って、その中に引き寄せられた者たちは、当時の人々以上に、
【人間】の方ばかりに心が向いてしまう危険性が強い環境にある、
と言えるかもしれません。
そんな状況に置かれている私たちですから、
自分の心が、聖地を取り巻く人間ではなくて、ちゃんと【神】=「天の理」の方を向いているか、
常に「自問自答」を繰り返していく必要がある。
このご逸話からは、そうした教訓を引き出すことも出来そうです。
また、熱心な人が集まると「一所懸命比べ」をしてしまいがち、
という茶木谷先生のご指摘も心に刺さりました。
梅谷四郎兵衛先生もその他のおやしきの先生方も、皆、熱心だからこそ摩擦が生じる。
適当にやっていたら、摩擦なんか生じない。
これは、宗教においては特に「あるある」の現象と言えるでありましょう。
宗教には「熱心な人の集まり」という面がありますから。
この「一所懸命比べ」というのも、
視点が神様の方ではなくて、人間の方を向いていればこそ起こり得る現象、と言えるかもしれません。
神様をめどにしていれば、人と比べる必要はないですものね。
せっかくの「一所懸命」という尊いエネルギーなのに、それによって心に苦痛を生じさせるのは、あまりに勿体ない。
「一所懸命」のパワーによって多くの人が明るい気持ちになれるためにも、
人と「一所懸命」を比べるような心にならないように心掛けたいものであります。
人をめどとすることなく神様をめどにして歩む、そのことの大切さを、改めて肝に銘じたい。
今回のお話を拝聴して、そのように痛感しました。
そして、
ご逸話から広がった内容である
【茶木谷式「心の3階層」説】
(feel➡think➡consider)
これも、実に勉強になりました。
これは、このご逸話の主題そのものではなく、そこから派生した内容ですが、
非常に興味深く拝聴させて頂きました。
さすが茶木谷先生のお話は深いです。
特に、「ほこり」の心に対する、茶木谷式「心の3階層」説による分析は、本当に勉強になりました。
次項「まとめ」欄に、自分なりの要約を「覚え書き」的に箇条書きしておきたいと思います。
心や意識を深掘りしていくと、スピリチュアルや精神分析等の深い話に入っていきそうです。
それはそれで興味深く、勉強していきたいと思いますが…
今回の記事は長くなりましたので、このあたりで切り上げることにします(^^;)
まとめ(今回の動画を通しての学び)

「茶木谷吉信先生『人がめどか』ご逸話をめぐって」【YouTube動画からの学び】
- 時代の経過と共に、天理教には多くの人が寄り集うようになり、組織が巨大化した。
なので、それに伴って、その中に引き寄せられた者たちは、
当時の人々以上に、
【人間】の方ばかりに心が向いてしまう危険性が強い環境にある。
- そんな状況に置かれているのが現在の私たちだから、自分の心が、聖地を取り巻く人間ではなくて、ちゃんと【神】=「天の理」の方を向いているか、
常に自問自答を繰り返していく必要がある。
- 熱心な人の集まりでは
「一所懸命比べ」をしてしまいがち。
- 「一所懸命比べ」というのも、
視点が神様の方ではなくて、人間の方を向いていればこそ起こり得る現象と言える。
- 神様をめどにしていれば、人と比べる必要はない。
- せっかくの「一所懸命」という尊いエネルギーなのだから、
それによって心に苦痛を生じさせるのはもったいない。
- 「一所懸命」のパワーによって多くの人が明るい気持ちになれるためにも、
人と「一所懸命」を比べるような心にならないように心掛けたい。
- 人をめどとすることなく「神様をめどにして歩む」
そのことの大切さを改めて肝に銘じよう。
【「ほこり」の心遣いの分析】
- 信仰すればするほど積む場面が増える怖いほこり
➡「高慢のほこり」
- 自分の努力だけでは止めようがないほこり
➡「腹立ちのほこり」
- 「腹立ち」は【feel】=「反射」だから、コントロールしきれない
- 心には3階層ある。
①感じる(feel)
➡②思う(think)
➡③思案(consider)
- 「思う=think」
&
「思案=consider」
それを天の理に添わせる努力を重ねることで、
それが「感じる=feel」へと波及し、
その結果として、
腹立ちのような【反射】現象も、
より親心に添った姿に変えて頂ける
以上、茶木谷吉信先生による
【逸話篇の世界を旅する】動画シリーズ>
「【逸話篇の世界を旅する14】茶木谷吉信先生「人がめどか」ご逸話をめぐって」
のYouTube動画を【文字起こし】して、そこから自分が学んだことをまとめました。
茶木谷吉信先生の著作『世界たすけに活かすおやさまご逸話』では、
この「人がめどか」というご逸話の【後日談】として
「講社のめどに」というご逸話がある、
と紹介されていました。
最後に、それを紹介して終わりたいと思います。
126 講社のめどに
明治十六年十一月(陰暦十月)御休息所が落成し、教祖は、十一月二十五日(陰暦十月二十六日)の真夜中にお移り下されたので、梅谷四郎兵衞は、道具も片付け、明日は大阪へかえろうと思って、二十六日夜、小二階で床についた。
すると、仲田儀三郎が、緋縮緬の半襦袢を三宝に載せて、
「この間中は御苦労であった。教祖は、『これを、明心組の講社のめどに』下さる、とのお言葉であるから、有難く頂戴するように。」
とのことである。
すると間もなく、山本利三郎が、赤衣を恭々しく捧げて、
「『これは着古しやけれど、子供等の着物にでも、仕立て直してやってくれ。』との教祖のお言葉である。」
と、唐縮緬の単衣を差し出した。
重ね重ねの面目に、
「結構な事じゃ、ああ忝ない。」
と、手を出して頂戴しようとしたところで、目が覚めた。
それは夢であった。
こうなると目が冴えて、再び眠ることが出来ない。
とかくするうちに夜も明けた。
身仕度をし、朝食も頂いて休憩していると、仲田が赤衣を捧げてやって来た。
「『これは、明心組の講社のめどに』下さる、との教祖のお言葉である。」
と、昨夜の夢をそのままに告げた。
はて、不思議な事じゃと思いながら、有難く頂戴した。
すると、今度は、山本が入って来た。
そして、これも昨夜の夢と符節を合わす如く、
「『着古しじゃけれど、子供にやってくれ。』と、教祖が仰せ下された。」
と、赤地唐縮緬の単衣を眼前に置いた。
それで、有難く頂戴すると、次は、梶本ひさが、上が赤で下が白の五升の重ね餅を持って来て、
「教祖が、『子供達に上げてくれ。』と、仰せられます。」
と、伝えた。
四郎兵衞は、教祖の重ね重ねの親心を、心の奥底深く感銘すると共に、昨夜の夢と思い合わせて、全く不思議な親神様のお働きに、いつまでも忘れられない強い感激を覚えた。

123「人がめどか」と、126「講社のめどに」
以上2つのご逸話セットで、一つのストーリーを味わうことができますね。
私たちの悩みや苦しみ、
必ず、おやさまは、
「ひながた」にその解決法を残してくださっています。
困った時は「ひながた」を勉強しましょう。
そこに必ず、解決策があります。
今回の「彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】」は、
「『人をめどとすることなく、神様をめどにして歩む』そのことの大切さを、改めて肝に銘じるべし。」
ということについての学びの記録でした。
人生、死ぬまで勉強。
今後も、勉強し続けていきたいと思います。
ではでは、今回はこのへんで。
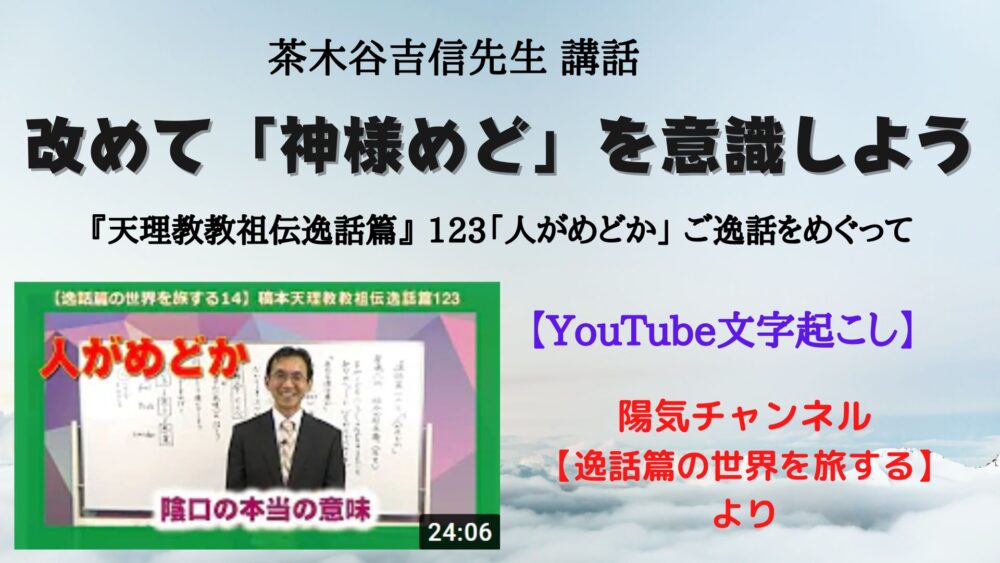
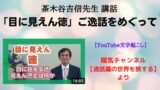
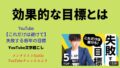

コメント