Dear everyone,
こちらは、
ふらふら彷徨う「さまよい人」による
『さまよいブログ』
= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。
今回も、
『天理教事典』(1977年版)に記載された
各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。
私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)
最新版👇
このシリーズを始めた理由については、
当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。
前回は、
教会番号71番「岐美大教会」の『天理教事典』記述を書写して
その歴史を勉強しました。
今回は、
教会番号72番「熊本大教会」について勉強します。
- 熊本大教会(くまもと だいきょうかい)
- 熊本大教会の発祥(明治18年)
- 友井常八 初おぢばがえり〜泉田藤吉への 布教師 熊本派遣依頼(明治19年〜明治20年)
- 堤 豊賀 初代会長と 友井常八のつながり
- 熊本市上林町における集談所の設置(明治21年)
- 井村徳次郎、熊本の集談所へ赴任(明治21年)
- 熊本集談所の隆盛〜官憲の迫害(明治21年頃)
- 井村徳次郎の離任〜堤 豊賀の黒田ツイ訪問=天龍講との出会い(明治21年)
- 熊本における集談所、天龍講へ(明治21年)
- 第5号天龍講 第1号講社の開設(明治21年)
- 堤 豊賀 初代会長が歩んだ教祖ひながたの道(明治22年頃)
- 拡大する伝道線〜集談所の移転(明治22年〜明治23年)
- 参拝者を連れてのおぢばがえり(明治24年〜明治25年)
- 熊本支教会の開設(明治26年〜明治27年)
- 部内の開設(明治27年〜明治28年)
- 教会の移転ふしん(明治27年〜明治28年)
- 友井常八、堤 豊賀の養子となり 堤 常八へ(明治30年)
- 教勢拡大に伴う迫害弾圧の増大(明治30年代)
- 教祖殿の建築(明治34年〜明治35年)
- 熊本分教会へ改称(明治42年)
- 満州の道(明治末期〜大正時代)
- 堤 豊賀 初代会長の出直し、堤 常信2代会長の就任(大正11年)
- 創立30周年記念祭(大正12年)
- 広がる熊本の道(大正後期〜昭和初期)
- 熊本大教会への昇格(昭和15年)
- 堤 常信2代会長の出直し、堤 信次3代会長の就任(昭和16年)
- 堤 信次3代会長の軍隊召集、夫人の会長代務者就任(昭和18年〜終戦後)
- 神殿ふしん(昭和25年頃〜昭和27年)
- 教祖70年祭〜堤カズエ4代会長就任奉告祭(昭和31年〜昭和42年)
- おわりに
熊本大教会(くまもと だいきょうかい)

熊本大教会の発祥(明治18年)
熊本大教会の発祥は、明治18年(1885) に始まる。
明治17年秋より
熊本市京町1丁目80番地在住の 友井常八は 肺病にかかり、
八方手をつくしたが 病状は悪化する一方であった。翌(明治)18年 5月に
(友井常八は) 遂に 命旦夕に迫まる という状態になった。丁度この頃、
大阪天恵組の講元・泉田藤吉の周旋として信仰していた
土建業の 大阪 大溝組の石工棟梁・北田常吉
という人が (熊本に)いた。(この時) この人(北田常吉) は、
熊本鎮台病院 南側の 高石垣修理を請負って大阪より出張して(熊本に)来ていて、
熊本市下通町に宿をとって 毎日 工事現場に出かけながら、
夜、宿で布教していた。
(それは) 当時、その地で 評判になっていた。友井常八の父・松永一二の耳に そのことが入って、
(松永一二は 北田常吉に、息子・友井常八の) おたすけを乞うた。しかし、北田(常吉)は 非常に多忙であったので (なかなか訪問することができないとのことであった。
そこで、松永一二は) 瀕死の病人(友井常八) を車に乗せて (自ら北田常吉の元へ出向いて)行った。
そうしたところ、
(友井常八は) ただちに鮮やかな御守護を頂いて(一同は歓喜に包まれた。
感激した友井常八は) 第2夜目からは 自ら歩いて行くほどになった。その後、北田(常吉)が (熊本市) 花岡山へ移転してからも、
友井(常八) は (北田常吉のもとへ) 一夜も欠かさず通い続け、(天理教の) 話を聞いた。この 友井常八の病気の御守護こそ、
熊本大教会の発祥の機縁となったものである。
友井(常八)は、当時 25歳であった。
友井常八 初おぢばがえり〜泉田藤吉への 布教師 熊本派遣依頼(明治19年〜明治20年)
北田常吉は、同年(明治18年) 8月、
熊本の工事を終え、大阪へもどった。友井(常八)は、(瀕死のところをたすけられた感謝の思いから) 天理教布教師として生きることを決意。
(その思いから) おぢばがえりの念 止み難く(なり)、
明治19年3月、
(おぢばへの道を求めて)
北田(常吉) より教えられた 大阪南区瓦屋町の 泉田藤吉を訪ねた。
(残念なことに) この時、(瀕死だった友井常八のおたすけをした) 北田(常吉) は、すでに出直していた。友井(常八)は、
泉田(藤吉) の世話で おぢばに帰った。
(そして、おぢば帰りの感動を胸にたたえ おぢばから)熊本にもどるや否や、直ちに にをいがけに回った。(友井常八は懸命に布教に歩いたが、なかなか) 思うようには行かなかった。
(そこで)
明治20年9月(に)、
(友井常八は、再び) 泉田(藤吉)の所へ寄り、熊本へ誰か(布教師)を 派遣してほしいと 依頼をした。
しかし、(その時は) 家庭の事情もあって、容易にその都合がつかなかった。
堤 豊賀 初代会長と 友井常八のつながり
(熊本大教会) 初代会長となる 堤 豊賀は、
嘉永2年3月15日、
熊本県 玉名郡 板楠村に出生(した)。(成人)後、陸軍々吏・高木市蔵の妻となった。
(堤 豊賀の夫である) 高木市蔵は、
熊本鎮台在勤中に 鎮台の御用商人であった 友井常八の父・松永一二と つながりがあった。
友井(常八)も (熊本)鎮台に勤務した事があり、高木(市蔵)と松永親子の関係は、昵懇の間柄であった。高木(市蔵)は、(熊本鎮台の勤務を終え東京へ)転勤(した)後、東京で出直した。
堤 豊賀は、(夫・高木市蔵が東京で出直した後)
明治20年の夏、(生まれ故郷の) 熊本にもどった。
寡婦としての頼りなさから、
(自然と) 亡夫と昵懇の間柄であった 松永一二とも交流(するようになった。)それに伴い (松永一二の息子である) 友井常八も 堤 豊賀宅に出入りするようになり、
堤(豊賀)は、友井(常八)から 天理教の話を聞くようになった。
熊本市上林町における集談所の設置(明治21年)
堤 豊賀は、
友井(常八から、自らの病をたすけてくれた尊い教えを熊本の地に広めたいとの 熱い思いを聞いて、
友井常八)の長年の念願である布教に同意(し、協力することとした)。(そして)
明治 21年、熊本市上林町に家を借りて、集談所を設置した。
井村徳次郎、熊本の集談所へ赴任(明治21年)
こうして(集談所を設置することとなったので)、
(堤 豊賀と友井常八は)
かねてより 大阪 天恵組 講元・泉田藤吉に依頼していた教師の派遣を (改めて)懇請した。そうしたところ、泉田(藤吉)の委嘱により、
井村徳次郎が (熊本へ) 出張することとなった。井村(徳次郎) は、元・天竜講 奈良第1号講元の周旋であったが、事情あって 大阪に転住していた。
大阪の転居先が (たまたま) 天恵組の集談所の付近であったので、
(井村徳次郎は) 始終 泉田(藤吉)の家に出入りしていた(のだった。その関係で、泉田藤吉と井村徳次郎には信仰的交流があった。
泉田藤吉は、堤 豊賀と友井常八からの熊本布教師派遣依頼に応えるにあたって、井村徳次郎を見込んで白羽の矢を立てたというわけである)。
熊本集談所の隆盛〜官憲の迫害(明治21年頃)
(泉田藤吉から委嘱されて、井村徳次郎が熊本の集談所へ赴いたわけだが)
その後、この集談所には、不思議な たすけを頂く者が次々と現れた。
(このことが評判となり) 集談所への参拝者は みるみる増加した(のだった)。この隆盛が警察の目にとまり、
(警察は) 井村(徳次郎)・友井(常八)を、
妄りに人を集めた事と医薬妨害のかどで 連行した。
井村徳次郎の離任〜堤 豊賀の黒田ツイ訪問=天龍講との出会い(明治21年)
こうした事もあって、井村(徳次郎)は 教導職の必要を痛感した。
(井村徳次郎は) 教師補命の手続を踏むため、おぢばに帰ることになった。(井村徳次郎は) 堤 豊賀に、
今後については、天竜講 奈良第1号講元・黒田ツイを頼り、一度 おぢばに帰るように と言い残し(て熊本を離れ)た。明治21年9月、
堤 豊賀は、(井村徳次郎の言葉を受けて) おぢばにかえり、
井村(徳次郎)より聞いていた 奈良の 黒田(ツイ)講元を訪ねた。黒田(ツイ)講元の案内で (堤 豊賀は) 月次祭にも参拝し、
(黒田ツイから) 郡山の 平野(楢蔵) 天龍講長にも紹介された。
熊本における集談所、天龍講へ(明治21年)
(もともとは、泉田藤吉・大阪天恵組の北田常吉による友井常八の身上おたすけから始まった熊本の道であったが)
種々 折衝の結果、
(友井常八の熱意から創まった集談所は)
天龍講の系統として、平野(楢蔵)講長が預かるということになった。(堤 豊賀は) 郡山の洞泉寺の集談所に 1ヵ月滞在の上、
郡山 天龍講より教師派遣を受ける事になり、
(明治21年) 11月、教師・飯原久吉の同道で、熊本へもどった。
第5号天龍講 第1号講社の開設(明治21年)
そして、(熊本に戻った堤 豊賀は)
熊本市内坪内町119番地に 5号天竜講 第1号講社を設け、
友井(常八)も (それに)参加し、日夜 布教につとめた。現・東肥大教会の初代、山内次三郎は、
この時代の熱心な信者であった。奈良県平群郡椎木村第40番地、5号天竜講の講長・飯原久吉が、
(第1号講社の開設にあたって)
約半年、熊本に滞在。
(飯原久吉は)
種々の仕込みや指導をなし、
明治22年2月、郡山の開筵式の準備のため、郡山へもどった。
堤 豊賀 初代会長が歩んだ教祖ひながたの道(明治22年頃)
こうして(堤 豊賀) 初代会長は 布教に精励し、
そのたすけに浴した信者が 続出した。(堤 豊賀は、布教に一路邁進する中で) 東京より持ち帰った衣類、調度品など総て(を)施す行為に及んだ。
(その結果) 明治22年頃には、3度の食事も思うにまかせぬ有様となった。(堤 豊賀は) 教祖が貧に落ち切られたひながたを、
身をもって通ったのである。このような窮乏の中にあって、(堤 豊賀は)
明治22年11月3日、おさづけの理を拝戴(した)。
拡大する伝道線〜集談所の移転(明治22年〜明治23年)
同年(明治22年)には、
長崎県島原に(まで) 伝道線は延び、
(堤 豊賀) 会長自ら 海を渡って 布教に従事(した)。翌(明治)23年11月には 長崎布教を展開し、
その間、熊本市寺原町73番地に敷地を求め、ここに集談所を移した。この(熊本市) 寺原町の布教所こそ、
(後に) 熊本支教会として 最初に教会を置く場所となったところである。
参拝者を連れてのおぢばがえり(明治24年〜明治25年)
明治24年旧正月、教祖5年祭には、
(堤)豊賀が、友井(常八)の他、島原より 2名の信者を伴い (おぢばへ) 参拝(した)。
また、明治25年の教祖の墓地改葬にあたっては、
10数名の参拝者を引き連れて おぢば帰りした。同年(明治25年)、友井(常八)の他 8名が、おさづけの理を拝戴した。
熊本支教会の開設(明治26年〜明治27年)
明治26月3月、平野(楢蔵) 郡山会長 巡教の際、
(堤 豊賀は、平野楢蔵会長より)
熊本講社は、(いまや) 市内は言うに及ばず、遠く 長崎・佐賀・福岡県までも道がついたのであるから、教会設置を願い出るよう 示唆された。(平野楢蔵会長から教会設立を促された堤 豊賀は)
建物の整備やその他に一年間(いただきたい、とそ)の猶予を乞うた。(そして、その一年後)
明治27年(1894) 5月3日、おさしづをもって「熊本支教会」が誕生。
同年(明治27年) 11月19日には、地方庁の認可も得た。
部内の開設(明治27年〜明治28年)
熊本支教会は、(明治27年の認可と)同時に 有明出張所を設け、
翌(明治)28年には、
長崎 及び 佐賀の 2出張所と、
諫早・栄城・小城・唐津・川瀬・清水・大村・稲佐・野母・久米島
以上の 10布教所を設けた。
教会の移転ふしん(明治27年〜明治28年)
(信徒の増加に伴い)
(熊本市) 寺原町の支教会建物も狭小となってきて、信者の間に移転の声が高まってきた。
(そこで) まず 現在の (熊本市) 京町本丁に土地を購入、
明治27年12月12日 (天理教教会)本部の許しを得た。一同は 勇躍して、普請に着手。
まず 教堂より工を起こし、
ついで 客殿、事務所兼住居、炊事場 その他 付属建物の建築に取り掛かり、
(明治)29年の初秋には 完成した姿を現した。そこで、年内に移転する事となり「熊本支教会移転願」が出された。
(願いは) おさしづにより許され、(堤 豊賀) 会長はじめ一同は、
同年(明治29年) 11月24日、
(熊本市) 京町本丁37、38番地 (熊本大教会の現所在地) に 引き移った。明治30年 旧3月15日、
平野(楢蔵) 郡山会長を始め 10数名の役員を迎えて 鎮座祭、
翌3月16日 盛大に開筵式を執行した。
友井常八、堤 豊賀の養子となり 堤 常八へ(明治30年)
この後、明治30年6月20日、
友井常八は、おさしづにより
堤 豊賀 会長の養子となり、堤 常八と名乗るようになった。
(大正11年6月には、堤 常八を 堤 常信と改名した)。
教勢拡大に伴う迫害弾圧の増大(明治30年代)
(教会)移転後、教勢は順調に延び、
熊本・長崎・佐賀・福岡 の4県にまたがり 部内出張所、布教所が設置された。しかし、
(教勢の拡大に伴い) 天理教に対する弾圧が 次第に強くなり、
(部内教会は)
地方庁の認可が思うように下がらず、
名称の移転、再出願が 頻繁に行われた。また、
東北地方に端を発した「金米糖事件」は 遠く九州にも波及し、
堤(豊賀) 会長が 警察へ召喚(された)。
長崎の福重布教所 他2ヵ所は、この事件の余波を受けて、
設立取消解散を命ぜられた。
【金米糖事件】
明治38年(1905) 11月下旬、
青森県南津軽郡で天理教のある婦人布教師が、御供 (ごく) の金米糖をめぐって刑事事件となり、拘留されたという事件。
布教に出た婦人布教師が たまたま警察の取り調べを受けることになった。
持参していた風呂敷包の中から 金米糖が出てきた。
警察で分析の結果、モルヒネが発見されたという廉で 問題とされた。
(『稿本中山眞之亮伝』310~311頁参照)
金米糖の御供は、すでに明治37年4月10日から 洗米に変更されていたのであるが、
遠隔地の青森のことゆえ、この変更が徹底されず、この布教師は まだ金米糖を持っていたのである。
教会本部では、ただちに役員を派遣して この事実調査を行った結果、
事実無根のことで、もともと 天理教を攻撃するための中傷であったことが判明し、一件落着となった。
(『天理教辞典』1977年版 P,362)
教祖殿の建築(明治34年〜明治35年)
明治34年 5月22日、おさしづによって、教祖殿の建築が許され、
同(明治)34年 旧5月19日 地ならし、
同(明治)35年 旧3月17日 遷座祭を執行した。
熊本分教会へ改称(明治42年)
明治42年2月、天理教一派独立に伴い、
熊本支教会は 熊本分教会 と改称、
新たに 7ヵ所の 宣教所を設けた。
満州の道(明治末期〜大正時代)
明治末期、
長崎支教会 所属の 鵜殿寛は、満州布教を志し、
大正2年11月1日、満州第1号たる 長春宣教所 を設立した。つづいて 同(大正)6年7月(には)、哈爾賓宣教所 を設立。
満州における布教線を 拡張するようになった。
堤 豊賀 初代会長の出直し、堤 常信2代会長の就任(大正11年)
この頃から (堤 豊賀) 会長の身上がすぐれなくなり、
大正11年(1922) 4月27日、
(堤 豊賀 初代会長は) 74歳で出直した。2代会長には、養嗣子・堤 常信 (旧・友井常八) が就任。
同年(大正11年) 7月24日、本部の許しを得た。
創立30周年記念祭(大正12年)
翌 大正12年は (熊本)分教会 創立30周年に当たることより、
(大正12年) 3月18日、
増田(甚七) 郡山大教会長はじめ 12名の役員を迎えて、
創立30周年記念祭に併せて、天理教青年会、婦人会の連合発会式が執行された。当時の部内教会数は 37を数えるに至っており、
遠く満州からも 数十名の参拝者があった。
広がる熊本の道(大正後期〜昭和初期)
(熊本分教会は)
引き続き 教祖40年祭(=大正15年執行) の活動も(活発に行い)、
順調なる教線の延びをみた。昭和に入って 教線の著しく急激な伸展をみるというところまではいかなかったが、
(それでも) 布教線は遠隔の地に延びて、
先に設立された 満州 (中国東北部) の長春 及び 哈爾賓の 2教会の他に、
長満・吉野区が 満州に設立された。また、
朝鮮には 咸興村・鏡清の 2教会を設け、
南洋に 爪哇島教会、
遠くブラジルに ブラジル教会を設けるなど、
教線は 思わぬ所に(まで) 伸展した。東京に貞信が設立されたのも、昭和10年であった。
熊本大教会への昇格(昭和15年)
昭和15年(1940) 7月25日、
熊本分教会は 郡山大教会より分離昇格し、
熊本大教会となった。
堤 常信2代会長の出直し、堤 信次3代会長の就任(昭和16年)
(堤 常信)2代会長は、翌 昭和16年5月7日、82歳で出直した。
(堤 常信)2代会長の後を継いで、
昭和16年7月25日、
堤 信次が3代会長に就任。
同(昭和)17年 3月19日、就任奉告祭(を)執行(した)。
堤 信次3代会長の軍隊召集、夫人の会長代務者就任(昭和18年〜終戦後)
しかし、(この頃は)
太平洋戦争に突入していた時代であったので、
(堤 信次3代)会長も、(昭和)18年より 海軍に召集された。(堤 信次3代会長が軍隊に召集されていた)この間、
3代会長夫人が 会長代務者としてつとめた。
神殿ふしん(昭和25年頃〜昭和27年)
昭和25年3月29日、 (堤 常信)2代会長10年祭が執り行われた。
その席上、
長年の懸案であった (熊本)大教会の神殿建築が打ち出された。(熊本大教会として) 早速 その準備にかかったが、
種々の事情のため、
早急に着手する事が出来なかった。しかし、(その後) 機が熟して、
昭和26年9月3日に (ふしんに) 着工。(神殿ふしんは、無事) 1年足らずで 完成。
昭和27年10月11日、2代真柱を迎えて 鎮座祭、
翌10月12日、賑やかに (神殿落成)奉告祭が 執行された。
教祖70年祭〜堤カズエ4代会長就任奉告祭(昭和31年〜昭和42年)
昭和31年には、
熊本大教会において、教祖70年祭が執行された。昭和42年11月21日付をもって、
堤カズエ会長就任が認められ、
同年(昭和42年) 12月6日、
(4代会長)就任奉告祭が執り行われた。(熊本大教会は)
現在、(一丸となって) 世界たすけのため 努力している。〔現住所〕〒861-0127 熊本県熊本市北区植木町亀甲2170
〔電話〕096-273-3221(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)
(『天理教事典』1977年版 P,303〜305)
おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。
72回目の今回は、
「熊本大教会」初期の歴史を勉強しました。
当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。
とても古い資料なので、
記載内容も 1970年代以前までとなっており、
かなり昔の歴史にとどまっています…
しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。
十分 私のニーズは満たされるので、
そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) という本の中にも熊本大教会に関する記述がありました。
熊本方面の道として、結構 詳しく書いてありました。
自己覚え書きとしてそのまま書写します。
【熊本】
明治十年二月、西南戦争で 熊本の街は ほとんど灰燼に帰した。
熊本と東肥創設の元一日は、その復興普請に起因する。熊本大教会は 堤 豊賀の信仰から始まる。
十八年、熊本市京町に住む雑貨商・友井常八は 肺患で重体となり、
大阪 天恵四番(泉田藤吉)の周旋で 熊本鎮台病院の石垣修理に来ていた 北田常吉のおたすけを受けた。豊賀の夫・高木一蔵は、軍人で熊本鎮台在勤中は 西南戦争征伐軍 会計官、
常八は その会計部の給仕として可愛がられた。そのため 一蔵の没後も 常八は 旧主の家をよく訪ねていた。
ある日、豊賀が猛烈な腹痛で苦悶しているのに出会い、神様にお願いし 御神水を与えると、夢からさめたように治った。
常八が言う人だすけに共鳴し、
二十一年、豊賀は 上林町に集談所を設けた。そこへ 藤吉に依頼した布教師・井村徳次郎が来て、道は 急速に発展した。
参拝者は 先陣争いをするすさまじさとなり、お願いするのに 番号札を出すほどだった。
このおたすけが 警察の目に止まった。
みだりに人を集め 医薬妨害をしたとの理由で、徳次郎は 二週間の拘留、常八は信仰差し止め。
豊賀は婦人の身であるため、咎めはなかった。これより 集談所は火の消えたようになり、
徳次郎は 教導職の必要を感じ 熊本を去った。
その時、奈良の黒田ツイを訪ねよ、と言い残した。豊賀は ツイを訪ね、天龍講講元・平野楢蔵を紹介された。
平野宅に一ヶ月ほど滞在、教理を仕込まれた。豊賀は「おたすけは心にあり、与えは天にあり」と、たすけっ放しで、
筍生活をしながら 島原、長崎へ道をつけた。厳格、男勝りながら 涙もろく、淡白。
自分は弁の人でないと、部内巡教に常信 (常八が豊賀の養子となり改名) を同行、
常信の一席の話の後、一口 締めくくりの仕込みをした。
人々は ピシリと辛い一口の仕込みを受けぬと、せっかくの千万言の話もありがたみが少ないと、
豊賀の巡教を期待したという。愛媛県出の山内次三郎は、熊本復興普請に来て 大工職の仕事に励むうち、
両眼とも膿漏症となった。
絶望していた時、案内されて二十一年、井村徳次郎の集談所へ行った。
その後、熊本を去った徳次郎の後を慕い、盲目の次三郎は船でおぢばへ向かった。帰郷後の次三郎のおたすけは鬼神をも泣かす厳しさに満ちていた。
『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,102
いんねんの自覚による徹底した通り方を実践し、心に浮かぶ教理を説いたが、それが的確に相手の心を衝いた。
この『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編)の記述は、『天理教事典』「熊本大教会」解説文の記述内容を補うような内容で、助かります。
『天理教事典』の記述だけでは、
熊本大教会発祥の元となった友井常八先生 肺病の おたすけをされた 北田常吉先生は、
何故 わざわざ 大阪から 遥か遠方の熊本へ行かれたのか はっきりしませんでしたが、
『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) を読むことで、その理由がわかりました。
瀕死の状態に陥った友井常八先生の肺病をおたすけされた北田常吉先生が大阪から熊本へ出張されたのは、西南戦争の 復興のふしんのためだったのですね。
そういえば、昔、日本史の授業で、
西南戦争において熊本鎮台の司令部は熊本城本丸に置かれて、
熊本城は 西郷軍の猛攻を受けた激戦地だった、
と教わったような 微かな記憶が… (^^;)
熊本は、西南戦争において灰燼と帰して、
その復興のための普請に 大阪からも 建築関係者が集まってきていたわけですね。
また、『天理教事典』の記述だけでは、
熊本大教会 初代会長の 堤 豊賀先生がお道の信仰に熱心になった理由が はっきりしませんでしたが、
それについても、
『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) を読むことで その理由がわかりました。
『天理教事典』には 堤 豊賀先生が体験されたことについての記述は 何もありませんでしたが、
『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) には、
堤 豊賀先生が 猛烈な腹痛で苦悶しているところに 友井常八先生が出会い、
神様にお願いし 御神水を与えたところ すっきりと苦しみから解放された、堤 豊賀先生はそういう実体験をしておられた、
と 書いてありました。
堤 豊賀先生は、
亡夫友人の息子という縁で 友井常八先生から 天理教の話を聞いていて 教理について ある程度理解していたところに、不思議なたすけを 自身の体で味わう、という 実体験が加わった。
それが、
その後の 熱い信仰実践に繋がっていった、
と いうことだったのですね。
最初『天理教事典』の解説文を読んだだけだと、
堤 豊賀先生が「貧に落ち切る」教祖のひながたを 文字通り実践されるほどの深い信仰実践に至られた経緯が よくわからなかったのですが、
『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) を読むことで、腑に落ちたのでした。
その他にも、
堤 豊賀先生は、厳格で男勝りながら涙もろく淡白で、自分は弁の人でないと 部内巡教には常信 (=友井常八先生) を同行し、常信の一席の話の後、ピシリと辛い一口の仕込みをした、
という『道〜天理教伝道史をあるく』の記述も、
熊本大教会の礎を築かれた 堤 豊賀 初代会長の人間味が深く感じられて、興味深かったです。
表面的な事歴をなぞるだけでなく、
こうした 人間的な部分の話を教えて頂くと、
目に映る景色は同じでも、そこに他人事ではない親近感のようなものが湧いてきますよね。
こういう話をどんどん知りたいです。

また、今回、熊本大教会について勉強する中で、
熊本大教会 初期歴史の中に「泉田藤吉」先生が登場されることに驚きました。
当シリーズ前々回の第70回で『天理教事典』「中津大教会」解説文の書き写しをしたわけですが、
その際「泉田藤吉」先生について 勉強したばかりだったからです。
『天理教事典』「中津大教会」解説文には、次のように書いてありました。
「泉田(藤吉) は、かつて (その数年前の) 明治19年(1886)に、九州への布教を思い立ったことがあった。
(『天理教事典』1977年版 「中津大教会」より)
しかし、この時 おさしづを伺ったところ「見合わせよ」とのお言葉があったため、(その時は) 断念した。
(そして、代わりに) 石工の北田某を熊本方面に送って 布教をさせた。」
ここに書かれてある 北田某というのは 北田常吉先生のことで、
泉田藤吉先生が 北田常吉先生を熊本方面に送って布教をさせたことにより、
「熊本大教会」の種が蒔かれた、
ということだったのですね。
今回、熊本大教会について勉強して、その部分がつながりました!
中津大教会と熊本大教会は、
カリスマ布教師「泉田藤吉」先生を通じて、その根っこの部分でつながりがあると言えなくもない、
ということですね。
この世の中は 目に見えない部分でいろいろ繋がっている、
ということの 典型的な一つの事例と言えそうです。

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】72回目の当記事では
『天理教事典』の中の「熊本大教会」についての記述を書き写したわけですが、
その他にも、知らないことばかりでした。
熊本大教会は、郡山大教会から分かれた大教会で、天龍講の流れ汲む大教会ですが、
天龍講の系統に入るに至ったのは、
泉田藤吉先生から委嘱されて熊本へ赴いた 井村徳次郎先生が 熊本を去る際、
天龍講に所属する黒田ツイ先生を頼るように言い残したところからである…
という話など、大変興味深かったです。
いつものように、今回もまた、
これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て とても勉強になりました。
有難いことでした。
「人に歴史あり」
組織にも歴史あり…
歴史を踏んで今がある――
だからこそ、
今を輝かせるためには
「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。
ということで――
今回は「熊本大教会」初期の歴史の勉強でした。
人生、死ぬまで勉強。
今後も、勉強し続けていきたいと思います。
ではでは、今回はこのへんで。
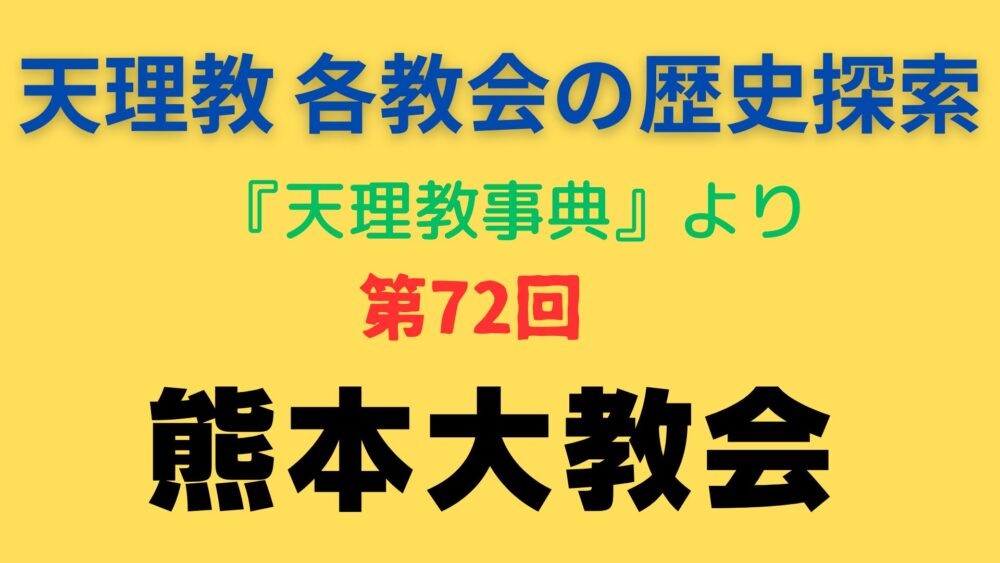

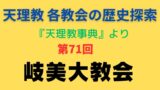
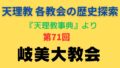
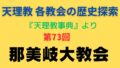
コメント
熊本大教会部内富鶴分教会(お返ししました)の者です。
熊本大教会史をネットにアップして頂き、誠にありがとうございます。
コメントありがとうございます。
このような自己満足ブログに目に留め読んで下さり、またコメントまで届けて下さって、本当に有難うございます。