Dear everyone,
こちらは、
ふらふら彷徨う「さまよい人」による
『さまよいブログ』
= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。
今回も、
『天理教事典』(1977年版)に記載された
各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。
私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)
最新版👇
このシリーズを始めた理由については、
当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。
前回は、
教会番号65番「南阿大教会」の『天理教事典』記述を書写して
その歴史を勉強しました。
今回は、
教会番号66番「香川大教会」について勉強します。
- 香川大教会(かがわ だいきょうかい)
- 北嶋友五郎 初代会長の生い立ち(元治元年~明治16年頃)
- 北嶋友五郎の失明、奇蹟のおたすけ(明治16年~明治17年)
- 北嶋友五郎の布教~おぢばがえり(明治17年~明治20年)
- 讃岐の道明け(明治19年~明治21年頃)
- 北嶋友五郎、信仰の深まり(明治21年〜明治22年)
- 引田集談所の設置(明治24年)
- 神殿ふしん(明治24年〜明治25年)
- 薄木事件(明治26年)
- 香川支教会の開設(明治27年)
- 香川の道の広がり(明治18年頃〜大正5年頃)
- 香川分教会への昇格(明治42年)
- 北嶋友五郎初代会長の辞任、北嶋栄吉2代会長の就任(大正9年)
- 会長宅等、教会建物のふしん(昭和5年〜昭和10年)
- 香川大教会への昇格(昭和15年)
- 北嶋栄吉2代会長の辞任、北嶋 巌3代会長の就任(昭和18年)
- 北嶋 巌3代会長就任後の動き(昭和19年〜昭和41年頃)
- 北嶋 巌3代会長の辞任、北嶋友衛4代会長の就任(昭和46年)
- おわりに
香川大教会(かがわ だいきょうかい)

北嶋友五郎 初代会長の生い立ち(元治元年~明治16年頃)
北嶋友五郎は、
元治元年(1864) 3月28日
阿波国 板野郡 北灘村大字大須 (現・徳島県鳴門市北灘町大字大須) 15番屋敷にて、
春次・ユキの長男として生まれた。
(北嶋)友五郎は、幼名を 友之進といった。2歳の時、父(春次) に死別、
叔父・計三郎を養父として育った。温厚な (父) 春次と異なり、
豪放磊落な (叔父) 計三郎は、
(北嶋)友之進に 剣術、砲術、槍術等、荒々しい武術を教えて 厳しく躾けた。8歳の時、(友之進から) 友五郎と改名。
本家(の) 北嶋藤三郎について 学間を始めた。
向学心の強い(北嶋)友五郎は 熱心に習得し、
18歳まで 先生について勉強した。19歳の時 戸主となり 家業を継いだが、
勉学は その後も怠らなかった。
北嶋友五郎の失明、奇蹟のおたすけ(明治16年~明治17年)
明治16年(1883) 陰曆正月4日の黄昏頃、
西の山に火煙の登るのを見た(北嶋)友五郎は、
種ヶ島鉄砲を携え、友人と共に山へ急行した。かねてより
阿讃(阿波と讃岐) 両国を結ぶ大坂峠に 盗賊が出没し、旅人が難儀している、
という噂を耳にしていた (北嶋)友五郎は、
盗賊を捕えて 人々の不安を除きたい と思ったのである。水谷まで行くと盗賊が気付いて、木の繁みに隠れた。
狙いを定めて引金を引いたが 発射しない。
再度 引金を引いたが 発射しないので 不審に思い、火縄に息を吹きかけた途端、火薬が爆発し、その場に昏倒した。その後、顔面の傷は治ったが、眼は 両眼共 失明した。
そこで、名医を尋ねて 出来得る限りの治療を行い、
世に聞こえた神社仏閣にも詣り 祈願を込めたが、はかばかしくなかった。明治17年(1884) 陰暦12月13日、
徳島の病院に入院していた(北嶋)友五郎は、
洗眼に来た二人連れの老婆から、初めて (天理教の) 神様の話を聞いた。
それは、今まで聞いこともない神名であった。そこへたまたま見舞いに来た 弟・重太郎も、
奇蹟的な御守護を頂いた近所の人の話を伝えた。(北嶋)友五郎は 心 大いに動き、
早速 退院(し)、両親に許しを乞うて
(明治17年) 陰暦12月15日、
弟・重太郎に手を引かれ、大阪峠を越えて
加賀須野 (現・徳島市川内町) の 講元・斉藤利太郎宅へ向かった。斉藤(利太郎) 宅は、当夜、講社祭で 5〜60名の参拝者で賑わっていた。
(加賀須野の講社で 斉藤利太郎より) 色々と(この道の)話を聞いた (北嶋)友五郎は(その教理に強い感銘を受け)、
今までのことを (深く) さんげした(のであった)。(そして その講において、友五郎のための真剣なお願いづとめが行われた結果) 三日三夜のお願いで
(見えなかった北嶋友五郎の)眼が見えるようになる という奇蹟的なご守護を頂いた。すっかり御守護頂いた(北嶋)友五郎は、
(明治17年) 陰暦12月22日、
喜び勇んで我が家に帰り、両親に報告した(のだった)。
北嶋友五郎の布教~おぢばがえり(明治17年~明治20年)
その後、欠かさず 月参りしていた(北嶋)友五郎は、
阿波真心組 講長・土佐卯之助から、人救けこそ 最上の御礼であると(のお話を)聞き (深く感じるところがあった。そのお言葉を重く受けとめた北嶋友五郎は、
そこから) 村内の病人を訪ね歩き、おたすけ活動に励んだ。
(その結果) 井上佐市、浜田為市、山口梅造、坂東郁郎…等が入信した。(不思議な神のはたらきを目の当たりにした感激に包まれて)
(北嶋)友五郎は、
明治20年(1887) 陰曆正月、初めて おぢばがえりした。
讃岐の道明け(明治19年~明治21年頃)
これより先、明治19年(1886)の春、
讃岐国 大内郡 小海村 (現・香川県大川郡引田町小海) 農業・三谷クラは、
次男・彦四郎の 小児喘息の治療のため 阿波国 板野郡北灘村粟田へ急ぐ道中、
(たまたま) 月参りから帰る (北嶋)友五郎と出会った。(三谷クラは 北嶋友五郎から、奇蹟的なご守護を頂いた話を聞いた。
そして 三谷クラは、北嶋友五郎に) 勧められるまま
(阿波国 板野郡の) 大須へ引き返し、お籠りをした。(その結果、三谷クラの次男・彦四郎は
身上ご守護を頂いたのであった。三谷クラは、息子の三谷)彦四郎が (不思議な) たすけに浴したことから入信。
(その後) 三谷家は (讃岐国) 小海村の講元になった。こうして 教えが 讃岐へ伝えられた。
(讃岐国の足がかりが出来た 北嶋)友五郎は、
明治21年、讃岐布教を開始した。
北嶋友五郎、信仰の深まり(明治21年〜明治22年)
明治21年11月29日、天理教会本部の開筵式が行われ、
(北嶋)友五郎も 団参に加って おぢばへ帰り、おさづけの理を拝戴した。明治22年(1889) 4月28日、
(北嶋)友五郎は、
(徳島県) 板野郡 松島村 大字七条村、吉田清七の次女・トヨ子と結婚した。同年(明治22年) 7月9日、
(北嶋友五郎は) 教導職試補となり、8月13日 改式した。
引田集談所の設置(明治24年)
明治22年から翌23年にかけて、教線は 燎原の火の如く広まり、
瞬く間に (香川県) 大内、寒川 二郡 (現・大川郡) 全域に及んだ。そこで、
明治24年1月15日、
(香川県) 引田村・木村順平宅において集会を行った。
(そして)
翌(1月)16日、講元・周旋等 35〜6名が集まって大会議を開き、
(香川県) 引田村 字南後田 547番戸に 集談所を設置することになった。(明治24年) 陰曆正月、
集談所設置の許しを受け、
同年(明治24年) 5月5日 鎮座祭、翌6日 開筵式を執行した。鎮座祭の当夜、
東の空から火の玉が飛来し、御鎮座が終わった頃、
集談所屋上で消え(るという怪奇現象が見られ)た。
もの珍しそうに蝟集していた村人達は (大層)驚き、先を争って逃げ帰った(のだった)。
神殿ふしん(明治24年〜明治25年)
集談所は、3間に5間の藁葺で、
周旋人・薄木民蔵が提供したもの(だったの)であるが、
(参拝者は日に日に膨れ上がり) 忽ち 狹隘となった。(そのため、開設からおよそ半年後の)
同年(明治24年) 10月15日(には)
相談の上、神殿建築に取り掛か(ることとな)った。秋の穫り入れが終わるや否や、
人々は 用材の伐り出しに精を出し、
山野に置く霜も物かわ、営々として ひのきしんに勇んだ。翌(明治)25年(1892) 3月、(無事) 神殿が竣工。
同月(3月)14日 鎮座祭、15日 開筵式を行った。この前後、教線は (香川県) 大内、寒川郡から更に西へ伸び、
(香川県) 高松、坂出、宇多津、丸亀へと伝わり、
講社 500戸を算するに到った。
薄木事件(明治26年)
一見 順調に見える道すがらにも 幾度か苦難が襲いかかったが、
明治26年(1893) に起こった「薄木事件」は、その最たるものであった。薄木民蔵は、屋号を『大谷屋』といい、米穀雑貨等を商っていた。
(薄木民蔵は) 引田村(の) 周旋人として 熱心につとめ、
米麦を始め、ローソク・油・つけ木等をお供えしていた。(熱心に信仰していたのであるが)
(ある時) ふとした行き違いから (天理教から)離反する事態に至ってしまった。(天理教から離れた薄木民蔵は、単に離脱するだけでなく) それまで用立てていた全ての物品を計算し、支払いを請求した(のである)。
(信頼していた薄木民蔵の離脱と攻撃により) 北嶋友五郎が受けたショックは計り知れないものであった。
(なんと北嶋友五郎は) その心痛のあまり失明(してしまった。そして、北嶋友五郎は) 仕方なく (集談所から) 実家に帰った(のだった)。(北嶋友五郎の去った) 集談所は 参る人も居なくなり、
心ない村人達は、
「あれ(集談所) は 薄木(民蔵)の蚕部屋になるそうな。天理さんも これでお仕舞いぢゃ」
等と噂し、信者達の中には 動揺して離れる者も出てきた。(事態を重く見た) 撫養分教会の 麻植房次郎・玉垣多伝次が
この おたすけと 事情の解決に出張してきた。丁度この日、北嶋家は サノボリ (田植えの終わる日) で 御馳走を作っていた。
(友五郎の養父・北嶋)計三郎は、機嫌よく二人を迎え入れ、酒飯を出して接待した。(会食は和やかな雰囲気で進んでいたが)
(麻植房次郎・玉垣多伝次の) 二人が、
「(北嶋友五郎の) 眼の御守護を頂くため (北嶋)友五郎を 神様のよふぼくとして差し出して欲しい」
と切り出した途端、(北嶋計三郎は) 急に不機嫌になった。「道一条」に出せ、 さもなくば盲目は治らぬ、と一方が言えば、
友五郎は 北嶋家の長男故、盲目が治らなくて (たとえ)生涯飼殺しにしても 出さぬ、
と片方が反発。
楽しいサノボリの夜が、価値観の異なる立場の者が 激しくぶつかり合う修羅場と化した。(両者一歩も譲らず) 雨嵐が吹き荒れるかの如き 激しい衝突がしばらくの間 続いたが、
(やがて、麻植房次郎・玉垣多伝次) 二人の決死の真実が、頑なな(北嶋)計三郎の心を動かした。(麻植房次郎・玉垣多伝次 両名は) 友五郎を神様の よふぼくとして差し出してもらう代わり、
万一、(北嶋友五郎の)眼が治らなかった場合には (麻植房次郎・玉垣多伝次) 二人の首を差し出す、
と約束したのである。(麻植房次郎・玉垣多伝次 両名から そこまでの命懸けの決意を聞かされては、さすがの北嶋)計三郎も納得せざるをえず、(その場は) 治まった(のであった)。
(麻植房次郎・玉垣多伝次) 二人は (失明した北嶋)友五郎の手を引いて 讃岐の講社を回り、
苦労して (薄木民蔵への) 支払いの解決に当たった。(そして) 約束の90日目の朝。
奇蹟は起こった。
(北嶋友五郎は) 御守護を頂き、(失明した)眼は (見事に)晴眼に復した(のであった)。養父(北嶋計三郎) は
「天理さんの神様は 性の悪い神様ぢゃ」
と嘆じつつも、
財産を分かって (北嶋)友五郎に与え (友五郎を 神のよふぼくとして差し出したのだっ)た。(北嶋家の) 家督を弟に譲った(北嶋)友五郎は、
晴れて 道一条につとめられるようになった。この (薄木)事件の後、
三谷彦次郎が 青年第1号として (集談所に)入り込んだのを初めとして、
小豆島から 川井利三郎が (集談所に)入り、
続いて、桑島栄吉、三木辰太郎、荒井雪蔵、池本治平、浜田弥三郎…
等 多くの青年が集まっ(てきて、参拝者が途絶えてしまっていた集談所に再び人が集まり始めたのだっ)た。
香川支教会の開設(明治27年)
薄木事件を契機として、一段と集談所の基礎が固まり、教勢が伸展。
いよいよ 教会設置の機運が高まった。かくて、明治27年1月29日、
香川県 大内郡引田村550番戸 (現・香川県大川郡引田町引田) にて、
「香川支教会」設置の許しを受けた。同年(明治27年) 3月6日 地方庁の認可を得たので、
5月9日(陰暦4月4日) 鎮座祭を、 翌(5月)10日 開筵式を執行した。
香川の道の広がり(明治18年頃〜大正5年頃)
山間部
(香川支教会の道は、引田村だけでなく)
四国三郎の異名を持つ吉野川を上流へ遡った山間の村にも、
市橋新太郎、大島藤助 等の手によって 逸早く伝道された。(香川支教会が設置される以前の)
明治18年に (徳島県)阿波郡大俣村日開谷の方から 讃岐国大内郡五名山村へ入ってきた 市橋新太郎から 同村(五名山村) 四宮茂平に伝えられた教えが、
明治18年頃から22年頃までの間に、次第に 讃岐の平野部へ広がっていった。(香川県) 丹生村の 滝井唯次、鶴羽村の 木村イノ、富田村の 六車竹次郎、
等(の人々)が入信した。
相次ぐ 部内布教所の開設
(また、香川県) 引田の道も 急速に広まり、一つにまとまっていった。
大内、寒川、讃陽、琴林…等の 布教所の始まりである。
高松布教所
高松は、
明治25年(1892) 10月、
香川支教会長の命を受けた 木村亀吉が、
同市(高松市) 大工町に 集談所を置いて布教したのが始めで、
撫養系・酒巻折造の 精心組の残された信者と合併発展した。明治27年、高松布教所が置かれた。
西讃出張所
坂出・宇多津・丸亀の道の始まりは、
明治24年4月、
丸亀歩兵 第12連隊入隊中の 北嶋重太郎より連絡を受けた 兄・友五郎が 自ら同地に赴き布教を行ったもので、
同じ頃、中島亀太郎も 宇多津へ伝道した。(後の) 明治28年(に) 西讃出張所が設置された。
若宮出張所・博多布教所
明治24年頃、
徳島県 板野郡大寺村(の) 香美冨吉は、
(福岡県) 筑前の炭坑に出稼ぎに赴き、ひまを見ては 布教していた。講社が増えたので、
(福岡県) 鞍手郡 若宮村 大字福丸の 講元・村上伊三郎宅を足場として布教に専念。
安部ヤス、安部茂三郎、同・孫右衛門、神保正右衛門、大峰仁三郎、等が入信した。神保正右衛門の義弟・六三郎は、
博多屈指の資産家・釜六こと、山本六平宅の番頭となり、後 養嗣子となった。安部ヤスは、しばしば博多へ赴き、教理を仕込んだ。
安部孫右衛門も、本格的に博多布教を始めた。明治28年、(北嶋友五郎) 香川支教会長は、
(上級) 撫養分教会の指示を仰ぎ、筑前講社をまとめ、
香美冨吉を担任(所長)として、
同年(明治28年) 12月、若宮出張所を設置した。(また)
明治35年、安部孫右衛門は、博多布教所を設立した。
杵築布教所
豊後布教は、
中島亀太郎の単独布教によって始められた。(中島)亀太郎は、明治28年3月4日、
(大分県に出ていた 香川県)引田村 安戸出身の 中川茂太郎を頼って、
大分県 東国東郡大内村へ出発した。これが、杵築の道である。
讃豊布教所
明治28年、(香川)県内の処女地開拓を議し、
六車梅太郎、三木和平が、
(香川県) 三野、豊田 二郡 (現・三豊郡) 布教に出発した。六車梅太郎は、(香川県) 三野郡元山村に足を止め 布教する内、
同年(明治28年)末(に) 松浦広助が入信。後(に)、讃豊布教所を開いた。
韓国
明治35年、(北嶋友五郎) 香川支教会長は、
山口県長府村出身の 中村順平を
膝下で薫陶した後、韓国布教に派遣した。(中村)順平は、一旦 長府に帰り、若宮出張所に参拝した後、
同年(明治35年) 4月、対島を経て 釜山府に渡り、熱烈な布教を開始した。講社も多数結成されたが、退韓命令を受けて、
明治37年3月29日、(泣く泣く) 若宮へ引き揚げた。
その後、山本六三郎・大峰仁三郎 等が派遣され、釜山布教所が設置された。これは、香川で初めての 海外の教会である。
東京
韓国布教の行われた年(明治35年) 、
森 伊勢造は、(北嶋友五郎) 香川支教会長に(自ら)提議し、東京布教に赴いた。(森) 伊勢造の弟・横山定助が、6年前 東京府南足立郡に移住していたので、
(森 伊勢造は) 同家へ留まり 布教した。
次いで、六車鉄太郎、福田覚 等が派遣され、40戸程の講社が出来た。(北嶋友五郎) 香川支教会長も、明治41年と43年に 東京布教に赴いた。
台湾
大正4年3月、松浦広助は、
藤田今治・丸岡吉太郎・保喜郁文を連れて、台湾布教に出発した。
後日、三好亀次も 渡台した。一行は、花蓮港へ上陸し 布教に励んだが、
気候風土から言語まで異なる土地での布数は、想像に絶する困難があった。同年(大正4年)10月16日、藤田今治がマラリヤで出直。
翌月(11月)、保喜郁文が 後を追った。それでも布教に励んでいたが、
翌(大正)5年4月、引揚げて帰国した。
香川分教会への昇格(明治42年)
明治42年(1909) 1月8日、
香川支教会は、分教会に昇格した。
北嶋友五郎初代会長の辞任、北嶋栄吉2代会長の就任(大正9年)
大正9年(1920) 1月16日、
(北嶋友五郎) 香川分教会長は、部内巡教中(に) 病を得て、
同年(大正9年)10月24日 辞任。北嶋栄吉が (2代会長に)就任した。
会長宅等、教会建物のふしん(昭和5年〜昭和10年)
昭和5年9月5日、会長居宅 及び 炊事場を改築。
昭和10年2月4日、客間改築の許しを受けた。
香川大教会への昇格(昭和15年)
昭和15年(1940) 3月30日、
香川分教会は 大教会に昇格。
撫養大教会から分離した。昇格奉告祭は、同年(昭和15年) 12月11日、執行された。
北嶋栄吉2代会長の辞任、北嶋 巌3代会長の就任(昭和18年)
昭和18年5月27日、(北嶋栄吉)2代会長が辞任。
北嶋 巌が (3代会長に)就任した。
北嶋 巌3代会長就任後の動き(昭和19年〜昭和41年頃)
北嶋 巌(3代会長)は、
昭和19年1月11日 徵用令により 神戸三菱造船所へ勤務することになったので、
同年(昭和19年) 7月3日、北嶋栄吉が代務者に就任した。昭和20年8月22日、北嶋 巌が復員帰宅したので、
同年(昭和20年)10月19日、代務者が解任された。昭和23年5月26日、信者詰所 第71寮 (現・香川大教会信者詰所) 開設の許しを受け、
6月25日 荒井貞吉が 寮長に任命された。昭和26年(1951) 1月21日、創立60周年記念事業として 神殿建築を提議。
同年(昭和26年) 10月28日、許しを受けて 着工した。翌(昭和)27年7月28日、付属建物移動 並びに 増築の許しを受けた。
工事は順調に進捗し、昭和29年3月、完工した。
同月(3月)20日 鎮座祭、21日 奉告祭が盛大に執行された。昭和41年10月25日、(部内の)高松分教会が 大教会に陞級、分離した。
北嶋 巌3代会長の辞任、北嶋友衛4代会長の就任(昭和46年)
昭和46年9月26日、(北嶋 巌)3代会長が辞任。
北嶋友衛が (4代会長に)就任した。機関誌『香川』は、昭和28年11月創刊され、
以後 月刊配布されている。〔現住所〕〒769-29 香川県大川郡引田町引田2276番地
〔電話〕 0878-33-2075(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)
(『天理教事典』1977年版 P,183〜185)
おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。
66回目の今回は、
「香川大教会」初期の歴史を勉強しました。
当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。
とても古い資料なので、
記載内容も 1970年代以前までとなっており、
かなり昔の歴史にとどまっています…
しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。
十分 私のニーズは満たされるので、
そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) という本の中にも 香川大教会に関する記述がありましたので、
自己覚え書きとして書写します。
北嶋友五郎 (香川初代) の生家は、
徳島県 板野郡北灘村大須の山裾にある。明治十六年、二十歳の友五郎は、山賊退治をして旅人の苦難を救いたいと、
友人を誘って火縄銃を手に山へ登った。
夕闇の木立の茂みに 賊の姿が隠れたのを見て、引金を引いた。
が、発火せず、火縄の火が消えたのかと ふっと吹いた瞬間、火薬が爆発。
両眼失明、目鼻が判別できぬほどの重傷を負った。通りがかりの老婆から聞いた徳島県加賀須野村の斎藤利太郎宅を訪ねた。
当日、講社づとめで賑わっていた。
友五郎のためのお願いづとめが行われた。三座のつとめに奉仕者は わが身わが家に代えてもと、
寒中にもかかわらず 汗を絞るほど真剣に勤めた。
その熱気に 友五郎は感動、晴眼と変わらぬ御守護を頂いた。帰郷後、大須の井上佐市が 二年も黄疸を患っていたのを 加賀須野へ連れて行ったところ、五日目に治った。
さらに 友五郎は、香川県小海村の三谷豊吉の弟の小児喘息をたすけるなど、道は 徳島から香川に入ってきた。
引田村の大工棟梁 山本梅六は 小海村で話を聞き、左官の八田弁吉を手引きした。市橋新太郎は、四国全県股にかけた怪盗だったが、土佐卯之助 (撫養初代) の導きで生まれかわり、己が犯した罪の償いに 人の行かぬ山間僻地へ布教に出た。
軽妙で理に徹した話は 多くの人に感銘を与えた。
しかし、常軌を逸する行動があり、信者たちは、引田集談所に合流した。後に、香川大教会設置へと進む。
(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,86)
香川大教会は、撫養大教会から分かれた大教会ですね。
撫養大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。
当シリーズ 前々回(第64回)が「周東大教会」、
前回(第65回)が「南阿大教会」、
そして 今回(第66回)は「香川大教会」。
前回(第65回)「南阿大教会」の「おわりに」の所でも書きましたが、
「香川大教会」は
【教会番号64〜66】 → (64番)周東 ー(65番)南阿 ー(66番)香川、
という「撫養大教会」から分離した「教会番号連続3兄弟」グループ 3番目の大教会ですね (^^)

当記事では『天理教事典』の中の「香川大教会」についての記述を書き写したわけですが、
今回もまた 知らないことばかりでした。
今回の『天理教事典』解説文読了後、まず最初に強く感じたのは、
それにしても、香川大教会 初代会長の 北嶋友五郎先生の入信に至る経緯が 何とも激しい、
ということでした (°д°;)
なんと、
北嶋友五郎先生の 入信の元となる 眼の身上は、
旅人を悩ませていた盗賊を捕まえてやろう
と 火縄銃を持って 峠に出掛けたところから生まれたものだったのですね。
まずもって、
個人で「盗賊を捕まえる」という発想そのものが 尋常ではありません。
よほどの正義感に満ち溢れた方だったのでありましょう。
そもそも、北嶋友三郎先生は、
盗賊退治にあたって何名か複数で向かったのでしょうか。それとも単独で?
火縄銃で盗賊を撃ち殺すつもりだったのでしょうか?
時代背景の違いもあるのでしょうが、
あれこれ想像すると、改めて恐ろしい… (>_<)
で、その際、
盗賊を見つけ、狙いを定めて火縄銃の引き金を引いた…
ところが、弾が出ない。
おかしいなぁ…
と、改めて火縄に息を吹きかけてみると、
なんと 銃が暴発!
北嶋友三郎先生は 失明してしまわれた!!
香川大教会の礎を築いた 北嶋友三郎先生の入信のきっかけとなったのは
「失明」の 奇蹟的なご守護。
で、その「失明」というのは、
盗賊を退治しようとした際の 銃の暴発によるものだったとは… (°д°;)
以上の事実は、
今まで知らなかったこともあって、私にとって 衝撃的なエピソードでした。
何とも「激しい」 (ll゚Д゚)

北嶋友三郎先生にまつわる史実の「激しさ」は
それにとどまりません。
銃の暴発によって失明した 北嶋友三郎先生の眼は、
明治17年、斉藤利太郎先生宅の講社での 皆様の真剣なお願いづとめによって、
奇蹟的なご守護を頂き、光を取り戻した。
しかし、入信から6年後の「薄木事件」のショックで、
なんと 再び失明してしまった‼︎
ちなみに「薄木事件」というネーミングは
『天理教事典』本文に記述されたままのものです。
私がつけた名前ではありません。
おどろおどろしい名前ですが、
その中身は、現代でも 多くのところで類似の事情が起きていそうな、
いわゆる 人間関係のトラブルですね。
…それはともかく、
「薄木事件」のショックで 再び失明してしまわれた 北嶋友三郎先生は、
讃岐・引田の集談所を去って、阿波の実家に戻ってしまった。
いわゆる 引田の集談所が、
今でいうところの 事情教会みたいになってしまったわけですが、
そうした事態を受けて、
上級・撫養分教会から 麻植房次郎・玉垣多伝次 両先生が 派遣されてきた。
そして、北嶋友三郎先生の今後を巡って、
麻植房次郎・玉垣多伝次 両先生と、養父・北嶋計三郎先生が 激突。
道一条に進ませたい麻植房次郎・玉垣多伝次 両先生。
お道とは距離を置いて、あくまで 北嶋家の長男として 家督を相続させたい 北嶋計三郎先生。
両者 一歩も引かない 膠着状態を打ち破ったのは、
「もし(北嶋友五郎先生の)眼が治らなかったら、首を差し出す」
という 麻植房次郎・玉垣多伝次 両先生の、文字通り「命懸け」の提案だった‼︎
これまた、何とも「激しい」 (ll゚Д゚)
この部分まで読んだ時、
私は、またもや 強い衝撃を受けました。
その時の私は、
マジか⁉︎ もし 治らなかったらどうするつもりだ!
と、正直 思ってしまいました。
後世に生きる私たちは、
北嶋友三郎先生の眼は 奇蹟的なご守護を頂いて 再び光を取り戻した、
と知っています。
だから、
「麻植房次郎・玉垣多伝次 両先生はすごい、さすがだ…」
等と 無邪気に その偉業を讃えられます。
しかし、その当時 リアルタイムで その場面に関係していた人々にとっては、
一寸先は闇。
先のことは 何もわからないのです。
それにも関わらず、
麻植房次郎・玉垣多伝次 両先生は、
首をかけて、すなわち命をかけて、
北嶋友三郎先生の 道一条を訴えられた。
これは、
現代の価値観に生きる私たちの 理解を超えた部分のように 私には思えます。
首を差し出せるということ、
それは、
麻植房次郎・玉垣多伝次 両先生の中には、
心の底から「ご守護は頂ける」という確信があったということ。
麻植房次郎・玉垣多伝次 両先生は、
それほどまでの強い信念を、それまでの信仰生活の中でつかんでおられた、
ということを意味している と言ってよいでありましょう。
いまだに、天理教の信仰に強い信念を持つことができずに、フラフラ彷徨い続けている私などは、
首を差し出せるほどの確信を持てる心境に到達された 麻植房次郎・玉垣多伝次 両先生に、
ただただ 強い憧れを抱くのであります。
どうしたら、そのような心境に近付くことが出来るのでしょうか…
今回、香川大教会の初期歴史の書き写しを終えた今、
命をかけられるほどの強い信念をつかむことの出来る歩みを模索していけるといいなぁ…
そんな考えに 包まれるのでありました。

その他にも、これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても勉強になりました。
有難いことでした。
「人に歴史あり」
組織にも歴史あり…
歴史を踏んで今がある――
だからこそ、
今を輝かせるためには
「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。
ということで――
今回は「香川大教会」初期の歴史の勉強でした。
人生、死ぬまで勉強。
今後も、勉強し続けていきたいと思います。
ではでは、今回はこのへんで。
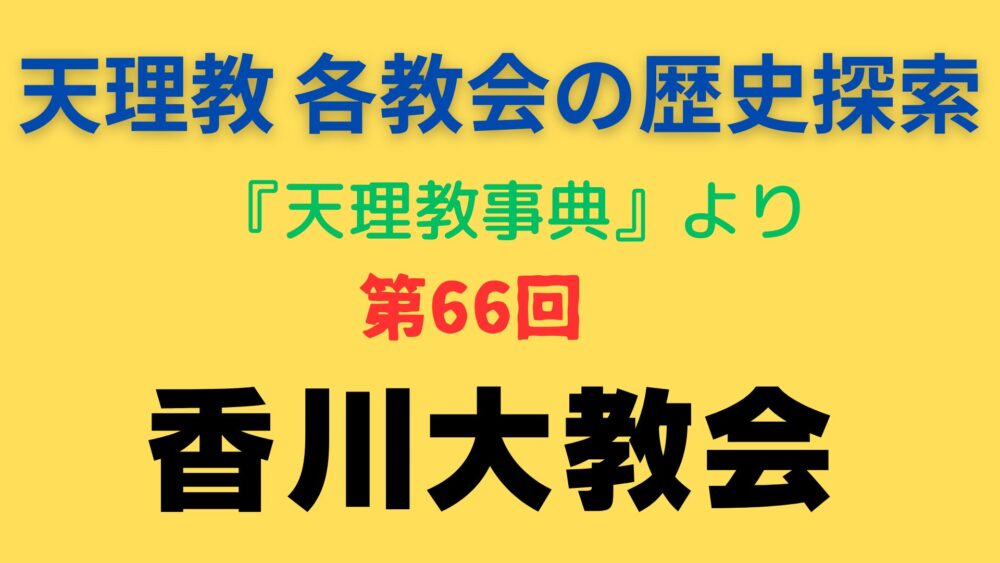

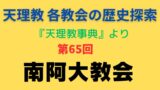
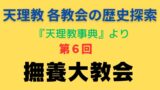
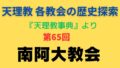
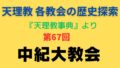
コメント