Dear everyone,
こちらは、
ふらふら彷徨う「さまよい人」による
『さまよいブログ』
= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。
今回も、
『天理教事典』(1977年版)に記載された
各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。
私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)
最新版👇
このシリーズを始めた理由については、
当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。
前回は、
教会番号48番「大江大教会」の『天理教事典』記述を書写して
その歴史を勉強しました。
今回は、
教会番号49番「旭日大教会」について勉強します。
- 旭日大教会(あさひ だいきょうかい)
- 岡本善六初代会長の誕生(嘉永2年)
- 初代会長の父・岡本重次郎の信仰(文久4年頃〜明治11年)
- 父出直し後の岡本善六初代会長(明治11年〜明治14年頃)
- 岡本志那子 初代会長夫人の乳呑児おたすけ(明治14年)
- 岡本善六初代会長の回心(明治15年)
- 日元講の発足(明治19年)
- 岡本善六講長の就任〜旭日支教会の設立(明治23年〜明治28年)
- 多大の負債に伴う停滞〜岡本善六初代会長の辞職(明治37年頃〜明治39年)
- 山沢為造2代会長の就任〜神殿建築・分教会への昇格(明治39年〜明治43年)
- 桝井安松3代会長の就任前後(大正4年〜大正15年頃)
- 中教会への昇格(大正15年頃〜昭和3年)
- 岡本栄太郎4代会長の就任(昭和4年)
- 旭日中教会の発展(昭和4年頃〜昭和11年頃)
- 中教会から旭日大教会への昇格(昭和13年頃〜昭和15年)
- 岡本重善5代会長就任〜岡本栄太郎4代会長出直し(昭和16年〜昭和20年)
- 神殿ふしん(昭和25年〜昭和35年)
- 教祖80年祭と創立71周年記念祭(昭和41年)
- 岡本善孝6代会長就任〜創立80周年記念祭(昭和46年〜昭和50年)
- おわりに
旭日大教会(あさひ だいきょうかい)

岡本善六初代会長の誕生(嘉永2年)
「旭日大教会」初代会長・岡本善六は、
嘉永2年(1849) 11月24日、
岡本重次郎の長男として 山辺郡永原村に誕生(した)。
初代会長の父・岡本重次郎の信仰(文久4年頃〜明治11年)
父・(岡本)重次郎の信仰は、
(文久4年) 親戚である 山中忠七の妻・そのが 不思議な守護を得たのを目の当りに見、
あるいは 教理を聞き、
更に、山中忠七に誘われてお屋敷に運び 教祖の温容に接してからの事である。その後、(岡本重次郎は)
仕事の閑を見ては庄屋敷に参拝して 教祖より色々の教理を聞き、
また、昔懐しいままに語られる三昧田付近の事などの話し相手をしている間に、
自然の薫陶を受けて、信仰の心も磨かれ、
報恩の道に精を出した(のであった)。(岡本重次郎は)
慶応元年10月の針ヶ別所事件の際 (針ヶ別所村に赴くに当たって)も、
他の高弟と共に(教祖の)お伴をした。慶応2年、教祖より黒骨の扇を授けられ、
慶応3年、正月からの「てをどり」の振付けがされた時には、
(てをどりの) 最初の6人衆の一人として加えられた。しかし、(岡本)重次郎は 明治10年頃から身上となり、
約1ヵ年の患いで
明治11年(1878) 6月19日、60歳を以って出直した。
父出直し後の岡本善六初代会長(明治11年〜明治14年頃)
長男である岡本善六は、
父・重次郎の没後は 細々ながら信仰の道を引継ぎ、
明治14年の甘露台の石曳きひのきしんを始め、
お屋敷には常に出入りして
屋敷の御用には 寸暇を惜しんで務めた。
岡本志那子 初代会長夫人の乳呑児おたすけ(明治14年)
明治14年8月中頃、
ある婦人が 永原村を尋ねて来て、
「この村に 乳吞児を預かって世話して下さる人はいませんか」
と、村の駄菓子屋の老婆に声をかけた。(駄菓子屋の老婆は)
「岡本さんのお宅は 乳余ると言うていなはったがナァ…
けど、取らはらへんやろナァ。
(どうせアンタも) 行きはらへんやろ…」
と(答えた)。それを聞いた婦人は、(藁にも縋る思いで) 岡本家に行った。
そこで、
「駄菓子屋で聞いたのですが、子供が可哀想でなりませんから、乳呑児を一人助けると思って預かって貰えませんでしょうか…」
と、事情を話して哀願した。
しかし、岡本家としても見知らぬ人であるところから、
その日は「考えておく」と言って断った。ところが、その翌日、
妻・(岡本)志那子が、身上で苦しみ出した。
(そこで、乳児の)長男・栄太郎(後の4代会長)と共に 庄屋敷に運び (たすけを願った。)(すると) 教祖から、
「志那子さんえ、赤子に乳やる程 立派な助けはないで。どうぞ、助けてやっておくれ」と言われた。
(岡本)志那子は恐れ入り、早速 その子を訪ね、世話をした。
(そうした)ところ、(その時は)弱々しい8ヵ月子であった(の)が、
その後(は) 育ちも良く、普通の子供同様、むくむくと(元気に)成長した(のであった)。(岡本志那子が) 後日、その子を連れてお屋敷に参った時、教祖は
「志那子さん、良い事しなはったなあ」
と言われ、喜ばれた。
『稿本天理教教祖伝逸話篇』
86.大きなたすけ
大和国永原村の岡本重治郎の長男善六と、その妻シナとの間には、7人の子供が授かったが、無事成人させて頂いたのは、長男榮太郎と末女カンの二人で、その間の5人は、あるいは夭折したり流産したりであった。
明治12年に、長男榮太郎の熱病をお救け頂いて、善六夫婦の信心は、大きく成人したのであったが、同14年8月ごろになって、シナにとって一つの難問が出て来た。
それは、永原村から約1里ある小路村で6町歩の田地を持つ農家、今田太郎兵衛の家から使いが来て、
「長男が生まれましたが、乳が少しも出ないので困っています。何とか預かって世話してもらえますまいか。無理な願いではございますが、まげて承知して頂きたい。」
との口上である。
その頃、あいにくシナの乳は出なくなっていたので、早速引き受けるわけにもゆかず、
「お気の毒ですが、引き受けるわけには参りません。」
と断った。
しかし、「そこをどうしても」と言うので、思案に余ったシナは、
「それなら。教祖にお伺いしてから。」
と返事して、直ぐ様お屋敷へ向かった。
そして、教祖にお目にかかって、お伺いすると、
「金が何んぼあっても、又、米倉に米を何んぼ積み上げていても、直ぐには子供に与えられん。人の子を預かって育ててやる程の大きなたすけはない。」
と仰せになった。
この時、シナは、
「よく分かりました。けれども、私は、もう乳が出ないようになっておりますが、それてもお世話できましょうか。」
と、押して伺うと、教祖は、
「世話さしてもらうという真実の心さえ持っていたら、与えは神の自由で、どんなにでも神が働く。案じることは要らんで。」
とのお言葉である。
これを承って、シナは、神様におもたれする心を定め、「お世話さして頂く。」
と先方へ返事した。
すると早速、小路村から子供を連れて来たが、その子を見て驚いた。
8ヶ月の月足らずで生まれて、それまで、重湯や砂糖水でようやく育てられていたためか、生まれて百日余りにもなるというのに、やせ衰えて泣く力もなく、かすかにヒイヒイと声を出していた。
シナが抱き取って、乳を飲まそうとするが、乳は急に出るものではない。
子供は癇を立てて乳首をかむというような事で、この先どうなる事かと、一時は、心配した。
が、そうしているうちに、2〜3日経つと、不思議と乳が出るようになって来た。
そのお蔭で、預かり児は、見る見るうちに元気になり、引き続いて順調に育った。
その後、シナが、丸々と太った預かり児を連れて、お屋敷へ帰らせて頂くと、教祖は、その児をお抱き上げ下されて、
「シナはん、善い事をしなはったなあ。」
とおねぎらい下された。
シナは、教祖のお言葉にしたがって通るところに、親神様様の自由自在をお見せ頂けるのだ、ということを、身に沁みて体験した。
シナ26才の時のことである。
『稿本天理教教祖伝逸話篇』
91.踊って去ぬのやで
明治14年頃、岡本シナが、お屋敷へ帰らせて頂いていると、教祖が、
「シナさん、一しょに風呂へ入ろうかえ。」
と仰せられて、一しょにお風呂へ入れて頂いた。
勿体ないやら、有り難いやら、それは、忘れられない感激であった。
その後幾日か経って、お屋敷へ帰らせて頂くと、教祖が
「ようお詣りなされたなあ。さあさあ帯を解いて、着物をお脱ぎ。」
と、仰せになるので、何事が心配しながら、恐る恐る着物を脱ぐと、教祖も同じようにお召し物を脱がれ、一番下に召しておられた赤衣のお襦袢を、教祖の温みそのまま、背後からサッと着せて下された。
その時の勿体なさ、嬉しさ、有り難さ、それは、口や筆で表すことの出来ない感激であったシナが、そのお襦袢を脱いで、丁寧にたたみ、教祖の御前に置くと、教祖は、
「着て去にや。去ぬ時、道々、丹波市の町ん中、着物の上からそれを着て、踊って去ぬのやで。」
と、仰せられた。
シナは、一瞬、驚いた。
そして、嬉しさは遠のいて心配が先に立った。
「そんな事をすれば、町の人のよい笑ものになる。」
また、
「おぢばに参拝した」と言うては警察へ引っ張られた当時の事とて、
「今日は家へ去ぬことが出来ぬかもしれん。」
と、思った。
ようやく、覚悟を決めて、
「先はどうなってもよし。今日は、たとい家へ去ぬことが出来なくてもよい。」
と、教祖から頂いた赤衣の襦袢を着物の上から羽織って、夢中で丹波市の町中をてをどりしながらかえった。
気がついてみると、町外れへ出ていたが、思いの外、何事も起こらなかった。
シナは、ホッと安心した。
そして、赤衣を頂戴した嬉しさと、御命を果たした喜びが一つとなって、二重の感激に打たれ、シナは、心から御礼申し上げながら、赤衣を押し頂いたのであった。
岡本善六初代会長の回心(明治15年)
その後、(岡本)善六(の方)は、家事半分、道半分の信仰であった。
明治15年5月半ば、(妻の)志那子は 乳が腫れて困り、
いつもの如く 庄屋敷へ行くと、
教祖は 1枚の「こうやく」をべったり貼って
「あんた一人の信仰ではいかん、連れ合いも連れておいで」
と言われた。しかし、(岡本)善六は 農事の忙しさに つい時を過ごし、
5月が7月になった。当時 全国を襲った「コレラ」が大和地方でも猖獗を極め(ていた。)
(そうしたところ、なんと)長男・栄太郎もこの病にかかり、その熱に冒され(るようになってしまっ)た。一人息子の苦悶を見ることは、(岡本)善六にとって わが身にかかる病よりもつらいことであった。
(しかし) 庄屋敷へは、5月に教祖より話をうかがい そのままにしておいたため、
気が咎めて行きづらく、思案に暮れていた。そこで、親戚にあたる山中忠七に一部始終を話し(てみ)た。
(そうした)ところ、山中忠七に お屋敷へ行くことを勧められ、
そうすれば (息子)栄太郎の病気は(きっと)治る、と元気づけられた。これが、(明治15年) 旧7月の半ばも過ぎた13日の出来事である。
(山中忠七からの助言を受け思案し) 心の定った(岡本)善六は、
(これからは)道専務になる(という)決意をして (息子のたすかりを) 願った。
(そうした)ところ、心通りの守護を頂くことができたのであった。この時の感激は、
(岡本)善六にとって、終生 忘れがたいものとなった。以後、(岡本)善六は、家業の農事は人に委せ、
生まれ変わった様に 教えに専心した。
おたすけに おてふりに、あるいは 講の結成に、と活躍した。
日元講の発足(明治19年)
明治18、9年の三島付近の講社は、各村において 群雄割拠の如き状を呈し(ていた。)
(そこで) 当時 本部に詰めていた(岡本)善六は、
井野弥市郎、上田民蔵等と相談の上、
本部前の石西三五郎宅において、結講(を企画し) 第1回(目)の会合をした。(その時) 参加したのは、
おぢば周辺の 57ヵ所の講元等であった。講長には辻忠作が選ばれ、
講名も「日元講」として発足することに決まった。
明治19年 旧11月の事である。その後、
明治20年正月頃には 本部東方の「鈴木芳太郎」宅を借受け、
講社一般の取扱いをすることとなった。
岡本善六講長の就任〜旭日支教会の設立(明治23年〜明治28年)
その後、各地に教会が設立されるに及んで「日元講」でも名称の設立を願い出たが、「おぢば」に近い関係で本部より許可されず、講名のまま内容の充実を計った。
こうした中で 明治23年、岡本善六は 辻忠作より (日元講の)講長を引継いだ。
(日元講の)講長となった岡本善六は、
本部勤務に専念するかたわら、常に 教会創設を心にかけ(つつ過ごし)、
(時満ちて、ついに)
明治28年3月13日、
奈良県山辺郡朝和村字永原において「旭日支教会」設立のお許しを得た(のであった)。「旭日支教会」開設の許しを得た教信者は勇み立ち、次々と教勢は拡張していった。
更に 神殿建築の議が起こり、
初代会長・岡本善六を中心として、
明治34年敷地を買収し、教会新築に取掛かり、
明治36年8月、付属建物を含めた総工事が完成した。明治37年3月9日、鎮座祭を執行し、翌日(3月10日) 落成奉告祭を執行した。
多大の負債に伴う停滞〜岡本善六初代会長の辞職(明治37年頃〜明治39年)
ところが、多大の負債が残り、
加えて 日露戦争が勃発し、会計面に意を注いでいた初代会長の子息・栄太郎(4代会長)が(軍役に) 召集されてしまうなど(悪条件も重なり)、
その後の教会の状況は思わしくなく(なった。)
(それは) 岡本家の全財産を投入しても (全く)局面打開の見通しがつかない程だった。その打撃によって、(岡本善六)初代会長は 軽い中風をも併発し、会長の職を辞した(のであった)。
山沢為造2代会長の就任〜神殿建築・分教会への昇格(明治39年〜明治43年)
(事情を承けて) 事情整理のため本部より派遣されていた山沢為造が
明治39年11月28日、旭日支教会2代会長に就任した。(山沢為造2代会長は)
教会の土地建物を一切売却して 負債の整理に当たると共に、
教会を 奈良県山辺郡二階堂村田井之庄、
中西憲一の離れ屋に移転した。その後、(混乱も収束して) 教線も拡大し、
次々に 部属宣教所の設置を見るようになった。(その勢いのまま) 神殿建築にとりかかることとなり、
明治43年12月10日(には) 移転新築工事完成。
翌(12月)11日、分教会への昇格と併せて「昇格新築奉告祭」を執行した。所在地は、奈良県山辺郡二階堂村大字田井之庄127番地である。
桝井安松3代会長の就任前後(大正4年〜大正15年頃)
(大正3年12月31日) 初代管長出直しのため、
(旭日分教会)2代会長・山沢為造が、
管長職務摂行者として「本部」に帰る事となった。(そのため)
(旭日分教会の)後任会長を 更に本部に奏請して、
(その結果) 3代会長に 桝井安松が就任する運びとなった。3代会長・桝井安松は、
明治10年4月9日、
桝井伊三郎の長男として誕生(した)。(桝井安松は)本部に勤務していた(のだ)が、
父・伊三郎の「旭日」との縁故により、
大正4年(1915) 2月25日、
旭日(分教会の)3代会長に就任(したのだった)。この前後、
旭日分教会としては 最も多くの部属教会の新設を見た。大正5年から10年まで1ヵ所の新設もなかった「旭日」が、
大正11年から大正15年までの間に 18ヵ所の新設を見るに至り、
部内教会(は) 40ヵ所を数えた。
中教会への昇格(大正15年頃〜昭和3年)
教祖40年祭が執行された大正15年、
「旭日」では、中教会への昇格を提唱し、昇格に向けて拍車をかけた。(そして) 昭和3年5月19日、
本部より(中教会)昇格の許しを得た。
岡本栄太郎4代会長の就任(昭和4年)
(中教会への昇格を果たした)桝井(安松)中教会長は、
教祖40年祭以降 本部の教務が多忙となったため、帰任することとなった。(そこで) 後任会長に岡本栄太郎を推挙し、
昭和3年(1928) 7月23日、
本部の許しを得て (岡本栄太郎が) 4代会長に就任した。4代会長・岡本栄太郎は、
明治7年1月10日、
初代会長・岡本善六の長男として誕生(した)。部内教会の整理に力をつくし、
教会内容の充実 または 教線の拡張に東奔西走した。昭和4年1月20日、
5千名余の教信者の参加のもと、盛大な(4代会長)就任奉告祭が執行された。
旭日中教会の発展(昭和4年頃〜昭和11年頃)
(岡本栄太郎4代会長は) 就任早々、
同年(昭和4年) 8月、
本部員・松村吉太郎を迎え、おさづけ拝戴者 並びに 教師大会を開催、
教勢倍加運動を起こした。この声に応えて、12ヵ所の教会が新設された。
折りしも、教祖50年祭・立教100年祭が本部より発表され、
両年祭に対する第一歩を踏み出した(時であった)。昭和7年4月(には)、
4万本の足場木を滝本山より本部へ運搬、本部神殿ふしんの声に応えて立ち上った。そうした中、
昭和9年11月4日、3代会長・桝井安松が出直し、
(また) 昭和11年7月20日には、2代会長・山沢為造も出直した。岡本(栄太郎4代)会長は、この(ような節目の) 時にあたって
「教祖殿」建築の議を提唱。婦人会旭日支部に呼びかけ、その土台となるよう激励し、完成を誓った。
中教会から旭日大教会への昇格(昭和13年頃〜昭和15年)
昭和13年、本部の教規変更に伴い、(旭日中教会の) 大教会昇格の議が起こった。
昭和15年2月8日、昇格相談役・中山慶太郎の来会を得て 臨時役員会議を開催。
(会議では) 役員一同が、昇格に賛同。
(それを受け) 早速 願書を提出した。(その結果) お許しが出て、
昭和15年2月14日、(旭日中教会は) 大教会に昇格した。
時に、「旭日支教会」設立以来 46年目(のこと)であった。
岡本重善5代会長就任〜岡本栄太郎4代会長出直し(昭和16年〜昭和20年)
昭和16年7月2日、岡本重善が (旭日大教会)5代会長に就任した。
「旭日」の上に多大なる力を注いできた4代会長・岡本栄太郎は、
“大正年間に建築された神殿を改めて新築するという大事業は 後々の者に残しておく…”
と言い残して、昭和20年2月24日 出直した。
神殿ふしん(昭和25年〜昭和35年)
(岡本重善5代会長は)
(岡本栄太郎)4代会長の遺志を受継ぎ、4代会長の設計に 更に意見を加えて、
昭和25年10月秋の大祭を期し、いよいよ 神殿新築の議を発表(した)。(岡本重善5代会長の打ち出しを受け、一同) その準備に取り掛ったが、
本部より 昭和31年1月の教祖70年祭に向かっての発表があったため、
旭日(大教会)は、 一時 神殿建築の準備を中止して 本部のつとめに徹(する事と)した。(そして) 昭和31年、教祖70年祭も無事終了した(のを見届けて)
3月6日(の)役員会議の席上で、
岡本重善代5会長より、延期されていた大教会神殿ふしんの議が、再度 発表された。この声に全員呼応し、
昭和31年8月25日、
本部の許しを得て その準備に取掛かった。昭和32年1月25日に釿始め、同年(昭和32年) 9月25日上棟式、
昭和35年11月22日 鎮座祭、翌(11月)23日 奉告祭を、
2代真柱・中山正善夫妻を迎えて、
(また) 更に多数の来賓の列席も得て、盛大に執行した。
教祖80年祭と創立71周年記念祭(昭和41年)
教祖80年祭がつとめられた昭和41年、
旭日大教会においても、3月23日 教祖80年祭を執行(した)。同年(昭和41年)10月31日(には)、
旭日大教会創立71周年記念祭を、
2代真柱、随行者を迎えて 盛大に執行(した)。更に、
その頃提唱された「1 人が3人のよふぼくを」という ぢばのスローガンに応えて、
全よふぼくが にをいがけ・おたすけに励んだ。この成果に対し、
真柱より、
その苦労を称えての「丹精」の額が下付された。
岡本善孝6代会長就任〜創立80周年記念祭(昭和46年〜昭和50年)
昭和46年10月24日、
秋季大祭後の役員会議の席上、
5代会長・岡本重善が 会長辞任の意志を発表(した)。後任会長に 岡本善孝を推挙し、
昭和46年12月26日、(岡本善孝は)6代会長就任のお許しを受けた。昭和47年3月29日、6代会長就任奉告祭を就行。
(それに合わせて)
昭和47年3月28日の夕勤後(に)、
2代真柱祖霊の合祀祭を、多数の来賓、2千5百余名の帰参信者を迎えて 盛大に執行した。昭和48年1月26日、教祖90年祭の発表があり、
『諭達第2号』を以って 年祭活動の指針が公布された。旭日(大教会)においては、
昭和50年3月30日、大教会創立80周年記念祭を
真柱夫妻、多数の来賓の臨席を得て盛大に執行し、
教会内容の充実と教会名称の増設を目指し、創立90周年へ10年の歩みをはじめた。〔現住所〕〒632-0071 奈良県天理市田井庄 128番地
〔電話〕0743-63-1324(昭和50年12月31日調「天理教統計年鑑」昭和50年度版)
(『天理教事典』1977年版 P,16〜18)
おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。
49回目の今回は、
「旭日大教会」初期の歴史を勉強しました。
当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。
とても古い資料なので、
記載内容も 1970年代以前までとなっており、
かなり昔の歴史にとどまっています…
しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。
十分 私のニーズは満たされるので、
そのまま書写し続けております (^_-)-☆

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】49回目の当記事では
『天理教事典』の中の「旭日大教会」についての記述を書き写して勉強しました。
旭日大教会といえば、おぢばのすぐ近くにある大教会ですよね。
天理大学体育学部のすぐ前にあって、かつておぢばで生活していた頃、こんな近くに大教会があるんだぁ…と驚いたことを覚えています。
旭日大教会の前身は「日元講」なのですね。
『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社)という本の中に、次のように書かれてありました。
文久三年には豊田村の仲田儀三郎が妻かじの産後の患いより中山を訪ね、辻忠作が妹くらの気の間違いより入信した。
儀三郎は村人の嘲笑を意に介さず、昼も夜も弁当持ちで通って来て教祖にお仕えした。その姿を見て忠作は、
「さよみさん(儀三郎のこと)が行く限り、わしも行く」
と、一徹な信仰によって多くの人を導いた。明治十九年、日元講を結び、二十三年には岡本善六に受け継がれ、後に旭日大教会となる。
(『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社) P,66)
日元講は、おぢば周辺に散らばっていた講社を束ねる形で、辻忠作先生を初代講元として、明治19年に結成されたのですね。
そして、明治23年に岡本善六先生が辻忠作先生の後を継いで講元となり、その5年後の明治28年に日元講が「旭日支教会」になった、と。
そのような歴史を書き写しながら思い出したのは、第33回で勉強した「城法大教会」の歴史でした。
その回の書き写し学習を通して、
城法大教会も、
(日元講よりは遠いけれど)おぢば近くで信仰していた講社を束ねる形で「心実講」を結成し、それが母体となって「城法支教会」という教会組織になったのだ、
ということを学びました。
旭日大教会も、
おぢば近くで信仰している講社を束ねる形で「日元講」を結成し、それが母体となって「旭日支教会」という教会組織になった。
まさしく相似形 (^^)‼︎
しかし、へそ曲がりな私は、今回「旭日大教会」書き写し学習をしながら、
似たような背景を持つ教会でありながら、「城法」と「旭日」では、設立時のご本部の姿勢がちょっと違うんだなぁ…
というところに、ちょっと引っ掛かってしまいました (^^ゞ
明治21年4月に天理教教会本部が公認されて各地で教会設置の動きが見られるようになったわけですが…
「城法支教会」の教会設立の動きについて、『天理教事典』には次のように書かれてありました。
【城法支教会】
明治21年 4月 天理教会(本部)が認可なったときは、奈良県 計43講社、信者戸数千有余を数えた。
かかる隆盛をみて、明治21年 法貴寺 市川(重郎平)屋敷内に 3間に7間の「集談所」の建物を建築したものの、
各地で教会設置が相次いだのに反し、「心実組」が (城法支)教会として開設に至るのは明治25年のことであった。この間の消息を推測するならば、
40に余る講社の大部分が おぢば から10km内外の近在で、それがため おぢばの「うちらのもの」たる意識が少なからず働いていて、ことさら教会を設置し 公認を得なければ ということもなかったし、
あるいは、それぞれの講元らが 教祖の直弟子である という自負もあり、入信の系譜も一筋でないところから 皆の心がまとまらず 教会開設の機運が盛り上がることがなかったから ともいえよう。しかしながら、
明治25年 1月22日(陰曆明治24年12月23日) 「心実講」集談所の月次祭当日、
本部より出張した 喜多治郎吉、地元出身の 鴻田忠三郎、宮森与三郎らが 公認を勧めたため、
前川喜三郎 以下、各講元、周旋人らが相談し、集談所の建物を 1間建て増して 4間に7間とすることにして(教会を設立することで相談がまとまった。)
(そして実際に) 本部へ願い出たのは その翌日(明治25年1月23日)のことであった。同(明治25年) 2月10日 本部の添書を得、
同(明治25年) 3月14日には 奈良県庁の認可がおりた。(太線はブログ主による)
(『天理教事典』1977年版 P,393)
一方、今回書き写し学習をした「旭日支教会」設立の動きについては、
『天理教事典』には次のように書かれてありました。
【旭日支教会】
各地に教会が設立されるに及んで「日元講」でも名称の設立を願い出たが、
「おぢば」に近い関係で本部より許可されず、講名のまま 内容の充実を計った。こうした中で 明治23年、
岡本善六は 辻忠作より (日元講の)講長を引継いだ。(日元講の)講長となった岡本善六は、
本部勤務に専念するかたわら、常に 教会創設を心にかけ(つつ過ごし)、(時満ちて、ついに)明治28年3月13日、
奈良県山辺郡朝和村字永原において「旭日支教会」設立のお許しを得た(のであった)。「旭日支教会」開設の許しを得た教信者は勇み立ち、次々と教勢は拡張していった。
(太線はブログ主による)
(『天理教事典』1977年版 P,16)
「城法支教会」の方は、
「心実組」の講社の方から教会設立を願い出たというより、
喜多治郎吉、鴻田忠三郎、宮森与三郎等【ご本部】の先生方が積極的に勧めることで、教会設立へと進んでいった。
それに対し、「旭日支教会」の方は、
「日元講」の講側から教会設立を願い出たのだけれども、「おぢば」に近過ぎるということで【ご本部】から なかなか許可が出ず、
岡本善六先生が辻忠作先生から日元講の講元を引継いでから「5年目」に、やっと教会設立に至った。
ご本部が積極的に後押しして教会となった「城法支教会」、
当初、ご本部は 当事者の教会設立願いに 消極的だった「旭日支教会」。
今回、書き写しをしながら、
似たような背景なのに 対応が違うのはどうしてなのかなぁ…
等と思ってしまいました。
…しかし、まぁ、そんなのはどうでもいいことですよね。
単純に、
「旭日支教会」はおぢばから近過ぎる、教会にならずとも おぢばに参拝したらよろしい、
ということだったのかもしれないし。
( いや、普通に考えれば、そうでしょう。何をことさらに…という声が聞こえてきそうです (^^;) )
ちょっと、どうでもいい所に引っ掛かってしまいました。
我ながらお恥ずかしい… (#^^#)
(しかし、未熟者の素朴な感想の一つであることは確かですから、恥を忍んで、消さずにそのまま残しておきます。(^_-) )

些細な部分にとらわれたことを長々と書き連ねてしまいましたが、
今回の書き写し学習の中では、
岡本善六初代会長が長男の身上を通して心の向きがガラリと変わり、神様と本気で向き合うようになった、
という史実が心に残りました。
最初の「てをどり6人衆」の一人であった 父親・岡本重次郎先生の信仰を受けて、
甘露台 石曳きひのきしんを始め お屋敷の御用をつとめてはいたものの 中途半端な信仰で
おやさまから 奥様(岡本志那子先生)に「あんた一人ではいかん、連れ合いも連れておいで」とまで言われた「岡本善六」先生。
そんな岡本善六先生も、
長男(岡本栄太郎先生)が コレラに罹患して苦しむ姿を通して、
己の歩み方を見直さざるを得なくなられた。
そして、道専務を決断したところ、
長男の身上を おたすけ頂き、
その感激が、日元講から旭日支教会を生み出すエネルギー源になった、
というわけだったのですね。
親から信仰の世界を受け継いだ者にとって、
何となく…の「惰性の信仰」から「本気の信仰」へ…
という切り替えは なかなか難しいものがある、
ということが、
道の先達である 岡本善六先生の足跡からも わかります。
たとえ 幼い頃より 親によって信仰の世界に身を置く境遇を与えられていたとしても、
「本気で」 神様と向き合うか否かについては、
信仰初代の人々と 何ら変わりはない。
人間は、身を切られるような苦しみ等の契機がなければ、なかなか神様と本気で向き合おうとしないもの。
本気で向き合ってほしい神様は、
だからこそ、たとえ親の代から信仰の世界に身を置いている者に対しても、
心の向きを変えるための契機を
(多くの場合、当事者にとって苦しみと感じられる形で)
もたらされる――
今回、岡本善六先生のご事歴に触れることで、
改めて、そのことを教えられたような気がします。
…また、わかったふうなことを書いてしまいました。
お前が言うな、という声が聞こえてきます (>_<)
このぐらいで終わりにしたいと思います (^^;)

その他にも、知らないことばかりでした。
今回もまた、書き写しを通して多くのことを知ることができ、とても勉強になりました。
有難いことでした。
「人に歴史あり」
組織にも歴史あり…
歴史を踏んで今がある――
だからこそ、
今を輝かせるためには
「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。
ということで――
今回は「旭日大教会」初期の歴史の勉強でした。
人生、死ぬまで勉強。
今後も、勉強し続けていきたいと思います。
ではでは、今回はこのへんで。

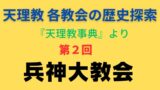
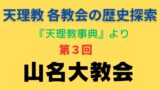
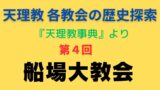
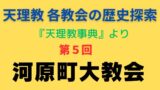
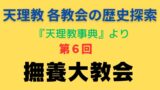
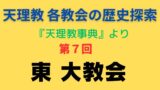
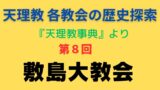
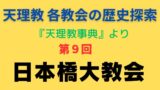
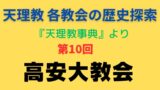
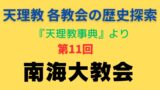
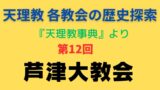
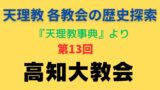
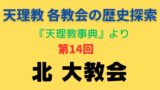
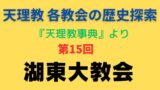
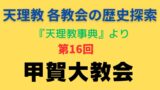
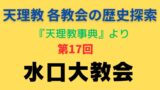
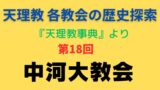
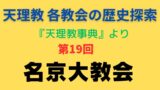
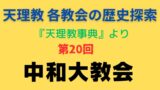
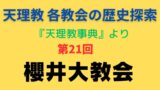
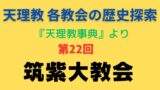
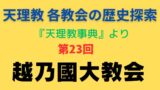
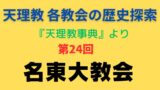
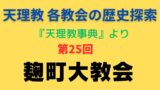
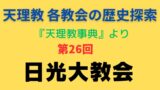
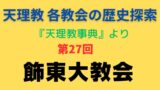
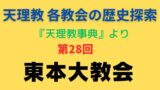
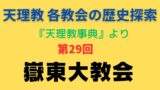
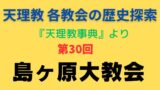
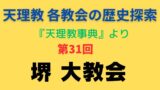
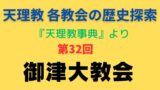

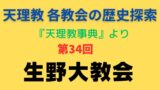
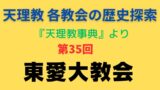
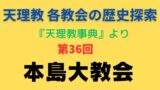
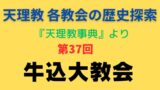
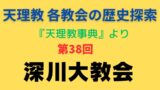
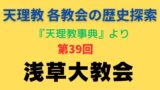
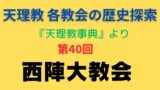
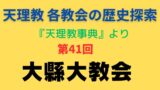

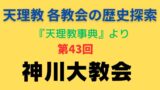
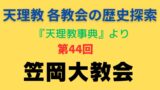
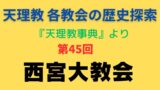
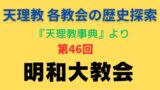
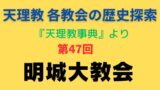
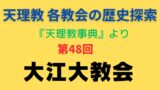
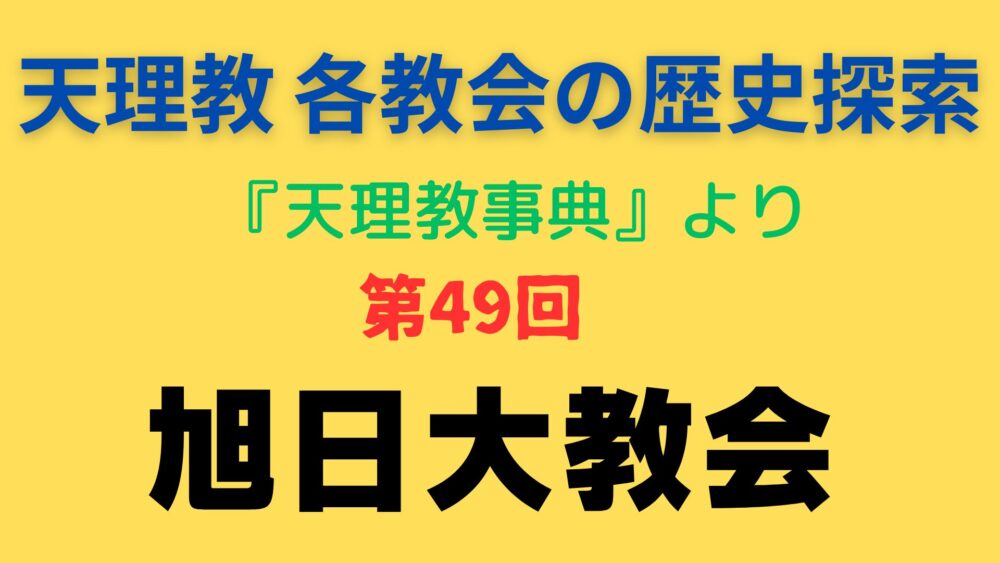
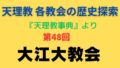
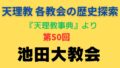
コメント