Dear everyone,
こちらは、
ふらふら彷徨う「さまよい人」による
『さまよいブログ』
= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。
今回も、
『天理教事典』(1977年版)に記載された
各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。
私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)
最新版👇
このシリーズを始めた理由については、
当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。
前回は、
教会番号66番「香川大教会」の『天理教事典』記述を書写して
その歴史を勉強しました。
今回は、
教会番号67番「中紀大教会」について勉強します。
- 中紀大教会(ちゅうき だいきょうかい)
- 中紀大教会の芽生え、岩本卯平 親族の不思議なご守護(明治20年〜明治21年頃)
- 大洪水後 岩本卯平のおたすけ活動、竹田夫妻の入信(明治22年頃)
- 正明講 第5号 の結成(明治23年)
- 集談所の設置(明治23年〜明治24年)
- 高まる反対攻撃をはね除け 伸びる教勢(明治24年頃〜明治25年頃)
- 中紀支教会の設置(明治25年)
- 教会建物のふしん〜開筵式(明治25年〜明治26年)
- 相次ぐ部内教会の設置(明治25年〜明治36年頃)
- 全国布教(明治28年〜明治35年頃)
- 経済的困窮時代(明治20年代後半〜明治30年代)
- 中紀分教会への昇格(明治42年)
- 大洪水後の教会移転〜神殿ふしん、教祖40年祭活動(大正6年〜大正15年頃)
- 南海大教会からの分離、中紀中教会への昇格前後(昭和10年〜昭和12年)
- 中紀大教会への昇格(昭和15年〜昭和16年)
- 西 松太郎 初代会長の辞任、西 千代造2代会長の就任(昭和17年)
- 西 千代造2代会長の辞任、畑林為喜3代会長の就任(昭和26年)
- 創立60周年記念祭、3代会長就任報告祭(昭和27年)
- 教会移転打ち出し~畑林為喜3代会長の出直し(昭和42年頃)
- 畑林清次4代会長の就任~教会移転建築の完遂(昭和43年~昭和46年)
- 創立80周年記念祭(昭和47年)
- おわりに
中紀大教会(ちゅうき だいきょうかい)

中紀大教会の芽生え、岩本卯平 親族の不思議なご守護(明治20年〜明治21年頃)
中紀大教会の芽生えは、
明治20年(1887)のことといわれる。和歌山県 西牟婁郡 岩田村の 岩本卯平は、
ある事情から その土地を去り、
三重県 南牟婁郡 相野谷村 大字桐原で、線香製造業を始めた。これより先、
同じ (和歌山県) 西牟婁郡西谷村で線香製造業をしていた 彼の甥・稲田熊次郎が
3年あまり前から病床につき 生活が困窮をきわめていたので、
(岩本)卯平は (彼を)
(三重県 南牟婁郡の) 桐原に呼び寄せて、職人の監督に当たらせることにした。(呼び寄せた 稲田)熊次郎の、次女・かや が、生来の虚弱体質であった。
明治21年の6月頃、その(稲田)かや (当時6歳とされる) が、
腸疾患のため、1週間あまり 昏睡状態が続いた。岩本卯平が医者を迎えようと平尾村へ急いでいる途中、
知人の 粂右衛門 (姓不詳、南牟婁郡尾呂志村大字片川の人) に逢った。
(大層急ぐ岩本卯平の様子を訝しんで、粂右衛門が どうしたのかと尋ねてきたため)
岩本卯平が事の由を告げたところ、粂右衛門は
「その医者は 親が亡くなって留守であるから 行っても駄目や。私が行って 神様にお願いしてあげよう」
というので、(二人は)同道して、(三重県 南牟婁郡) 桐原に引き返した。粂右衛門は 燈明をともし、これを めどうとして 水を供え、お願いして帰った。
(そうしたところ)
翌朝になると、(1週間あまり昏睡状態が続いていた) かやが、昏睡状態から覚め、食欲も旺盛になった。この粂右衛門(という人物) は、
以前、妻の病気を、同村 (三重県南牟婁郡尾呂志村) の正明講長・山田作治郎 (後の南海大教会 初代会長) に救けられ(た経験の持ち主だった。
その時の) 神様の不思議な働きに (強く) 心打たれていたので (稲田)かやの病気に対して お願いをしたものと思われる。(甥の娘をたすけて頂いた感激に満たされた) 岩本卯平は、
やがて梅雨期に入り 線香製造の仕事が閑散となったので、
故郷の (和歌山県 西牟婁郡) 岩田村に帰り、
村人に 天理王命の不思議な救けを語ったという。
大洪水後 岩本卯平のおたすけ活動、竹田夫妻の入信(明治22年頃)
さて、明治22年8月18日、
(和歌山県) 西牟婁郡地方が 大洪水に襲われた。富田川は 一夜に 555名の溺死者を生じ、
また 岩田村でも 田畑は一面の河原と変わり、
その惨状は 言語を絶するものがあった。(三重県 南牟婁郡の) 相野谷村から 急いで見舞のため (和歌山県の岩田村へ)帰村した岩本卯平は、
竹田しか (民蔵の妻) が 熱病のため 永く病床に呻吟していると聞いて、
竹田宅を訪ね 神様のお話を取り次いだ。
そして、 (三重県南牟婁郡) 尾呂志村の 宮の芝 (山田作治郎の屋号=正明講) に参拝するように勧めた。(岩本)卯平は、竹田夫妻とともに (明治22年)10月16日に 宮の芝 (正明講) に参拝。
山田(作治郎) 講長から教理を聴き、(また、熱病で永らく苦しんでいた竹田)しかは、おさづけの取次ぎを受けた。
(その結果) 1ヵ月余りの滞在の内に、(竹田しかは) 全快するに至った(のだった)。このおたすけを契機として、竹田夫妻は 熱心な信者となった。
(その後、竹田)民蔵は、(岩本卯平の線香製造工場がある三重県南牟婁郡) 桐原に滞在して、
4ヵ月余 岩本卯平の (線香製造業の) 仕事を手伝いながら、
月3回の (正明講の) 講社のお祭りには、3名揃って欠かさず参拝。
そして、熱心にお話を聞いた。かくて、その信仰が進むと共に 布教の決意が固まり、
同年(明治22年)末、3名は、(三重県 南牟婁郡) 相野谷村での (線香製造業の) 仕事を放棄して、
故郷の (和歌山県 西牟婁郡) 岩田村に帰った。当時 既に (和歌山県 西牟婁郡) 岩田村には 若干 信仰する者がいたけれども、
かくして、(岩本)卯平は、自宅を講元とし 竹田民蔵と共に 布教第一歩を踏み出したのである。
正明講 第5号 の結成(明治23年)
明治23年1月、
正明講長・山田作治郎が、(和歌山県 西牟婁郡) 岩田村の 竹田宅を訪ね、
同年(明治23年) 3月には、
畑林(為七) 副講長が、西 松太郎を伴い、西牟婁郡に出張している。当時、
山田(作治郎)・畑林(為七) 正副講長の この地方への巡教、及び、岩本(卯平)・竹田(民蔵) 両人の手引で入信した 主な人々には、
福田銀之助、真砂平次郎、真砂伊平、福田幸吉、岩本重三郎、谷本庄平、平田平作、山本宇平、羽山佐平、福田半吉、福田角蔵、稲垣卯作、
らがある。更に、(明治23年) 8月には、
(和歌山県) 栗栖川村大字北郡の 医師・石田玄益、
(明治23年) 12月には、
(和歌山県) 日高郡竜神村の 久保清五郎、(和歌山県) 西牟婁郡三舞村の 下村兵蔵など、
地方の有力者の入信が相次ぎ、信者が 次第に増加していった。そこで、明治23年5月、
岩本卯平を中心として、講が結成され、
これは「正明講 第5号」と定められた。
集談所の設置(明治23年〜明治24年)
(講は結成されたものの、明治22年の) 洪水後のこと(とて どの家も被害を受けており)、
(正明講第5号 結成後の) 講の集まりは、
被害の最も僅少だった 福田銀之助宅で行われていた。しかし (そこも)、信者の増加に伴い、やがて 狭小となっ(てき)た。
(そこで)
山田(作治郎)講長や 畑林(為七)副講長 の意向もあり、
(和歌山県 西牟婁郡) 岩田村に 集談所を設置することになった。敷地は (和歌山県西牟婁郡) 岩田1564番地、
羽山佐平 所有の 田地7畝余に 若干 (土地を)買い足して定め、
(明治23年)12月に (集談所建物の) 竣工をみた。この集談所は、翌(明治)24年12月28日に
「さあ/\尋ねる事情/\、所々旬々 事情治め方/\、許し置こう/\」
との おさしづを得て、
真砂平次郎 を所長として、本部の許しを得たのである。これが、現・中紀大教会の前身である。
信者たちは、これにより、
教理の研究や おてふりの練習に 夜のふけるのも忘れ(て打ち込むようになり)、
布教活動は 一層 活発となった。
高まる反対攻撃をはね除け 伸びる教勢(明治24年頃〜明治25年頃)
不思議な救けが現われて、信者の数も日に月に増加するのをみて、
寺院の僧侶たちは、
信者を呼びつけて講社脱退を強要したり、天理教撲滅講演会を開催したり、
露骨で執拗な妨害をし(てくるようになっ)た。しかし、信者たちの結束は 益々固く、
教えは 近郷一帯に伸び広がり、
(和歌山県 西牟婁郡) 岩田村を 正明講第5号として、
(和歌山県) 日高郡竜神村に (正明講)第5号の 2番、
(和歌山県) 西牟婁郡三舞村に (正明講第5号の) 3番、
(和歌山県) 栗栖川村北郡に (正明講第5号の) 4番、
(和歌山県) 二川村大川に (正明講第5号の) 5番、
(和歌山県) 東富田村に (正明講第5号の) 6番、
以上が 設けられた。
中紀支教会の設置(明治25年)
このような教勢の発展に伴い 教会設置の必要に迫られ、
周旋人たちは 協議を重ねた。(その後) 気運(も) ようやく熟し、
上級・南海分教会の指示のまにまに、
西 松太郎を担任として、教会設置を願い出た(のだった)。(そして) 明治25年(1892) 6月22日、
従来の集談所 所在地 (=和歌山県西牟婁郡) 岩田村大字岩田1564番地に、
「中紀支教会」設置の許しを受けた。
教会建物のふしん〜開筵式(明治25年〜明治26年)
(一同は、中紀支教会として) 待望の教会設置の許しを得たので、
従来の 集談所敷地の隣接地を買収し、集談所は 事務所に改造し、7間四方の神殿建設に着手した。(ふしんは順調に運び)
明治26年3月21日 上棟式、7月26日 鎮座祭、同月(7月)27日には 開筵式が執り行われ、
当日は、この地方 未曽有の盛況となった。
相次ぐ部内教会の設置(明治25年〜明治36年頃)
これと共に、
各地の講元・周旋人たちは 親教会である「中紀支教会」の設置に勇み立ち、
一層 布教に専心して、続々 部内教会の設置をみた。明治25年から明治41年までに設置された直属教会は、次の通りである。
(地方庁未認可は除く。なお、部属教会の数は この時19ヵ所を数える。)明治25年、富田、三舞、北郡、真妻、
明治26年、竜神、
明治27年、田辺、牟婁、
明治28年、芳養、
明治29年、太華、
明治33年、伍邨、鮎川、朝生、三栖、西江、富和、
明治36年、北陽、岡喜 (現・日延)。
全国布教(明治28年〜明治35年頃)
明治28年5月、
上級・南海分教会から提唱された全国布教の方針に基づき、
中紀(支教会) においても、続々と 遠隔の地へ布教師を派遣した。まず、この年(明治28年)には 板木平音吉が 宮崎へ、
翌年(明治29年)には
中松小太郎・玉置隆吉・中田円吉らが 島根へ、
山本源七は 鳥取へ、
玉田甚助・柳谷初太郎・高松又助らは 広島地方へ、
寺本金喜・松本村吉・鈴木留吉・稲垣民蔵・森佐七らは 山口地方へ、
それぞれ赴いた。なお、明治27年、
稗田彦平は 屯田兵の家族として北海道に移住し、
同(明治)35年頃から 布教を開始している。現在、これらの苦労は実を結んで、
北海道から九州にわたって 中紀の部内教会が設けられている。
経済的困窮時代(明治20年代後半〜明治30年代)
しかし、
当時は 神殿建築の後始末に苦しみ、
また 布教費の調達も意の如くならず、中途にして布教から引揚げて帰る者もあり、
中紀支教会は 遂に 多額の負債を生ずるに至った。これの整理は容易でなく、部内教会は 非常な辛酸をなめた。
その間、数々のおさしづを伺い 心の治め方を図る一方、
負債整理のため、3ヵ年間は、(西 松太郎)会長はじめ 役員一同も、
帽子を被らず、表付の下駄をはかず、時計を持たず、絹物一切を着用せず、禁酒禁煙を断行する旨の 申し合わせをした。明治33年6月には、
本部の許しを受けて
9家族 (谷川長助・高松又助・一岡為吉・楠本半三郎・松本村吉・谷本庄平・岩本重三郎・平田平作・鈴木留吉) が教会に引越し、教会出仕の人は増加したが、
その生活は困難を極めた。
教会当番は弁当持参であり、役員たちは 家財道具を持ち寄って 市をしたことも 再三に及んだ。病気になる者もあり、世間からはさげすまれて、
天理教の者といえば 信用がなく、
金銭は勿論、僅かの米さえ貸してくれる人がない という 悲惨な境遇が 長年にわたって続いた。
中紀分教会への昇格(明治42年)
その中、
やがて「節から芽が出る」のお言葉の通り、
明治41年 天理教が一派独立の許可を得て、
(それに伴い)
翌(明治)42年、中紀(支教会)は、分教会に昇格・改称(した)。この頃には、部属教会 37ヵ所を数えるに至った。
大洪水後の教会移転〜神殿ふしん、教祖40年祭活動(大正6年〜大正15年頃)
大正6年(1917) 8月、
富田川に 3回目の大洪水があった。元来、教会の敷地は、
先の明治22年の洪水に 河原となっていた荒地を 開いたものだった。(そのため) 出水の度毎に心配しなければならないところから、
その対応について (一同で)協議。
その結果、西(松太郎) 会長の提唱に従って、
(和歌山県) 田辺へ 移転建築することになった。大正8年、(和歌山県) 田辺山崎に敷地を買収して、神殿を建築。
(様々な節を乗り越えて、ふしんは完成。)
大正13年 5月1日・2日、
南海大教会長・山田清治郎を迎えて、神殿落成鎮座奉告祭を執行した。この神殿建築の工事と併行して、教祖40年祭の年祭活動につとめ、
大正11年から15年までに 29ヵ所の教会を新設した。
南海大教会からの分離、中紀中教会への昇格前後(昭和10年〜昭和12年)
昭和10年(1935)9月、
板倉槌三郎 本部員が 中紀(分教会) へ来会の折、
「東愛(分教会)は 今度 南海(大教会)から分離して中教会になった。中紀(分教会)も 早く100ヵ所の部内教会を設けて 中教会に昇格改称するよう 努めるがよい」
との勧めがあった。その勧めに従い、
教祖50年祭という時期にあわせて (南海からの)分離 (昇格) を実現したい
という 西(松太郎) 会長の意向(が表明され、それ)に 役員も賛成し(た。そして) 上級教会である南海大教会の同意を受けた上で、
翌昭和11年1月19日、(天理教教会)本部に 願書を提出。同(昭和11年1月)25日、
すなわち 教祖50年祭が執行される前日に
(中教会へ昇格改称の) 許しを受けた。翌(昭和)12年 2月には、信徒詰所の建築に着手した。
中紀大教会への昇格(昭和15年〜昭和16年)
その後、教会制度の改革に伴い、
昭和15年、(中紀は 分教会から) 大教会に昇格。
翌(昭和)16年5月8日に、昇格奉告祭を執り行った。
西 松太郎 初代会長の辞任、西 千代造2代会長の就任(昭和17年)
昭和17年、
西(松太郎) 会長は、長男・千代造に会長職を譲り、
専ら 本部へ出仕することとなった。(昭和17年) 2月、
2代会長 就任奉告祭が執り行われた。
西 千代造2代会長の辞任、畑林為喜3代会長の就任(昭和26年)
戦中戦後の混乱期も過ぎて「復元」の時を迎え、
新たに教会内容の充実に努めようとする気運の中で、
西 千代造(2代会長)は、
一身上の都合により 会長職を辞した。(そして)
昭和26年4月18日、
南海2代会長・畑林為七の嗣子・為喜が、
中紀(大教会)の3代会長として就任した。
創立60周年記念祭、3代会長就任報告祭(昭和27年)
畑林(為喜3代)会長は、鋭意 教勢の伸張を図り、
部内教会一同もまた それに応えて 活気を呈した。教祖殿改築、客殿建築、信者室、事務室の整備が行われ、
昭和27年11月17日には、
創立60周年記念祭、及び (3代)会長就任奉告祭を執行した。
教会移転打ち出し~畑林為喜3代会長の出直し(昭和42年頃)
また、かねてより、
教勢の伸展、交通事情 その他もろもろの背景から、
教会敷地の狭隘を感じていた 畑林(為喜3代)会長は、
新たな飛躍を図るべく 教会移転の必要性を痛感していた。(畑林為喜3代会長から教会移転の意向を示された) 部内教会も これに賛意を表し、
(和歌山県) 田辺市元町に 約5,000坪の土地を購入して
移転準備をすすめることとなった。大所高所に立ち、ゆるぎない信念に基づいて指導する (畑林為喜3代) 会長に従い、
しかも 新たに掲げられた「移転建築」という目標に結集して、
部内教会も 一段と活気づくかに見えた。ところが、昭和42年(1967)、
畑林(為喜3代)会長は 12月10日に 出直し(てしまっ)た。
畑林清次4代会長の就任~教会移転建築の完遂(昭和43年~昭和46年)
翌 昭和43年1月27日、
畑林清次が 4代会長として就任した。同年(昭和43年) 5月23日、(畑林清次)4代会長の 就任奉告祭が行われ、
(畑林為喜)前会長の遺志を継承して
翌(昭和43年) 5月24日、移転建築の起工式が行われた。昭和44年、神殿の起工式、(昭和)45年 6月22日には 上棟式、
と 次第に工事が進められた。(様々な節を乗り越え 無事 工事は完成し)
昭和46年5月11日には鎮座祭、
(そして、その翌日) 5月12日に
田辺湾と その先に広がる 太平洋の黒潮を見晴らす景勝の地 (和歌山県田辺市元町1355) に建てられた (壮大な)神殿 (=鉄骨コンクリート造・地上2階重層入母屋本瓦葺・床面積2,151.90㎡) の
落成奉告祭を (盛大に)執行(した)。
創立80周年記念祭(昭和47年)
更に、昭和47年5月12日には、
中紀大教会 創立80周年記念祭を 執行した。現在(『天理教事典』1977年版出版当時)、
部内教会、よふぼく、信者が一つになって、世界たすけに奔走している。〔現住所] 〒646-0050 和歌山県田辺市天神崎30−1
〔電話〕 0739-22-0459(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)
(『天理教事典』1977年版 P,514〜516)
おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。
67回目の今回は、
「中紀大教会」初期の歴史を勉強しました。
当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。
とても古い資料なので、
記載内容も 1970年代以前までとなっており、
かなり昔の歴史にとどまっています…
しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。
十分 私のニーズは満たされるので、
そのまま書写し続けております (^_-)-☆

中紀大教会は、南海大教会から分かれた大教会ですね。
南海大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】67回目の当記事では
『天理教事典』の中の「中紀大教会」についての記述を書き写したわけですが、
今回もまた、知らないことばかりでした。
『事典』という書籍の性格上 当然のことではありますが、
『天理教事典』(1977年版) の大教会解説というのは
本当に表面的なことを 執筆担当先生の目線で書いて下さっているだけなので、
ある程度の予備知識がないと 流れがよくわからないことが多いです。
今回の「中紀大教会」解説文でも、
最初は 流れがよくわからなくて、何回か読み返して やっと理解できました。(~_~;)
読み始め当初、
てっきり 岩本卯平先生が初代会長なのだ と理解してしまいました。
しかし、途中から、西 松太郎先生が会長として記述されていることに気付いて、
あれ?岩本卯平先生が初代じゃなかったっけ?と こんがらがりました。
で、前の方の文章へ戻ったり先へ進んだり…解説文全体を行ったり来たりすることで、
ようやく 流れをつかむことが出来たのでありました。
ちょっと整理してみます。
- 【岩本卯平 先生】 … 中紀大教会の母体となった「正明講 第5号」を結成した際の中心人物。
(『天理教事典』(1977年版) には 講元になった との記述がありませんでした。 講元になられたのではないかなぁ と想像しますが… ごめんなさい、詳しいところはわかりません。) - 【真砂平次郎 先生】 … 「正明講 第5号」が発展して開設された「集談所」(中紀大教会の前身) の所長。
(『天理教事典』(1977年版) に「真砂平次郎を所長として、(集談所設置の)本部の許しを得た」との記述がありますので、所長になられたのは 間違いないと思います。) - 【西 松太郎 先生】 … 「中紀支教会」として教会設置のお許しを得た際の会長=中紀大教会・初代会長。
(『天理教事典』(1977年版) に「南海分教会の指示のまにまに、西 松太郎を担任として、教会設置を願い出た」との記述がありますので、会長=初代会長に就任されたのは 間違いありません。)
岩本卯平先生を中心に 中紀大教会の母体となる「正明講 第5号」が結成されて、
それが、真砂平次郎先生を所長とする「集談所」に昇格して、
その後、それが 全教的な「教会設置ムーブメント」の流れに乗る形で「教会」という姿に衣替えするにあたって、
上級・南海分教会の意向もあって、西 初太郎先生が 初代会長に就任された――
そういう流れだったのですね。
頭が悪いもので、すんなり理解できなかった… お恥ずかしい (^^ゞ
それにしても、
「講」「集談所」「支教会」…と、
天理教の初期は、信仰共同体の名前が 色々ありますね。
共同体 変遷の経過を通して ずっと同一の先生が会長だとわかりやすいのですが、
その都度 代表者が変わると、
私のような信仰初級者は 流れを把握するのに時間がかかるのでありました。
いや、お前の頭が悪いだけだろ、
と言われたら、確かにその通りなのですが… (⸝⸝⸝¯ ¯⸝⸝⸝)

当シリーズにおいて天理教大教会 初期歴史を勉強する中で、
これまでにも、何回も、
経済的困窮時代のことが強調して記述されているのを 目にしてきました。
そうした経済的困窮時代の史実は、
読者である私にとって、強く 印象に残る内容のものばかりでした。
そして、今回の「中紀大教会」解説文でも、
経済的困窮時代についての記述に 多くの部分が割かれていました。
『天理教事典』(1977年版)に書かれていた 今回の「中紀大教会」の経済的困窮時代の史実も、
私にとって 非常に印象に残る内容でした。
当時 (明治20年代後半〜明治30年代) は 神殿建築の後始末に苦しみ、
また 布教費の調達も意の如くならず、中途にして布教から引揚げて帰る者もあり、
中紀支教会は 遂に 多額の負債を生ずるに至った。これの整理は容易でなく、部内教会は 非常な辛酸をなめた。
その間、数々のおさしづを伺い 心の治め方を図る一方、
負債整理のため、3ヵ年間は、(西 松太郎)会長はじめ役員一同も、
帽子を被らず、表付の下駄をはかず、時計を持たず、絹物一切を着用せず、禁酒禁煙を断行する旨の申し合わせをした。…(中略)…
教会当番は弁当持参であり、役員たちは 家財道具を持ち寄って 市をしたことも 再三に及んだ。病気になる者もあり、世間からはさげすまれて、
(『天理教事典』1977年版 P,515)
天理教の者といえば 信用がなく、
金銭は勿論、僅かの米さえ貸してくれる人がない という 悲惨な境遇が 長年にわたって続いた。
現代、天理教にご縁を頂いている者が たまに聞かされる話として、
“今のお道は本当に結構になったけど、昔の天理教の人は「屋敷を払うて田売り給え 天貧乏の命」と馬鹿にされて 苦労したんだよ”
という類の話があります。
現代の日本社会というのは、本当に 物質的には何不自由のない裕福な時代で、
私を含め 全ての現代人が、そのような話に 全くリアリティを感じられないというか、ピンとこない、
というのが 実際のところではないだろうか、と思います。
しかし、初期の天理教信仰者の先生方は、歴史の真実として、
「世間からはさげすまれて、天理教の者といえば 信用がなく、金銭は勿論、僅かの米さえ貸してくれる人がない という 悲惨な境遇が 長年にわたって続いた。」
という境遇の中を、実際に、通り抜かれたのであります。
この『天理教事典』「中紀大教会」解説文の中には書かれてありませんが、
きっとそれは、自らの「いんねんの自覚」を出発点として「教祖のひながた」を心の支えとして、
後世に生きるであろう者たちのたすかりを願って、
涙を流しながら 歯を食いしばって歩んだ 魂の道だったのに違いありません。
そして、その上に、今の私たちの結構があるわけです。
そのような 地の底を這うような 先人先生方のご苦労の上に 今の私たちの結構さがある ということ。
私たちは、今、そのことを「想像」することさえ 難しくなってきた時代に生きています。
なぜ 自分の家は天理教なんだ、という苦悩に覆われる機会が この先 増える一方であろうことが予想される時代に 私たちは 生きています。
であるからこそ、今の自分を自分たらしめている足場を見失ってしまわないためにも、
かつて 今の私たちの土台を築いて下さった先人先生方の 今回改めて学んだような「苦難」の道中というものに ことあるごと折に触れて 思いを馳せる機会を持ち続けていきたい、いかねばならない、
そのように 思うのでありました。
今回の書写学習を通して、
「先人ありて今の道」
というお言葉を、改めて強く肝に銘じたい、との思いに包まれた「さまよい人」なのでした。

その他にも、これまで知らなかった多くのことを知ることが出来て、とても勉強になりました。
有難いことでした。
「人に歴史あり」
組織にも歴史あり…
歴史を踏んで今がある――
だからこそ、
今を輝かせるためには
「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。
ということで――
今回は「中紀大教会」初期の歴史の勉強でした。
人生、死ぬまで勉強。
今後も、勉強し続けていきたいと思います。
ではでは、今回はこのへんで。
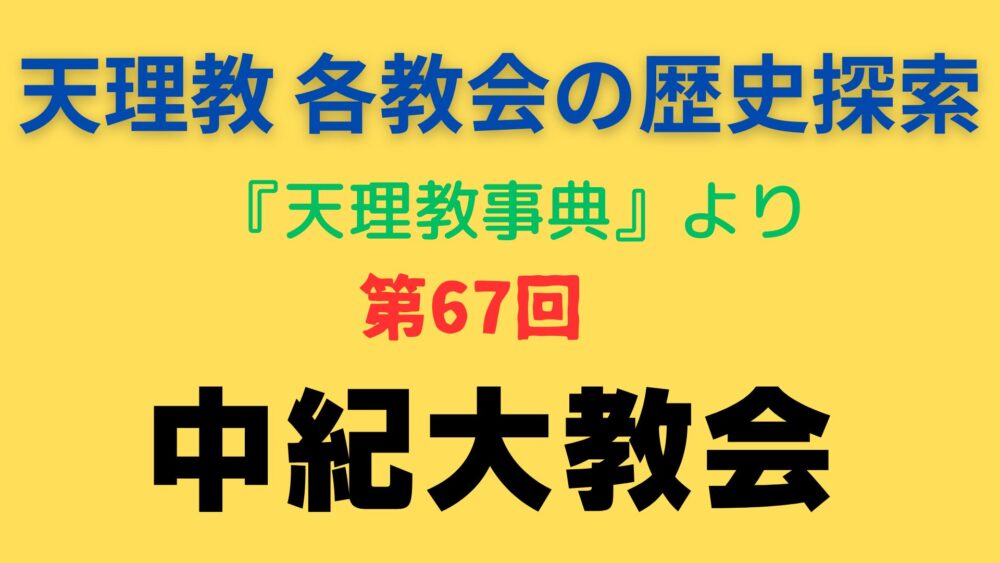

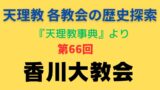
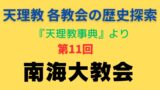
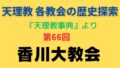
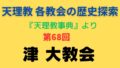
コメント