Dear everyone,
こちらは、
ふらふら彷徨う「さまよい人」による
『さまよいブログ』
= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。
今回も、
『天理教事典』(1977年版)に記載された
各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。
私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)
最新版👇
このシリーズを始めた理由については、
当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。
前回は、
教会番号56番「高岡大教会」の『天理教事典』記述を書写して
その歴史を勉強しました。
今回は、
教会番号57番「愛知大教会」について勉強します。
- 愛知大教会(あいち だいきょうかい)
- 愛知大教会の始まり(明治20年)
- 橋本伊平の心定め(明治20年)
- 橋本伊平のおたすけ活動(明治20年〜明治22年)
- 橋本伊平の名古屋布教(明治23年)
- 名古屋真明組の結成(明治23年)
- 愛知支教会の設置(明治24年)
- 拡大する教勢、湧き起こる教会事情(明治25年頃〜明治28年頃)
- 橋本伊平の2代会長就任前後(明治28年頃〜明治32年)
- 神殿建築(明治31年)
- 愛知支教会の道の広がり(明治33年頃〜明治38年頃)
- 愛知分教会へ改称(明治42年)
- 教会の移転(明治44年)
- 上級・山名大教会の教統問題(大正7年〜大正12年)
- 橋本伊平2代会長出直し〜諸井梅乃3代会長の就任(大正15年)
- 部内教会の動向(昭和5年頃〜昭和16年)
- 橋本兼正4代会長の就任(昭和10年)
- 愛知大教会への昇格(昭和15年)
- 太平洋戦争前後(昭和16年頃~昭和22年)
- 橋本義郎5代会長の就任~境内建物の移転建築(昭和43年~昭和48年頃)
- おわりに
愛知大教会(あいち だいきょうかい)

愛知大教会の始まり(明治20年)
愛知大教会の創始は――
(後に) 2代会長となった 橋本伊平が
明治20年(1887)1月、静岡県 周智郡森町村で 寿司屋をしている時、ノボセ眼(結膜炎か) となり、
後見役で親代りになっていた 岡野桂次郎に おたすけを懇願したところ、
「お前の様な悪道を通って来た者は、眼が悪くなるのも当然だ、今までの道すがらについて、よく胸に手を当てて思案して見るがよい」と諭された。(そのお諭しを受けて、橋本伊平が)
一心になっておわびをして (たすけを) 願ったところ、不思議な御守護を頂いた。――ここに始まる。
橋本伊平の心定め(明治20年)
(橋本伊平の後見役だった) 岡野桂次郎は、
すでに前年(明治19年)、孫の安産願から(天理教に)入信し(ており)、
後に、山名大教会部属・周智分教会の基を築いた人である。岡野桂次郎(初代会長・岡野勘蔵の父)から諭された (橋本)伊平は、
薄遇の運命から親戚姉妹に迷惑をかけたこと (あるいは) 役者時代の極道等、15歳以後 通って来た道すがらを、
天理の教えに照らして、さんげの角目を巻紙にしたため、岡野家の神棚に供えて、
再び 前車の轍は踏むまい と誓うと共に、
たすけて頂いたら 必ず 人様を手引きすることを誓った。
当時33歳である。この心定めは、生涯変わることはなかった。
橋本伊平のおたすけ活動(明治20年〜明治22年)
こうして入信した橋本伊平は、
岡野桂次郎夫婦と共に、
静岡県山名郡下貫名村にあった山名分教会へ、
峠を越えて 3里の道程を朝参りに通って、信心の道に心を磨いた。そのうち、明治22年5月中旬頃、
かつて(の)役者時代の師匠、片岡松童(坂入泰次郎)が、
名古屋区 城代町の佗住居で、病となり床に臥していると聞き、
(橋本伊平は) 松童の叔母に当たる 岡野いと (桂次郎の妻)と共に見舞い、
信仰をするように 勧めた。(橋本)伊平の心中は、 師匠が教えを聞き分け 救かって欲しい、という願で一心であった。
(橋本伊平が 名古屋区城代町の 片岡松童宅に) 2、3日滞在する間に すっかり御守護を頂き、(片岡)松童は 入信した。それ以後、(橋本伊平は) 時々 名古屋へ出かけたが、
その年(明治22年) 11月中旬頃のこと、
(片岡)松童の出入り商人が
「うちの親方が 中風で 10年余りも寝たきりだが、これでも 助かるだろうか」
といった。この親方とは、
芝居に使う 櫛やかんざし等の小道具を商う 銭屋(かざりや)の主人で、
柴田久兵衛 という人であった。この商人に連れられて 名古屋市南伊勢町130番戸(の) 柴田久兵衛宅へおもむいた橋本伊平は、
自分の入信から今日まで聞いた 月日親神、かしものかりものの理、八つのほこり等の教理を取り次いだ。
(そして) 茶碗に水を一杯汲み、月日親神に(向かって)、(橋本伊平が柴田久兵衛に)代って詫びをいって (その水を)飲ませた。この時、(柴田)久兵衛は、(橋本)伊平の話から(深い感銘を受け)
「よし、自分の余命と財を 人だすけの上に投げ出そう。それが 自分のせめてもの罪滅ぼしである」
と悟り、明治22年12月10日 入信した。
橋本伊平の名古屋布教(明治23年)
(橋本)伊平は、諸井国三郎 山名初代会長に、(柴田)久兵衛の入信を報告した。
(すると、諸井国三郎 山名初代会長から)
「それは 結構やったなあ。名古屋は将来性のある所である。道も世界に延びにゃならん。お前、(柴田)久兵衛宅を足場にして 名古屋布教をしてくれぬか。」
といわれた。明けて 明治23年1月15日、
橋本伊平は、寿司屋を止め、
森町の信者の人々に送られて、山名分教会の人となり、
(明治23年)1月21日、東海道線 袋井駅から 下り一番列車に乗り、名古屋布教に乗り出した。懸命の布教により、
早くも、その年(明治23年)のうちに 214戸の信者加入を見る等、主な先人が 陸続と入信した。その中の一人、市村末彦(小牧大教会初代会長) は、
明治23年4月5日の入信であるが
生まれつき「かいぐり」という不具者で、
あらゆる手だてをしたが よくならず、生涯不具かと悲嘆に暮れ(ながら)
親戚に当たる 石崎金太郎方で 銭屋職人をしていた。(そのような中)
橋本伊平から「人をたすけて、我身が助かる」と聞かされ、
(その教理は市村末彦の魂を揺さぶり、心を鷲づかみにした。)
(教理に感銘を受けた市村末彦は)
不自由な体を這うようにして 教えを説いて回った。
(そうしたところ) 21日目に、足の裏が上向いていたのが 鮮やかに元通りになり、生まれて初めて 下駄を縛って履いたという。(市村)末彦は その感激を生涯持ち続け、布教伝道の上に挺身した。
名古屋真明組の結成(明治23年)
その年(明治23年) 5月22日、
「名古屋真明組」を 柴田久兵衛宅に於いて結成し、
名古屋第一警察署へ届をした。講長は 橋本伊平、周旋方は 柴田久兵衛、(講員は) 小柴久七、竹内正常、柴田安次郎 外 13名であった。
しかるに、その年(明治23年) 11月、橋本伊平は、
山名分教会の命により、分教会に住み込むこととなり、山名へ引き揚げた。
(それで) そのあと(は)、山名の役員が 交替で出張してきた。
愛知支教会の設置(明治24年)
明治24年4月迄には、教勢は 益々伸展し、
愛知県内は勿論、岐阜県始め 近県に及んで、278戸の信者が加入し、教会設置の機運が高まって来た。明治24年4月9日、
はからずも、本席 始め 本部役員 6名の立ち寄りがあり、設置の視察という結果となった。明治24年(1891) 4月25日、
教第34号を以って 名古屋市 南伊勢町2丁目130番地、柴田久兵衛 持家にて、「愛知支教会」設置を許された。(愛知)支教会長は、
山名初代(諸井國三郎) 会長の指図により、
山名分教会役員・松井松太郎 (後年、清麿と改名) が任命された。しかし、(松井)松太郎は 山名分教会に詰めている役である上から、
山名初代(諸井國三郎) 会長は、
柴田久兵衛を副会長に、小柴久七 外 27名を 役職員に任命した。
拡大する教勢、湧き起こる教会事情(明治25年頃〜明治28年頃)
翌(明治)25年6月には、早くも 熱田、渥美、小牧 の 3部内教会の設置を始め、
(明治)26年に 一宮、
(明治)27年に 半田、
(明治)28年に 武儀、瀬戸、常滑、阿久比、八幡、野間、
(明治)30年に 菅原、幅下、篠島、東春、
(明治)33年に 土岐、
(明治)34年に 平針、中京、
というように、
部内教会の設置が 相次いでいる。しかるに、明治26年から起こった教会事情は、
3度も「おさしづ」 を伺う程、容易に治まらない教会事情となった。(松井松太郎) 初代会長は、
明治28年7月13日、その職を辞し、
更に 混乱する結果となった。
橋本伊平の2代会長就任前後(明治28年頃〜明治32年)
山名分教会では、
事情に対処するため、役員を交互に派遣し、
遂には、
山名初代(諸井國三郎) 会長自ら「愛知支教会長」を 兼務したこともあった。しかし、明治32年2月2日に伺ったおさしづに、
「土地処に伏せ込んだ理を立てよ」とお示し頂くに及び、
草分の祖(おや)である「橋本伊平」をして 後任会長とすることを
山名分教会で協議(の上、決定した)。その年(明治32年) 8月22日、
橋本伊平は 愛知支教会長 事務扱 として来会し、諸準備の上、
翌(明治)33年1月18日、(橋本伊平が)2代会長の許しを得た。(その後) 徐々に教会事情も治まってゆき、
「愛知(支教会)」盤石の礎が 築かれた。
神殿建築(明治31年)
それより少し前、明治31年、
(愛知支教会は) 柴田久兵衛より土地が献納されたのを機に 神殿建築の工を起こした。その年(明治31年) 4月15日、普請の許しを得、
(明治31年) 7月31日 鎮座祭、8月1日 開筵式を執行した。
愛知支教会の道の広がり(明治33年頃〜明治38年頃)
明治33年から34年に亘り、
小牧、幅下、土岐の各部内教会からは、伝手を頼って 北海道へ布教に出る者が現われ、
後年になり、陸続と教会設置となった。また明治38年頃、
半田の教会関係からは、関東に布教にゆき、同じく 各地に教会設置となった。
愛知分教会へ改称(明治42年)
明治42年(1909)2月25日、
天理教の一派独立に伴い「愛知分教会」と改称され、
4月23日その奉告祭を執行した。
教会の移転(明治44年)
明治31年5月17日の副会長・柴田久兵衛の出直しを汐に、
先に (柴田久兵衛より)献納された土地につき (柴田久兵衛の) 親戚から異議が出(てい)た。(以来、その問題が潜在的にくすぶっていたわけだが)
(ついに) 明治44年3月6日、
名古屋市東区 添地町9番地の1に 移転の許しを得、
その年(明治44年) 8月28日 鎮座祭、29日 奉告祭を執行した(のであった)。
上級・山名大教会の教統問題(大正7年〜大正12年)
大正7年に 諸井国三郎 山名初代会長が出直した後、
山名大教会では 教統問題が起こった。(その後、紆余曲折を経て)
大正12年、従来の山名大教会の教勢を二つに分割して、
新たに名古屋市内に大教会を設けることとなった。その年(大正12年) 11月23日、(山名分教会を分割した) 名京大教会が設立されると同時に、
愛知(分教会) は、部内教会 50ヵ所と共に、名京(大教会) 所属となった。(愛知分教会) 部内教会数は、更に 教祖40年祭の倍加提唱によって、
大正14年末には、126ヵ所となった。
橋本伊平2代会長出直し〜諸井梅乃3代会長の就任(大正15年)
2代会長の橋本伊平は、
大正13年頃から 健康勝れず 名京大教会 役員宅において静養していたが、
大正15年(1926) 7月16日、齢73歳で 出直した。(橋本伊平2代会長出直しとなった 愛知分教会は)
時の名古屋教務支庁長・飯降政甚の声で、
名京大教会長夫人・諸井梅乃を3代会長に迎え(ることとなった。)
(そして)
大正15年9月15日 許しを得、10月16日 その(3代会長就任)奉告祭を 執行した。ただし、諸井忠彦 名京大教会長より
(教会の) 実務担当は
理事である小牧支教会長の市村末彦を以って 会長代理とすることを任命された。(それにより、市村末彦が)
草分の祖なきあと(の愛知分教会 実務) を統べることとなった。
部内教会の動向(昭和5年頃〜昭和16年)
昭和5年(1930)、幅下支教会の部内である 小島久満吉は、
アメリカ合衆国ポートランド市にて、先に渡米していた土井庄之助と共に布教し、サクラメント教会(現、名京部属)をおこした。昭和9年5月25日、小牧支教会は 分教会に昇格し、名京大教会の直轄となった。
後に昭和16年5月、(小牧)大教会に陞級した。
橋本兼正4代会長の就任(昭和10年)
昭和10年1月25日、諸井梅乃(3代会長) の辞任により、
橋本兼正が4代会長の許しを得た。
(そして)
(昭和10年) 3月20日、その(4代会長就任)奉告祭を 執行した。
愛知大教会への昇格(昭和15年)
昭和15年3月9日、
時局刷新に伴い、天理教教規の改正が行われ、
第1次指名により、(愛知分教会は) 大教会昇格の許し(教昇第559号)を得た。
(そして)、翌(昭和)16年3月8日 昇格、(愛知大教会昇格)奉告祭を執行した。この時の部内教会数は93ヵ所である。
太平洋戦争前後(昭和16年頃~昭和22年)
ところが
昭和16年に起こった太平洋戦争のため
昭和20年3月19日、有形のもの すべてを焼失。(愛知大教会は) 部内の 名城分教会へ避難した後、
名古屋市東区 板屋町55番地の借家に 仮移転して 終戦を迎えた。(すべてを失って終戦を迎えた 愛知大教会だったが)
その年(昭和20年) 11月、(橋本兼正)会長の病気から 復興建築の心定めをするに至った。翌(昭和)21年8月27日、名古屋市瑞穂区 初日町1丁目26番地に 移転建築の許しを得、その工を起こした。
(そして) 昭和22年12月2日 鎮座祭、(12月)3日 復興奉告祭を執行した。昭和28年3月27日、信徒詰所の建築の工 成って 開設披露を行い、教祖70年祭を迎えた。
昭和の初め頃から ブラジル国に移住して 布教の傍ら 洗濯屋をしていた岐支教会の信者である 岩島義一が、
昭和31年5月12日、ブラジル国サンパウロ市に エステレーラ教会を設置した。
橋本義郎5代会長の就任~境内建物の移転建築(昭和43年~昭和48年頃)
昭和43年9月27日、
4代会長・橋本兼正が辞任して、橋本義郎が5代会長の許しを得た。
(そして)
その年(昭和43年) 12月22日、(5代会長) 就任奉告祭を執行した。昭和44年11月、境内建物が 名古屋市 都市計画街路の計画線上に在り、建物の建築が不可能との事由から、
翌(昭和)45年5月26日、名古屋市緑区 鳴海町大字神之倉3番地の182に 移転建築の許しを得て 移転に着工(した)。続いて 昭和46年 9月26日(に) 神殿建築の許しを得(て)
(昭和46年) 10月23日 起工式、
翌(昭和)47年 5月23日 上棟式。
昭和48年 11月 竣工、
(昭和48年) 11月6日鎮座祭、(11月)7日 落成奉告祭を執行。そして今日に至っている。
【出版物】
『愛知大教会史』第1巻 (425頁),
『神殿ふしん記録』(10頁),
『あいち』(月刊,休刊中)〔現住所〕〒458-0808 愛知県名古屋市緑区東神の倉 2丁目2401
(『天理教事典』1977年版 P,4〜6)
〔電話〕 052-876-0487
おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。
57回目の今回は、
「愛知大教会」初期の歴史を勉強しました。
当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。
とても古い資料なので、
記載内容も 1970年代以前までとなっており、
かなり昔の歴史にとどまっています…
しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。
十分 私のニーズは満たされるので、
そのまま書写し続けております (^_-)-☆

『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) という本の中にも大教会に関する記述がありましたので、自己覚え書きとして書写します。
橋本伊平(愛知ニ代) は 結膜炎より 岡野桂次郎 (山名系周智初代の父) にたすけられた。
伊平は 若いころ役者を志望し 片岡松童の門に入った。
桂次郎の妻 いと は 松童の叔母にあたる。
明治二十年正月、伊平は 桂次郎あてに、巻紙三尋に及ぶ誓紙をしたため、信仰者に生まれかわった。二十二年、師匠・松童が病床にあると聞き、いと と伊平は 松童宅を見舞った。
『道〜天理教伝道史をあるく』(道友社編) P,91〜92
そこの出入り商人が「中風のうちの親方もたすけてほしい」と申し出た。
親方とは錺職問屋の柴田久兵衛で、ここから翌年までに二百戸余の信者ができた。
久兵衛の下請職人や出入り商人が多かった。
南伊勢町の久兵衛宅に 講社事務所 開設。
愛知大教会は、名京大教会から分かれた大教会ですね。
名京大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。
私は、これまで50数回にわたって『天理教事典』1977年版に記載された「天理教大教会」初期歴史の書き写しを行ってきました。
最初は、自己学習ブログのネタに行き詰まって、特に深い考えもなく軽い気持ちで始めたのですが、
回数を重ねるにつれて、天理教大教会の歴史って(特に教会制度創設初期は)「もつれ合う人間関係が渦巻く伏魔殿」 のような側面が 多々あるなぁ…
という思いを強くしています。
今回勉強した「愛知大教会」が特にそうだというわけではありませんが、
「山名ー名京ー愛知」の歴史勉強を通して(これまで全くその歴史を知らなかったこともあって)、天理教教会史には「人間ドラマ」というか人間的な要素がぎっしり詰め込まれている、ということを、
改めて、しみじみと感じさせられました。
『天理教事典』というのは公的な書籍ですので、おまけに私が参照しているのは1977年版という極めて古いものということもあり、内部の細かい事情や背景については書かれていません。
なのでわからないことが多いわけですが、
今回もまた、わからない点が多々ありました。
まず、
名古屋で結成された「名古屋真明組」が【教会】(=愛知支教会) になる際、
愛知支教会の初代会長に、山名分教会役員の松井松太郎先生が就任しておられる点。
なぜ、橋本伊平先生が初代会長でないのか?
(おまけに、副会長は柴田久兵衛先生で、愛知支教会創立時の執行部の中に、母体となる「名古屋真明組」講長だった橋本伊平先生の名前がどこにもない…)
『天理教事典』には 史実が淡々と書いてあるだけでしたので、その理由が分かりませんでした。
橋本伊平先生は、
明治23年5月に「名古屋真明組」結成した際 その講長に就任しながらも
その半年後の同年11月には 山名分教会の命により分教会へ住み込むこととなった、そして、その後は 山名の役員が交替で出張してつとめた――
そのように『天理教事典』には書かれてありました。
母体となる講の講長ではあっても、新たに起ち上げる教会の【会長】に就任するには「不適切な何か」があったのかな…と推察されます。
そして、『天理教事典』には、
明治24年「愛知支教会」設立し その2年後の明治26年から 教会事情が発生。
その2年後の明治28年には 松井松太郎初代会長が 辞職。
その後、諸井國三郎 山名初代が 愛知会長を兼務するなどの紆余曲折を経て、最終的に「名古屋真明組」講長だった「橋本伊平」先生が2代目として会長に就任した。
とも書かれてありました。
これもまた 史実が淡々と書いてあるだけでしたので、
部外者には その理由・背景が分からない点です。
失礼を承知の上で、そのあたりの背景を ちょっと想像してみたいと思います。
愛知大教会の元一日を築いた「橋本伊平」先生は、
『天理教事典』の中には、
入信前「薄遇の運命から親戚姉妹に迷惑をかけ、15歳以後 役者時代には極道等の道を通って来た…」と書かれてありました。
そういった経歴から(もしかしたら言動も含めて)、当時の関係者の方々の目には 橋本伊平先生は「教会長」に相応しくない、と映ったのかもしれません。
それで、関係者一同「人間」の頭で思案して、相応しいと思われる方々に役割を振り分けて対応していった…
しかし、あれこれ事情が重なり 収まらない。
それで、おさしづを伺った(明治32年2月2日)。
そうしたところ、
「土地処に伏せ込んだ理を立てよ」とのお言葉があった。
それを受け 一同は、
人間の目には相応しくないように映るかもしれないけれども、
神様が会長として望んでおられるのは 愛知における草分の祖(おや)である 橋本伊平先生である、と悟った。
それで、橋本伊平先生が「愛知支教会」の2代会長に就任されることになった。
その後、「愛知支教会」は、橋本伊平先生を中心として結束し、
上級・山名と名京の分裂といった大きな問題に直面しながらも、それを乗り越え、今日のような隆盛を誇る姿となった――
…以上は、ブログ主による、完全に 独りよがりな「妄想」です (^^;)
妄想かもしれない史実ではありますが、
以上のような
『天理教事典』の記述を基にして私の中で生まれた(妄想かもしれない)ストーリーを通して、
- 人間の目には相応しくないように映っても、因縁に基づくその場にふさわしい魂というものが存在する
- 人間の頭で考え出したことが最善だと思い上がってはいけない
- 常に、人間の思案と神様の思いにはズレがあるかもしれない という謙虚さを忘れてはいけない――
私は、そのような学びを引き出しました。

以上、『天理教事典』「愛知大教会」解説文の書き写しを通して頭に浮かんだことを書き連ねさせて頂きました。
これらはすべて、『天理教事典』の記述のみを参考資料とした思案ですので、
史実の背景を含めて、もしかしたら、全くの見当違い(!)の可能性が 大いにあります (>_<)
もしも そうだったとしたら、非常に失礼な話なわけで、関係者の皆様に深くお詫びしなければなりません。
想像でこのようなことを書いて公開するのはいかがなものか という気もします。
しかし、私の意図するところは、決してどなたかを批判したり、興味本位で古い史実をスキャンダルのように取り上げることではありません。
『天理教事典』の記述を参考にし、お道の初期の歴史を学ぶことで、
その中から 現代にも通じる教訓を見出し、自分自身の歩みに少しでも活かしていきたい――
この記事は、そのような純粋な動機に基づいて執筆したものです。
もし 私の認識に誤りがあり、不快に感じられた方がいらっしゃいましたら、何卒 ご容赦くださいますよう お願い申し上げる次第です。

今回は、『天理教事典』解説文の内容から、ちょっと想像を飛躍させ過ぎたかもしれません (-_-;)
ご訪問して下さった方の 上手な悟りに甘えさせて下さい (^^)
その他の部分でも、これまで知らなかった多くの尊い話を知ることが出来て、とても勉強になりました。有難いことでした。
「人に歴史あり」
組織にも歴史あり…
歴史を踏んで今がある――
だからこそ、
今を輝かせるためには
「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。
ということで――
今回は「愛知大教会」初期の歴史の勉強でした。
人生、死ぬまで勉強。
今後も、勉強し続けていきたいと思います。
ではでは、今回はこのへんで。
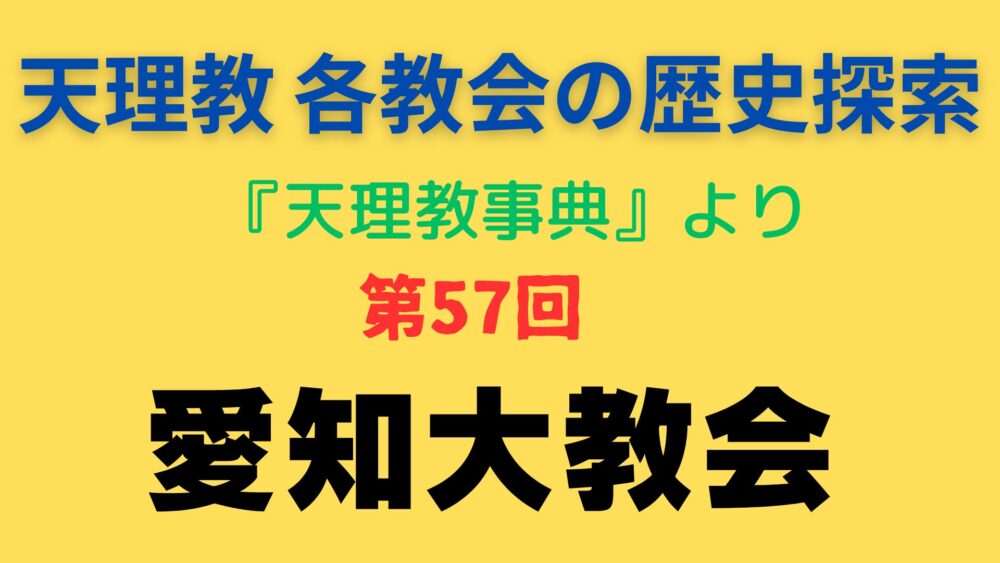

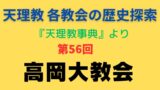
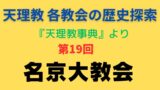
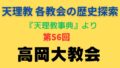
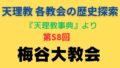
コメント