Dear everyone,
こちらは、
ふらふら彷徨う「さまよい人」による
『さまよいブログ』
= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。
今回も、
『天理教事典』(1977年版)に記載された
各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。
私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)
最新版👇
このシリーズを始めた理由については、
当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。
前回は、
教会番号44番「笠岡大教会」の『天理教事典』記述を書写して
その歴史を勉強しました。
今回は、
教会番号45番「西宮大教会」について勉強します。
- 西宮大教会(にしのみや だいきょうかい)
- 秋岡夫妻の入信(明治19年)
- 初代会長・秋岡亀治郎(明治19年)
- 真明組 西宮講社の結成(明治19年)
- 西宮講社の道の広がり(明治21年〜明治23年)
- 西宮支教会の設置(明治24年)
- 神殿 及び 付属建物の建築と 部内教会の新設(明治24年頃〜明治26年)
- 秋吉末吉2代会長の就任(明治40年)
- 西宮分教会へ改称、そして道の広がり(明治42年〜昭和2年頃)
- 秋吉弥束3代会長の就任(昭和9年)
- 中教会から西宮大教会への昇格前後(昭和14年〜昭和17年)
- 太平洋戦争空襲被害からの仮神殿建設(昭和20年頃〜昭和21年)
- 秋吉寿美江4代会長の就任(昭和22年)
- 信者詰所の開設〜新神殿ふしん(昭和24年〜昭和28年頃)
- 秋吉正史5代会長の就任〜その後(昭和35年〜昭和45年頃)
- おわりに
西宮大教会(にしのみや だいきょうかい)

秋岡夫妻の入信(明治19年)
西宮大教会の創立は、
明治19年(1886) 1月、
秋岡亀治郎、とみ夫妻の天理教入信にはじまる。同(秋岡)夫妻の長女・しづ (当時11歳) が 黒疱瘡に冒され、
生命旦夕に迫ったとき、
大阪真明組(現 芦津大教会)の 秋岡はなから
天理教の教えを伝えられた。(秋岡)しづは 奇蹟的な守護によって救かり、
(秋岡)夫妻の信仰がはじまっている。
初代会長・秋岡亀治郎(明治19年)
秋岡亀治郎は、
天保8年(1837) 12月15日、
大阪 高津で紙漉業を営んでいた秋岡重兵衛、ハマ夫妻の長男として出生した。幼少の頃から 豪放な性格だったという。
14歳にして両親の許を離れ、
明治維新の動乱の中で 職業を転々と変え 辛酸をなめた。明治6年頃、
兵庫県 武庫郡 西宮町内浜久保町200番屋敷で 紙漉業をはじめ、
定住するようになった。
真明組 西宮講社の結成(明治19年)
亀治郎夫婦が信仰しはじめたころ、
全国的にコレラが流行していた。兵庫県下でも 5,425名が死亡し、
罹病者の死亡率 90%だったという。そうした中で、
秋岡しづの奇蹟的な守護を伝えきいた人々は、
次々と 秋岡家を訪れて たすけを願った。こうして 入信者が相次ぎ、
同(明治)19年 11月には
「真明組 西宮講社」を結成するにいたった。秋岡亀治郎 を講元とし、
広田万蔵 を講脇として、
西宮町浜東町3丁目に 開設された。
西宮講社の道の広がり(明治21年〜明治23年)
このときから、
(秋岡)亀治郎は 布教に専従するようになった。明治21年 1月3日、
(秋岡)亀治郎は「おさづけの理」を拝戴し、
さらに 人を救けることに 専心 尽くすこととなった。教勢の伸展により、
明治21年 11月、
浜東町3丁目320番屋敷へ 講社を移転した。翌(明治)22年には、
西宮周辺、武庫郡、川辺郡、大阪府豊能郡、京都府福知山に、
また、
同(明治)23年には、
香川県伊吹島から 豊浜町、観音寺の方面に
講社が結成されていった。
西宮支教会の設置(明治24年)
西宮講社では「支教会」設置の議が起こり、
明治24年 11月19日、
西宮町内浜東3丁目301番屋敷に 設置することを願い出た。(明治24年) 同月(11月)22日、
おぢば から設置の許しを得、
翌 12月22日には 地方庁の認可も得ている。
(=「西宮支教会」の設置)初代会長に(は) 秋岡亀治郎が就任した。
神殿 及び 付属建物の建築と 部内教会の新設(明治24年頃〜明治26年)
その後、教会移転が進められ、
西宮町字北横道の400坪の土地に
神殿(52坪余り) 及び 付属建物(63坪余り)を新築し、
明治26年 4月5日、
落成奉告祭を執行した。一方、布教活動も進められ、
(明治)24年には 福知山、
(明治)26年には 川辺、武庫、南丹
の各教会が 設置された。
秋吉末吉2代会長の就任(明治40年)
明治40年(1907) 4月19日、
2代会長に 秋岡末吉が就任した。秋岡末吉 (旧姓 山脇) は、
明治33年 2月21日、
秋岡しづと結婚し、教務に携わっていたものである。この頃までに、
柏原、遠阪、上竹田、三丹、和田浜、小浜野、摂豊、多田、東地
の各教会の設置を見た。
西宮分教会へ改称、そして道の広がり(明治42年〜昭和2年頃)
天理教の一派独立により、
明治42年 1月10日、
芦津大教会 西宮分教会と改称され、
この頃には 韓国へも布教が進められて、
ソウルの竜山に教会が設置された。国内では、
中筋、大野原、宮都農
の教会が 設置されている。大正年間には、
教祖40年祭活動として 教勢倍加運動 が進められたこともあり、
43ヵ所の教会が新設された。その後
昭和2年(1927)には 9ヵ所、
同(昭和)3年には 5ヵ所、
同(昭和)4年には 2ヵ所
の教会が設置された。
秋吉弥束3代会長の就任(昭和9年)
(秋岡末吉)2代会長の辞任により
昭和9年 12月24日、
3代会長に 秋岡弥束 が就任した。秋岡弥束 (旧姓 千田) は、
大正11年 2月、
秋岡家の養子としてむかえられ、
昭和5年 2月23日、
中内寿美江 と結婚している。
中教会から西宮大教会への昇格前後(昭和14年〜昭和17年)
昭和14年 5月26日、
芦津大教会から分離昇格して「西宮中教会」となった。これに伴い、
同年(昭和14年) 9月7日、
現 天理市三島に 信者詰所を開設した。さらに、
翌(昭和)15年(1940) 2月10日、
中教会から「大教会」へ昇格した。翌(昭和)16年 5月6日、
2代真柱を迎えて(大教会)昇格奉告祭を執行した。同(昭和)17年、
網大、網花、東蕨、明園
の4教会が 西宮の所属となる。
太平洋戦争空襲被害からの仮神殿建設(昭和20年頃〜昭和21年)
その頃、
日本は 第2次世界大戦の最中にあった。敗戦を目前にした 昭和20年 8月6日、
空襲を受けて、西宮大教会は 全焼した。親神様、教祖の「お目標」は、
幸いにも、甲東分教会に 仮遷座することができた。翌(昭和)21年 6月1日、
仮神殿の普請の許しを得、さっそく着工し完成した。同年(昭和21年) 10月23日、
新築なった仮神殿に2代真柱をはじめ多くの来賓を迎え、仮神殿落成奉告祭を執行した。
秋吉寿美江4代会長の就任(昭和22年)
こうした中、
翌(昭和)22年 1月29日、
3代会長 秋岡弥束が 出直した。これを機に、
戦争のため停滞していた布教活動を進展することになった。同年(昭和22年) 3月25日、
4代会長に 秋岡寿美江(3代会長夫人) が就任し、
同年(昭和22年) 10月23日、
4代会長 就任奉告祭を執行した。
信者詰所の開設〜新神殿ふしん(昭和24年〜昭和28年頃)
(秋岡寿美江)4代会長のもとで、
昭和24年には 現 天理市川原城に 西宮信者修行所を開設。さらに、
翌(昭和)25年 12月26日、
神殿普請の許しを得て着工。同(昭和)28年に完成して、
12月6日に鎮座祭を、
(12月)7日に 新神殿落成奉告祭を執行した。また、
(秋岡弥束)3代会長の出直を動機として進められた布教活動も実り、
7年間に 15ヵ所の教会が設立された。
秋吉正史5代会長の就任〜その後(昭和35年〜昭和45年頃)
昭和35年 3月26日、
5代会長に 秋岡正史 が就任した。(昭和35年) 5月24日、
2代真柱を迎えて 就任奉告祭を執行。秋岡正史(旧姓橋本)は、
同(昭和)34年 3月、
敷島部属 名草分教会から迎えられていたのである。昭和40年 11月、
山本清子と結婚した。(秋岡正史)5代会長のもとで、
現在(『天理教事典』1977年版 出版当時)までに
5ヵ所の教会の設立をみている。なお 昭和45年には
客殿などの付属建物を増改築した。また
現在(『天理教事典』1977年版 出版当時)、
第61母屋として西宮詰所を建築中である。〔現住所〕〒662-0911 兵庫県西宮市池田町1番19号
〔電話〕0798-34-0393(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)
(『天理教事典』1977年版 P,660〜661)
おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。
45回目の今回は、
「西宮大教会」初期の歴史を勉強しました。
当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。
とても古い資料なので、
記載内容も 1970年代以前までとなっており、
かなり昔の歴史にとどまっています…
しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。
十分 私のニーズは満たされるので、
そのまま書写し続けております (^_-)-☆
『道~天理教伝道史を歩く』(道友社編) という本の中にも
西宮大教会初代・秋岡亀治郎先生の入信に関する記述が ほんの少しだけありましたので、
『天理教事典』解説文と重なりますけれども 書写致します。
西宮初代の秋岡亀治郎は
兵庫県西宮町内浜で 紙漉業を営んでいた。大阪の本家が 芦津真明講に属していた関係で、明治十九年、長女しづが黒疱瘡にかかった時、井筒梅治郎のおたすけを受けた。
奇跡的な守護を知った人々が 秋岡家の門をたたいた。
『道~天理教伝道史を歩く』(道友社編)P,82

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】45回目の当記事では
『天理教事典』の中の「西宮大教会」についての記述を書き写して勉強しました。
西宮大教会は、芦津大教会から分かれた大教会ですね。
芦津大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。
西宮大教会は、秋岡亀治郎・とみご夫妻のご息女(しづ)が黒疱瘡になって生命も危ない程の状態のところを、大阪真明組の秋岡はな先生を通して 奇跡的なご守護を頂いたところから始まるのですね。
『道~天理教伝道史を歩く』(道友社編)の中に、「大阪の本家が芦津真明講に属していた関係で…」と書いてありましたので、
秋岡はな先生というのが、大阪の本家の方だったのでありましょう。
初代の秋岡亀治郎先生は、幼少の頃から豪放な性格で、
14歳で親元を離れ職業を転々と変えられ、そして36歳頃から西宮で紙漉業を始め、そこで定住された。
そのような中、
11歳に成長した愛娘が 黒疱瘡に罹患してしまい、危篤状態に…
秋岡亀治郎初代会長は豪快な先生だったとの事ですので、
可愛い娘が明日をも知れぬ状態となってしまった際の 世を呪う嘆きの大きさは、並々ならぬものだったのではないか、と想像致します。
そうした絶望的な状態の中で、本家の秋岡はな先生からこの道へ導かれ、
そして、芦津の井筒梅治郎先生のおたすけにより、奇跡的な回復のご守護を頂かれた。
その喜びはどれほどのものだったでしょうか。
秋岡亀治郎先生の入信のあたりを書き写しながら、
嶽東大教会の勉強をした際に学んだことを思い出しました。
嶽東大教会の初代会長である鈴木半次郎先生も、
西宮の秋岡亀治郎先生同様、任俠心あふれる豪快な性格であられた。
ところが、鈴木半次郎先生の最愛の一人息子が、恐風の虫という引きつけの激しい病気に罹り、骨と皮ばかりに痩せ細り病状が悪化する一方となった。
なす術なく絶望的になっていたところ、水口の井上佐市先生よりおたすけを頂き、
その感激から文字通り生まれ変わり、たすけ一条の道へ進まれた。
そこから不思議なたすけが相次ぎ、教えが爆発的に広がり、
それが、今の壮大な「嶽東」の道へつながっている。
西宮の秋岡亀治郎先生も、
愛娘が命も危ないという状態から、井筒梅治郎先生のおたすけにより 奇跡的な回復のご守護を頂いた。
鈴木半次郎先生同様、秋岡亀治郎先生も、
子供の身上を通して 文字通り 生まれ変わられたのに違いありません。
嶽東の鈴木半次郎先生や西宮の秋岡亀治郎先生のように、
もともと豪快な先生は、一旦心を定めると、その勢いは凄まじい…!!
その勢いが、西宮大教会という見事な姿として結実し 今に至っている、
というわけなのですね。
明治19年1月におたすけを頂かれて、同じ年の11月には講社を結ぶほどに入信者が集まっておられるその素早さは、
秋岡亀治郎先生の勢いが如何に強いものだったのか、
ということを示しているような気がします。
そしてそれは、すなわち、
たすけられた感激がいかに大きいものだったかを示している、
とも言えるのではないでしょうか。
何事においても、折につけ事に触れて「原点」を思い返す、というのは大切ですね。
「原点」における感情や状況を風化させないため、
そして 今ある姿の「意味」を肝に銘じるために。
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】の回数を重ねて、
今回も、また改めて、その思いを強くしました。

また、今回の書き写しで、
多くの古い「大教会」がそうだったように、
「西宮大教会」でも、
太平洋戦争で激しい戦災を受けた歴史があることを知りました。
わけても、
敗戦目前の 昭和20年8月6日に 空襲を受けて教会が全焼してしまった
という事実には、胸が痛みます。
昭和20年 8月6日といえば、終戦の約1週間前ではないですか!
西宮大教会の皆様は、
文字通り、焼け野原の中で終戦を迎えられたのですね。
あと1週間持ちこたえてくれていたら、戦争が終わったのに…
西宮大教会の皆様は、どのような思いで 終戦の玉音放送を聞かれたのでしょうか。
茫然自失という感じだったのではないか、と想像します。
これまでの【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】で、
どの大教会も、多かれ少なかれ太平洋戦争の被害を受けられた歴史を学んできましたが、
西宮大教会も、大きな被害を受けられたのですね。
教会が全焼した1週間後に終戦となり、茫然自失となる程に。
しかし、西宮大教会の皆様は、そうした絶望的な状況から、
一同で力を合わせ 這い上がり、雄大な姿で今に至られています。
これまでの勉強のたびに、毎回最後に同じような感想を書き加えてきましたが、
今回もまた、
これまでの歴史を知ることで、今の勇姿により重みを感じられるようになった、
ということを 最後に書き加えたいと思います。

当記事では
『天理教事典』の中の「西宮大教会」についての記述を書き写したわけですが、
今回もまた、知らないことばかりでした。
書き写しを通して いろいろと知ることができて、とても勉強になりました。
「人に歴史あり」
組織にも歴史あり…
歴史を踏んで今がある――
だからこそ、
今を輝かせるためには
「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。
ということで――
今回は「西宮大教会」初期の歴史の勉強でした。
人生、死ぬまで勉強。
今後も、勉強し続けていきたいと思います。
ではでは、今回はこのへんで。

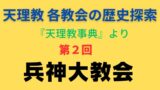
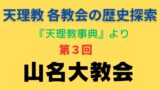
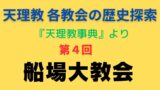
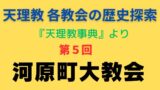
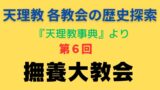
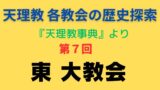
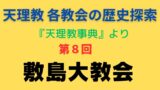
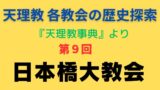
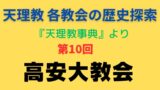
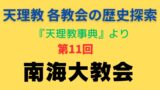
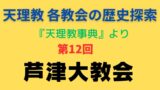
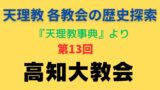
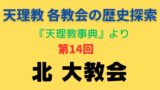
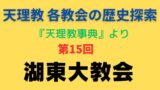
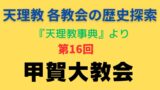
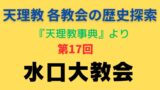
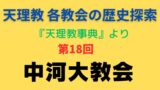
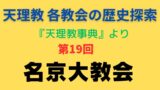
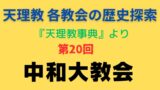
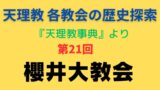
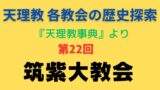
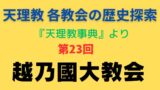
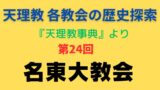
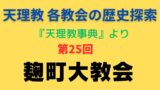
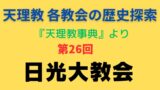
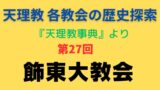
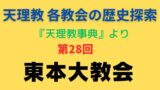
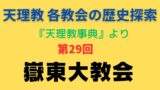
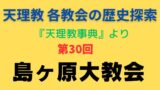
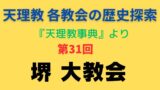
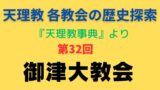

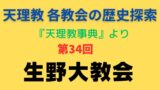
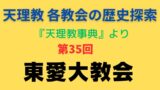
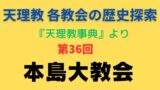
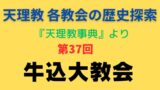
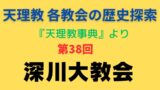
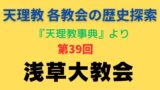
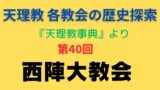
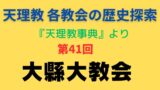

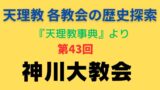
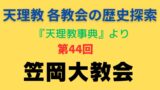
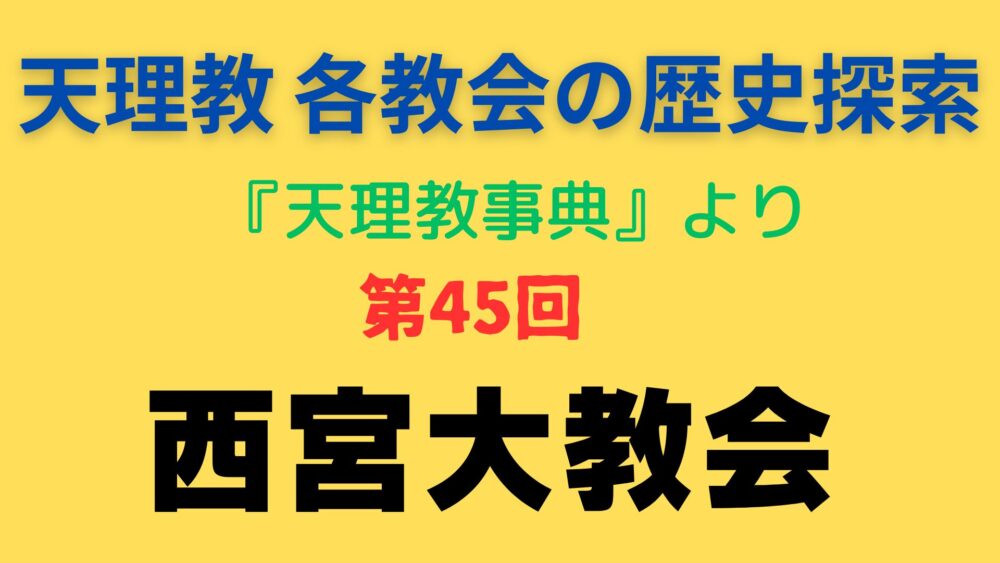
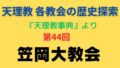
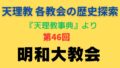
コメント