Dear everyone,
こちらは、
ふらふら彷徨う「さまよい人」による
『さまよいブログ』
= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。
本年3月から
『天理教事典』(1977年版)に記載された
各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】を続けています。
私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)
最新版👇
毎回記述の繰り返しになりますが、
当シリーズの意図は、
天理教 教祖百四十年祭へ向かう今の旬に、
これまで自分とはご縁がなかった天理教の各教会の歴史を
多少なりとも知ることを目指す、
というものであります。
そのための教材として、
たまたま自教会にあった『天理教事典』(1977年版)を活用させてもらっています。
何分 古い教材であるため、
当然、記述内容は とても古いです。
そして、
とりあえず、無条件に「原文」を書き写していますので、
もしかすると、
たまたまこの記事を目にした 関係者の方々にとっては、
この記述内容は事実と異なる! (~_~;) …
という部分があるかもしれません。
ですが、
当ブログは、自己学習の目的で運営しているもので、
記事作成にあたっては、
何らかの主義主張を行う意図はありません。
すなわち、
当シリーズ 全ての記事は、
「知る」ということだけを目的として、
ひたすら教材である『天理教事典』(1977年版)の記述内容を
淡々と書き写したものに過ぎない
というわけです。
よって、
記事の記述内容の真偽というか 正確性というところまでは
全く検証できていないということを、
お断りしておきたい と思います。
本文に出てくる史実に関係される方の中には、
もしかしたら、記述内容にご不満を感じられる方があるかもしれませんが、
どうか、大らかな心で受けとめて頂きますよう
お願い申し上げる次第です。m(__)m
前回は、
教会番号8番「敷島大教会」の『天理教事典』記述を書写して、
その歴史を勉強しました。
今回は、
教会番号9番「日本橋大教会」について勉強したいと思います。
日本橋大教会 (にほんばし だいきょうかい)

明治19年〜明治27年 (中台勘蔵 初代会長)
日本橋大教会の設立は、
明治19年(1886)11月、
中台勘蔵が 天理教へ入信したことにはじまる。勘蔵が 重症神経痛、慢性胃腸病で悩んでいたところ、
上原佐助(後に東大教会初代会長となる) に救けられたものである。中台勘蔵 (幼名は 国太郎)は、
天保11年(1840) 11月15日、
江戸日本橋に生まれた。明治4年に 父が出直し、
「勘蔵」を襲名して
家業の魚問屋 木村屋を継いだ。入信してまもなく、
明治20年 1月に
家業を 嗣子 平治郎に任せ、
勘蔵夫婦は 布教に専念するようになった。同年(明治20年) 8月、
柴田吉之助らと相談の上、
東京真明組 日京講社を結成し、
(中台) 勘蔵は 講脇兼会計となった。翌21年 8月3日に「おさづけの理」を拝戴してからは
いっそう 布教に励むようになった。明治22年(1889) 8月1日、
日京講社は 分割されて
日本橋講社と 京橋講社になった。(中台) 勘蔵は 日本橋講社の 講元となる。
そして、同年(明治22年) 12月28日、
この講社は 東分教会部属 日本橋支教会となり、
(中台) 勘蔵は 初代会長に就任した。初代会長となった(中台) 勘蔵は、
同(明治) 23年に 同望会(青年会の前身) を組織して 青年布教師の育成に尽力した。
翌(明治) 24年には 婦人会も組織している。こうして布教活動が推進され、
(明治) 24年10月には 講社1,120戸の結成をみている。(明治) 25年には 2カ所、
(明治) 26年には 4カ所、
(明治) 27年にも 4カ所の
部内教会が設置された。なお、明治27年 2月17日、
東分教会部内であった 日本橋支教会は分離して
教会本部直属の 日本橋分教会となった。同年(明治27年) 9月26日、
(中台勘蔵) 初代会長は 享年55歳で 出直した。
明治27年〜明治32年 (中台平治郎 2代会長)
明治27年(1894) 10月21日、
中台平治郎が 2代会長に就任し「勘蔵」の名前を継いだ。(中台) 平治郎は、
明治元年(1868) 1月26日、
(中台勘蔵) 初代会長の嗣子として
江戸日本橋 本小田原町で 生まれた。父が入信して布教に専従するようになったため、
明治20年 1月、
家業の魚問屋 木村屋を継いだ。同(明治) 23年には、
(中台勘蔵) 初代会長が組織した「同望会」の会頭になっている。同(明治) 26年 2月27日、「おさづけの理」を拝戴し
同年(明治26年) 12月、
妻 いそ の病気から 布教に専務することを決心し、
その年(明治26年) のうちに、
家業の魚問屋を 廃業した。(中台平治郎が) 2代会長に就任してからは、
(中台勘蔵) 初代会長の希望でもあった 神殿建築に着手した。まず、明治27年12月、
神田区錦町に土地を買い求めた。その後 3年かけて工事が進められ、
約545坪の土地に
神殿 (10間に9間)、
教祖殿(3間に4間)、
客殿 (4間に8間)、
信徒室 (8間に15間)
などが完成した。同(明治) 30年11月1日、
喜びのうちに 神殿移転建築 落成奉告祭を執行した。さらに、同(明治) 28年 9月、
染井墓地に (中台勘蔵) 初代会長の 奥津城を造営。
あわせて、役員、信徒のための墓地も 購入した。これは 現在の 大教会 染井墓地の基礎となっている。
明治32年10月、(中台平治郎) 2代会長は その職を辞し、
家族とともに 神田区 皆川町に引き移った。( 2代会長は 昭和21年 7月9日、享年79歳で 出直している。)
明治32年〜明治43年 (中台庄之助 3代会長)
明治32年 9月8日、
(中台平治郎) 2代会長の辞任にともない
中台庄之助が 会長代理 事務取扱者となり、
翌(明治)33年 2月22日、「おぢば」から許しを得て、
(中台) 庄之助は 3代会長に就任した。(中台) 庄之助は、
安政元年(1854)11月14日、
(中台勘蔵) 初代会長の 弟として生まれた。入信するまでは 鰹節や海苔などの商売をしていた。
明治20年 1月、
突然 原因不明の高熱に冒され、
強い胸の痛みを訴えて
病床に 呻吟する身となった。このとき、兄、中台勘蔵のすすめで、
(中台庄之助 3代会長は)
上原佐助から 天理教の教えを聞き、
たすけられて入信した。その後、商売は番頭に任せて 布教にいそしむようになり、
明治22年 8月18日、「おさづけの理」を拝戴。同(明治) 24年 4月から、商売を廃し、
家族を引き連れて 埼玉県 本庄へ 布教に出た。同(明治) 26年 4月23日には 本庄支教会を設置して
(中台) 庄之助は 初代会長となった。(中台) 庄之助 3代会長 在任中の 明治35年、
「おぢば」に 436坪の敷地を購入し、
49坪 5合の 木造2階建1棟を新築して
「日本橋 三島村事務所」(山辺郡三島村34 番地)を開設した。また、天理教の一派独立により、
明治42年(1909) 1月31日、
分教会から 大教会へと昇格した。翌(明治) 43年3月、
(中台庄之助) 3代会長は その職を辞し、
以後は 大教会にあって 後進の指導にあたった。明治年間には、
関東地方 及び 三重、長野、新潟、北海道の各地にわたって
20年代に 52ヵ所、
30年代に 14カ所、
40年代には 13ヵ所、
計79ヵ所の 部内教会が設置されている。
明治43年〜昭和15年 (中台赤太郎 4代会長)
明治43年 3月23日、
中台赤太郎が 4代会長に 就任した。(中台) 赤太郎は、
明治17年 5月5日、
東京市 京橋区五郎兵衛町にて、
3代会長 中台庄之助の子として 生まれた。父とともに 教会生活を営み、
明治36年 9月25日には「おさづけの理」を拝戴し、
同(明治) 41年には、
増野道興らとともに 東京青年会を組織している。翌(明治) 42年、明治大学 文学部を卒業した。
(中台赤太郎は) 4代会長に 就任後、
明治45年 2月11日、
群馬県富岡から 横山とわ を 妻に迎えた。大正2年(1913) 1月、
部内の 沼田支教会が 海外布教を開始した。(中台赤太郎) 4代会長は 積極的にこれを支援し、
中国各地 (上海、青島など) への布教を 成功させた。また、大正3年 4月、
教祖30年祭に参拝する人々のために、
詰所を増築した(2階建1棟、44坪)。そして また、大正10年には、
教会本部の境内が 拡張されることを見越し、
この三島村の信徒詰所を 移転することになる。丹波市町 川原城に土地を求めて、
同年(大正10年) 1月27日、鍬入式を行った。一方、
この頃から始まった 教祖40年祭活動を通して、
熱心な布教がすすめられ、
大正11年から 同(大正) 14年末までに
約220ヵ所の 教会の設置をみている。また、
布教要員の育成もすすめられ、
「別科生」として 毎期 100名以上を 送り出した。こうした中に、
大正12年 9月1日、
関東大震災によって、
大教会を始め 東京で13ヵ所、
神奈川県 9ヵ所、
千葉県 1ヵ所が 罹災した。さっそく、部内教会や信者たちの協力により、
仮建築ではあったが 復興がすすめられた。翌(大正13年) 12月には
76坪の神殿をはじめ 付属建物を含めて 237坪余のものが 完成した。大正14年には、
教祖40年祭に参拝する人々の受け入れのため、
信徒詰所の増築(2階建1棟 156坪)をなした。この詰所は、
昭和6年、8年にも 増改築がなされて
一応の完成を見ている。昭和8年4月、
教会本部からの声を受けて
大教会の移転建築がはじまった。まず、同年(昭和8年) 9月に、
品川区 五反田 5丁目108番地の土地 (1,609坪) を購入。同年(昭和8年) 12月26日、神殿 移転建築について 許しを得て、
翌(昭和) 9年10月15日、講堂が落成したので、
ここへ「お目標」を遷座し 仮鎮座祭を 執行した。昭和10年 7月2日、
神殿(164坪)、ならびに 付属建物が完成、
新築落成 奉告祭を 執行した。同(昭和) 11年の 教祖50年祭には
6,000余名がおぢばへ参拝するなど 教勢は一段と伸展した。同(昭和) 15年 2月、阪東分教会が分離して 本部直属となった。
昭和15年9月1日、
4代会長 中台赤太郎は 享年57歳で 出直した。(中台) 赤太郎は 会長としてのつとめばかりでなく、
教会本部においては
昭和3年 3月から 天理中等学校 初代校長、
同(昭和) 8年12月に 北海道 教務支庁長、
同(昭和) 11年1月からは 本部員としてつとめるなど、
生涯 天理教発展の上に尽くした。
昭和15年〜昭和48年 (中台赤太郎 5代会長)
(中台赤太郎) 4代会長の出直しによって、
昭和15年(1940)10月28日、
5代会長として 中台義夫が就任した。(中台) 義夫は、
明治39年 8月12日、
奈良県 丹波市町 三島において、
春野喜市・たか の 3男として生まれた。昭和3年 2月19日、「おさづけの理」を拝戴。
同(昭和) 6年10月23日、
中台春枝 と結婚して 日本橋大教会に迎えられた。同(昭和) 8年には 東京市向島へ 布教に出ている。
5代会長に就任した (中台) 義夫は、
まず、
教祖40年祭で 4倍加した 部内教会の内容充実に 尽力した。大教会においては、
直轄の信者による「日本橋講」を結成して 布教活動をすすめた。しかし、第2次世界大戦の勃発により、
教会の布教活動は 停滞せざるを得なかった。国家からの要請により、
日本橋大教会においても
炭坑作業に「ひのきしん」の要員を送り出した。この戦争のため、
昭和20年 5月24日、
大教会は 全焼した。また 部内教会も
36ヵ所が焼失、
爆弾による破壊 2カ所、
強制疎開 10ヵ所、
海外からの引揚げ 4カ所
という被害をうけた。敗戦後、さっそく復興建築に着手し、
昭和22年 4月2日、
神殿 および 付属建物 6棟(153坪) を完成、落成奉告祭を 執行した。昭和23年 4月、
大教会 創立60周年 記念祭を執行、
この記念事業として「よろづ相談部」を開設した。これは
教会本部の「各地 社会文化施設の拡充」 とのスローガンを受けたものであり、
法律、税務、事情、結婚の相談 および 医療活動であった。翌(昭和) 24年 4月には
「池田山診療所」を設け、
内科、小児科、レントゲン科、耳鼻咽喉科、歯科の診療をはじめた。昭和26年 6月、
2代真柱の言葉を受け、
神殿の復興建築に 着手した。まず、翌(昭和) 27年 4月1日、
第1期工事のうちの 講堂が完成したので 仮遷座祭を執行。続いて 工事はすすめられ、
同(昭和) 29年10月1日、
神殿 (221坪) ならびに 付属建物の 落成奉告祭を執行した。昭和34年 8月、
大教会では 創立70周年を期して 教会内容の一層の充実をはかり、
これを記念して 客殿が新築された。翌(昭和) 35年から、
戦後はじめての海外布教がはじまり、
南米コロンビア、ブラジルへと 布教師を派遣した。同(昭和) 44年11月、
大教会 創立80周年記念事業として、
鉄筋コンクリート3階建(延256坪) の「千戸寮」の新築をみている。昭和47年 3月、
教会内容の充実に 力を注ぐことになった。これによって、
それまで 教会の機能を十分に果たすことのできなかった教会が 30数カ所あったが、
1年間で 皆無となった。また、「おつとめ」奉仕者の数も増加し 初期の目的を果たした。
さらに、同(昭和) 49年 9月、
初代会長の 80年祭を期して『日本橋大教会史 第1巻 (昭和15年まで) 』を刊行した。この活動のなかで、
昭和48年(1973) 3月26日、
(中台義夫) 5代会長は その職を辞し、
同年(昭和48年) 6月4日、
享年 66歳で出直した。
昭和48年〜 (中台春満 6代会長)
昭和48年3月26日、
中台春満が 6代会長に就任し同年(昭和48年) 5月2日、
会長就任奉告祭を執行した。〔現住所〕〒141 東京都品川区 東五反田 5丁目25番1号
〔電話〕 03-3441-2320(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑』昭和50年度版)
(『天理教事典』1977年版 P,664~666)
おわりに

天理教各教会の歴史を知りたいとの思いで始めた
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。
9回目の 今回は、
「日本橋大教会」の歴史を勉強しました。
当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。
とても古い資料なので、
記載内容も 1970年代以前までとなっており、
かなり昔の歴史にとどまっています…
しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。
十分 私のニーズは満たされるので、
そのまま書写し続けております (^_-)-☆
「日本橋大教会」は「東 大教会」から分離昇格した大教会です。
東大教会の記事は、2024年5月11日に公開しました。
今回は日本橋大教会について調べたわけですが、
私は、今回のリサーチを通して 初めて、
「日本橋大教会」は 【東京都品川区 五反田】という所にあるのだと知りました。
「すげぇ…、ホントの都心、大都会にあるんだぁ…」
と、妙なところで驚いたのですが
と同時に、
きっと都会の教会ゆえの苦労も多いんだろうなぁ…
との 低俗な感情もふつふつと湧き出してくるのでした。
今回の「日本橋大教会」についての勉強では、
東京都品川区という大都会に存在している…
という妙な部分に、最初のところで強いインパクトを受けてしまって、
私の中で、ちょっと教会所在地に関する部分に意識が集中してしまった感があります…(笑)
「日本橋大教会」の所在地は、
『天理教事典』によると、
最初から 現在の 品川区五反田だったわけではなくて、
最初の神殿は 神田区錦町に建築されたとのこと。
『天理教事典』によれば、
中台平治郎 2代会長が
明治27年12月に 神田区錦町に土地を買い求め、
その3年後の明治30年11月に神殿移転建築落成奉告祭を執行した、
とあります。
2代会長? 初代会長・中台勘蔵先生の時代には神殿がなかった?…
という疑問を抱えながら、
以前まとめた 東大教会の記事 を見ていたところ、
その中に、以下のような記述があるのを見つけました。
明治27年(1894)、
『天理教事典』「東 大教会」説明文 P,21
先の教会本部の公認にあたり土地建物を献納した
中台勘蔵を教会長とする 日本橋支教会は
2月17日のおさしづにより 日本橋分教会に 分離昇格した。
『天理教事典』の「東 大教会」の説明文の中に
「…教会本部 の公認にあたり土地建物を献納した 中台勘蔵 を教会長とする 日本橋支教会…」
と記載されています。
中台勘蔵先生は、
天理教公認のために必要な土地建物を
教会本部に献納した…
もしかすると、
そのために 自分の教会・神殿の土地がなかった(なくなった)、
ということ?
ネットを検索してみましたが、
これについての詳しいところは、私には分かりません。
きっと、日本橋大教会関係の方に直接尋ねればすぐ分かることでしょうが、
何分、人脈の乏しい私には 日本橋関係の方とのご縁がなく、わかりません (-_-;)
教会本部の公認のために土地建物を献納されたというのは、もの凄い伏せ込みだと思います。
『天理教事典』の「日本橋大教会」説明の項目にも 記載されるべき事実のようにも思います。
ただ、
それが、ご自分の日本橋支教会の土地・神殿をお供えしたものだったのか?
日本橋支教会と何らかの関りのある行為だったのかどうか?
という(信仰うんぬんは一旦横に置いた)事実関係については、
しっかりとしたリサーチが出来ておりませんので、
ここで何かを書くのは控えておきたいと思います。
『天理教事典』の「日本橋大教会」説明の項目に
初代・中台勘蔵先生の時代の土地・建物についての記述がないのは何故かなぁ…
と単純な疑問を抱いたところから、
このような、一見、こだわる必要などないような細部に関して
あれこれお思案を巡らせているわけですけれども…
中台勘蔵先生の時代に全く神殿がなかった ということはないでしょうから、
『天理教事典』の「日本橋大教会」の記述は、
きっと、本格的な神殿ができたのは2代会長中台平治郎先生の時代だよ…
という意味なのだろう、と思います。
が、いずれにしても、
都心であるが故の土地を確保する大変さというものは、
地方とは比べ物にならぬほど並々ならぬものであったことは間違いないであろう、
と 想像致します。
それほど苦心して手に入れた土地・神殿であるにも関わらず、
大正12年 9月「関東大震災」によって罹災してしまう――
奇しくも、現在においても、2024年元日に石川県能登半島で大地震がありました。
多くの方々が被災され、そこからの復興を目指して懸命に努力する姿と重なる感がありますが、
当時の先人先生方も、
そのような大災害の中、歯を食いしばって復興を進められた。
そして、昭和8年、教会本部からの声もあり 移転建築に着手。
その結果、品川区五反田の土地を手に入れられ、現在へと至っている、
というわけなのですね。
都心に行こうと思って、都心を意識して移っていったわけじゃない。
…しかし、そのように血みどろ思いで復興を果たしたにも関わらず、
『天理教事典』を読んでわかるのは、
(都心の場所を動いたわけではないものの)
太平洋戦争における東京大空襲のため、
昭和20年 5月24日に教会が全焼してしまったという事実――
『天理教事典』では そのあたりの経緯をサラリと書いておられだけですし、
文字を追いかけるだけだと、今イチ ピンとこない。
しかし、よくよく考えてみると、
震災からやっと復興したのに、空襲で…すべてご破算!
「神も仏もないのか‼︎」
そんな 絶望的な気持ちになってしまったのではないか、
私なら絶望してしまう…
そう思います。
――しかし、そんな絶望的な状況を乗り越えて、無事に復興を成し遂げ、
今では、都心の大教会として見事な輝きを放っておられる。
「東 大教会」の所でも勉強しましたが、
今回の「日本橋大教会」の歴史について調べることを通して、
都心の古い教会には、
関東大震災、東京大空襲という2つの大きな節が、外せない歴史として深く刻まれている、
ということを 改めて感じました。
田舎の教会にも それなりの苦労があることは 間違いありません。
しかし、今回の「日本橋大教会」歴史の勉強を通して
――都会の教会には都会の教会特有の苦労がある…
特に東京の教会は、
関東大震災、大空襲、と立て続けに大節に襲われながらも
そのような苦難の歴史を乗り越えて、今がある――
と、しみじみ感じさせられたことでした。
「人に歴史あり」
組織にも 歴史あり…
歴史を踏んで 今がある――
だからこそ、
今を輝かせるためには
「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。
ということで――
今回は「日本橋大教会」初期の歴史の勉強でした。
…ちょっと今回は、
東京都品川区という教会所在地に関する部分に囚われた記事になってしまいました…
お恥ずかしい (^^ゞ
公開するのを控えた方がいいかな…書き直すべきかな…
とも思いましたが、
まぁ、この記事のメインは『天理教事典』の書写部分だし、
自己満足ブログだから…(という言い訳を盾にして)
このまま公開させて頂くこととします… (~_~;)
人生、死ぬまで勉強。
今後も、勉強し続けていきたいと思います。
ではでは、今回はこのへんで。

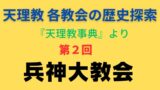
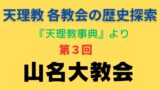
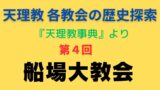
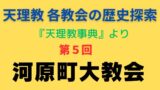
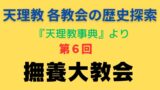
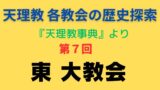
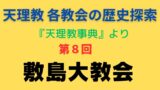
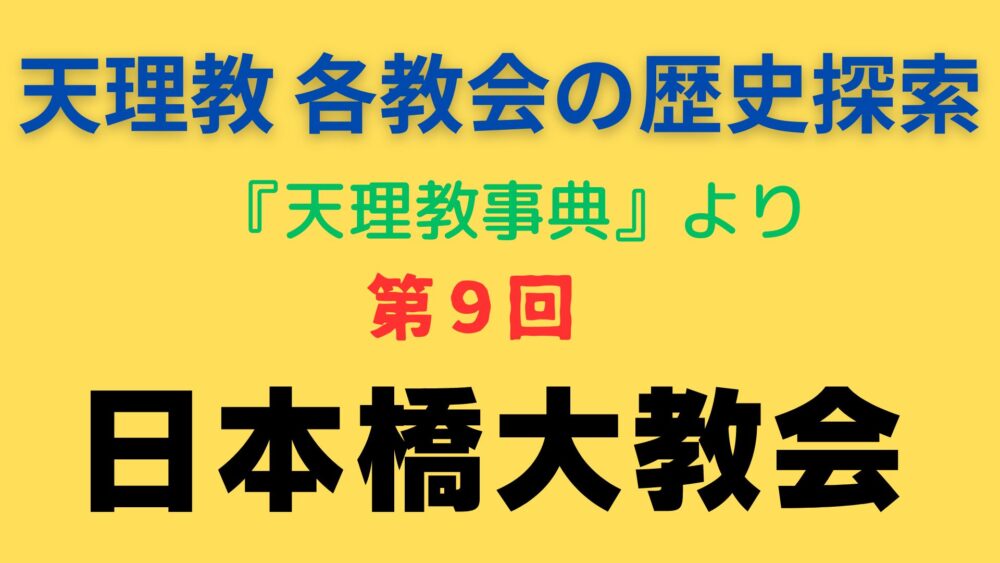
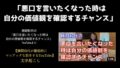
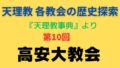
コメント