Dear everyone,
こちらは、
ふらふら彷徨う「さまよい人」による
『さまよいブログ』
= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。
今回も、
『天理教事典』(1977年版)に記載された
各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。
私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)
最新版👇
このシリーズを始めた理由については、
当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。
前回は、
教会番号40番「西陣大教会」の『天理教事典』記述を書写して
その歴史を勉強しました。
今回は、
教会番号41番「大縣大教会」について勉強します。
- 大縣大教会(おおがた だいきょうかい)
- 増井りんの生い立ち(天保14年〜明治4年頃)
- 増井りんの奇蹟(明治5年〜明治7年)
- 増井りんのおぢばがえり(明治7年)
- 入信後の増井りん、その歩み(明治7年頃〜昭和14年)
- 真恵講の誕生(明治9年)
- 増井幾太郎の転輪王講社世話係就任(明治13年〜昭和14年頃)
- 真恵講の道の広がり(明治17年頃〜明治21年頃)
- 大縣支教会の開設(明治21年頃〜明治25年)
- 初めての神殿ふしん(明治25年頃〜明治27年)
- 大縣支教会の道の広がり(明治27年頃〜明治31年頃)
- 高安から分離、大縣分教会へ昇格(明治32年)
- 信者詰所の新築(明治34年)
- 大縣分教会昇格後のふし(明治35年〜明治37年頃)
- 停滞からの復活(明治37年頃〜大正5年頃)
- 詰所の移転〜教勢拡大(大正10年頃〜大正14年)
- 増井幾太郎初代会長の出直(大正15年)
- 増井小玉2代会長の就任(大正15年)
- 大縣中教会へ昇格〜教勢倍加運動(昭和2年〜昭和6年頃)
- 神殿建築〜落成奉告祭(昭和3年〜昭和7年)
- 大教会への昇格〜太平洋戦争(昭和15年〜昭和20年)
- 戦後復興(昭和21年〜昭和20年)
- 増井常信の生い立ち〜3代会長就任まで(〜昭和26年)
- 戦災からの復興ふしん(昭和26年頃〜昭和28年)
- 教祖80年祭頃〜90年祭活動(昭和37年〜昭和48年頃)
- おわりに
大縣大教会(おおがた だいきょうかい)

増井りんの生い立ち(天保14年〜明治4年頃)
天保14年(1843) 2月16日、
増井りんは、
父・善治、母・うの の一人娘として、
河内大県の里に生まれた。増井家は 代々、村の年寄役をつとめ、
農家としても 地持ちとして聞こえていた。
城主・北条相模守より 苗字帯刀を許された程の 旧家でもある。19歳の時、
南河内郡 島泉村の 林栄治郎の2男・惣三郎(当時26歳)を養子に迎えて、
21歳の時 長男、続いて 長女、次男と子宝にも恵まれて
満ち足りた10年が 過ぎ去った。
増井りんの奇蹟(明治5年〜明治7年)
明治5年、(増井)りん 30歳の時、
父・善治が、そして 夫・惣三郎までも、
僅かな病で相ついで出直し、
3人の幼児をかかえて 彼女は全く途方にくれた。翌年(明治6年)、さらに自分も リウインシャクを病む身となり、
医者、薬、祈禱、どんな信心もしたが、
とうとう 3年の寿命と宣告され、
悲歎にくれて 明治7年を迎えた。その年(明治7年)、
10月25日夜から 翌日の26日にかけて、
(増井)りん の両眼は 一夜の間に腫れ塞がり、痛みも激しく、
彼女は 手をひかれて 有名な眼医者を回ったが、
いずれも全治不能 のソコヒと診断、
いわゆる 盲目の宣告であった。当時12歳の長男 (増井)幾太郎は、
何とかして 母の眼病を癒したさに、
その翌月(11月)、所用で大和の竜田へ行った帰り途、
道連れになった男の人に 母のソコヒの話をした。親を思う心に感心したのか、その人は
「それならば 大和の天竜さんに拝んで貰いなされ。
お産の神さんやが、どんな病気でも 三日三夜の祈禱で救けて下さるそうな。」
と、親切に教えてくれた。母と子は 早速 教えられた通り、
大和の方を向いて、唯々 たすけて下さるように、
と 3日間、一心不乱にお願いをしたが、
何の効能も見えなかった。落胆の末、
男衆の 為八 を代人として
大和の庄屋敷に差し向けることになり、
為八は 早速 大和へ出向いた。為八は、
「神さんというのはお婆さんで、一段高い所に赤い着物を着て座っておられました。
また『身の内かしもの、かりもの』『因縁の理』『八つの埃』その他 詳しいことは無学で覚えきれないので、取次の先生に書いて貰ってきました。」
と言って (書かれた紙を) 差し出した。(増井)幾太郎が (それを) 声をあげて読んだ……
初めて聴く教理、それは 一つ一つ (増井)りん の心にしみ込んで
りん の心の眼は大きく開いた。そして (為八が受け取った紙には)
三日三夜の願いをかける時には、
まず この教理を心に治めてからお願いするように
と、最後に書き添えてあった。彼女(増井りん)は、改めて
「こうして 御教理を聞かして頂きますれば、たとえ 自分の身上はどうなりましても結構でございます。
前生の因縁とあれば、我が家がどうなりましても結構でございます。
因縁果たしのためには、杖にすがってでも たすけ一条のため、因縁果たしのために通らせて頂きます。
たとえ火の中、水の中も 道ならば 喜んで通らせて頂きます」
との心定めをした。再び 三日三夜の願いがかけられた。
11月も末の寒い朝、そして 冷たい夜半、
12歳の (増井)幾太郎も、8歳の富枝も、
母と共に 井戸水を汲み上げて水ごりをとり、
(増井)りんは 三日三夜の間、ずっと端座して
願あけの朝を迎えた。夜明けの光があたりを包んだ。
(と共に)
やがて 夜明けの光は、彼女の両眼に再び光を与えた(のであった)。
鮮やかなご守護である。
『稿本天理教教祖伝逸話篇』
36.定めた心
明治七年十二月四日(陰暦十月二十六日)朝、増井りんは、起き上がろうとすると、不思議や両眼が腫れ上がって、非常な痛みを感じた。
日に日に悪化し、医者に診てもらうと、ソコヒとのことである。
そこで、驚いて、医薬の手を尽したが、とうとう失明してしまった。
夫になくなられてから二年後のことである。
こうして、一家の者が非歎の涙にくれている時、年末年始の頃、(陰暦十一月下旬)当時十二才の長男幾太郎が、竜田へ行って、道連れになった人から、
「大和庄屋敷の天竜さんは、何んでもよく救けて下さる。
三日三夜の祈祷で救かる。」
という話を聞いてもどった。
それで早速、親子が、大和の方を向いて、三日三夜お願いしたが、一向に効能はあらわれない。
そこで、男衆の為八を庄屋敷へ代参させることになった。
朝暗いうちに大県を出発して、昼前にお屋敷へ着いた為八は、赤衣を召された教祖を拝み、取次の方々から教の理を承わり、その上、角目角目を書いてもらって、もどって来た。
これを幾太郎が読み、りんが聞き、
「こうして、教の理を聞かせて頂いた上からは、自分の身上はどうなっても結構でございます。
我が家のいんねん果たしのためには、暑さ寒さをいとわず、二本の杖にすがってでも、たすけ一条のため通らせて頂きます。
今後、親子三人は、たとい火の中水の中でも、道ならば喜んで通らせて頂きます。」
と、家族一同、堅い心定めをした。
りんは言うに及ばず、幾太郎と八才のとみゑも水行して、一家揃うて三日三夜のお願いに取りかかった。
おぢばの方を向いて、なむてんりわうのみことと、繰り返し繰り返して、お願いしたのである。
やがて、まる三日目の夜明けが来た。
火鉢の前で、お願い中端座しつづけていたりんの横にいたとみゑが、戸の隙間から差して来る光を見て、思わず、
「あ、お母さん、夜が明けました。」
と、言った。
その声に、りんが、表玄関の方を見ると、戸の隙間から、一条の光がもれている。
夢かと思いながら、つと立って玄関まで走り、雨戸をくると、外は、昔と変わらぬ朝の光を受けて輝いていた。
不思議な全快の御守護を頂いたのである。
りんは、早速、おぢばへお礼詣りをした。
取次の仲田儀三郎を通してお礼を申し上げると、お言葉があった。
「さあ/\一夜の間に目が潰れたのやな。
さあ/\いんねん、いんねん。
神が引き寄せたのやで。
よう来た、よう来た。
佐右衞門さん、よくよく聞かしてやってくれまするよう、聞かしてやってくれまするよう。」
と、仰せ下された。
その晩は泊めて頂いて、翌日は、仲田から教の理を聞かせてもらい、朝夕のお勤めの手振りを習いなどしていると、又、教祖からお言葉があった。
「さあ/\いんねんの魂、神が用に使おうと思召す者は、どうしてなりと引き寄せるから、結構と思うて、これからどんな道もあるから、楽しんで通るよう。
用に使わねばならんという道具は、痛めてでも引き寄せる。
悩めてでも引き寄せねばならんのであるから、する事なす事違う。
違うはずや。
あったから、どうしてもようならん。
ようならんはずや。
違う事しているもの。
ようならなかったなあ。
さあ/\いんねん、いんねん。
佐右衞門さん、よくよく聞かしてやってくれまするよう。
目の見えんのは、神様が目の向こうへ手を出してござるようなものにて、さあ、向こうは見えんと言うている。
さあ、手をのけたら、直ぐ見える。
見えるであろう。
さあ/\勇め、勇め。
難儀しようと言うても、難儀するのやない程に。めんめんの心次第やで。」
と、仰せ下された。
その日もまた泊めて頂き、その翌朝、河内へもどらせて頂こうと、仲田を通して申し上げてもらうと、教祖は、
「遠い所から、ほのか理を聞いて、山坂越えて谷越えて来たのやなあ。さあ/\その定めた心を受け取るで。
楽しめ、楽しめ。
さあ/\着物、食い物、小遣い与えてやるのやで。
長あいこと勤めるのやで。
さあ/\楽しめ、楽しめ、楽しめ。」
と、お言葉を下された。
りんは、ものも言えず、ただ感激の涙にくれた。
時に、増井りん、三十二才であった。
増井りんのおぢばがえり(明治7年)
(抑えきれぬ程の感激を抱いて)
(増井)りんは 初めて「おぢば」に帰った。
明治7年(1874) 11月下旬のことである。教祖は待ちかねていたように
「遠い所からほのか理をきいて山坂こえて谷こえて来たのやなあ。
さあさあ、その定めた心うけとるで、たのしめ、たのしめ。
さあさあ、きもの、くいもの、こずかい与えてやるのやで。
さあさあ、たのしめ、たのしめ、たのしめ。」
と 仰せられた。3年の寿命もないと言われた体、そして盲目
そこから元(の体)に戻して頂いた (増井)りんは、
もう 家にジッとしていられなかった。(その後 増井りんは)
雨の日も風の日も、
夜となく昼となくおぢばに通った。河内から山越えて7里半、
大雪の日には、
まろびつ ころびつ「おやしき」に帰って来た (増井)りんを、
教祖は あたたかい両の手でしっかりと握りしめて下さった(のだった)。
『稿本天理教教祖伝逸話篇』
44.雪の日
明治八、九年頃、増井りんが信心しはじめて、熱心にお屋敷帰りの最中のことであった。
正月十日、その日は朝から大雪であったが、りんは河内からお屋敷へ帰らせて頂くため、大和路まで来た時、雪はいよいよ降りつのり、途中から風さえ加わる中を、ちょうど額田部の高橋の上まで出た。
この橋は、当時は幅三尺程の欄干のない橋であったので、これは危ないと思い、雪の降り積もっている橋の上を、跣足になって這うて進んだ。
そして、ようやくにして、橋の中程まで進んだ時、吹雪が一時にドッと来たので、身体が揺れて、川の中へ落ちそうになった。
こんなことが何回もあったが、その度に、蟻のようにペタリと雪の上に這いつくばって、なむてんりわうのみことなむてんりわうのみことと、一生懸命にお願いしつつ、やっとの思いで高橋を渡り切って宮堂に入り、二階堂を経て、午後四時頃お屋敷へたどりついた。
そして、つとめ場所の、障子を開けて、中へ入ると、村田イヱが、
「ああ、今、教祖が、窓から外をお眺めになって、『まあまあ、こんな日にも人が来る。なんと誠の人やなあ。ああ、難儀やろうな。』と、仰せられていたところでした。」
と、言った。
りんは、お屋敷へ無事帰らせて頂けた事を、「ああ、結構やなあ。」と、ただただ喜ばせて頂くばかりであった。
しかし、河内からお屋敷まで七里半の道を、吹雪に吹きまくられながら帰らせて頂いたので、手も足も凍えてしまって自由を失っていた。
それで、そこに居合わせた人々が、紐を解き、手を取って、種々と世話をし、火鉢の三つも寄せて温めてくれ、身体もようやく温まって来たので、
早速と教祖へ御挨拶に上がると、教祖は、
「ようこそ帰って来たなあ。
親神が手を引いて連れて帰ったのやで。
あちらにてもこちらにても滑って、難儀やったなあ。
その中にて喜んでいたなあ。
さあ/\親神が十分々々受け取るで。
どんな事も皆受け取る。
守護するで。
楽しめ、楽しめ、楽しめ。」
と、仰せられて、りんの冷え切った手を、両方のお手で、しっかりとお握り下された。
それは、ちょうど火鉢の上に手をあてたと言うか、何んとも言いあらわしようのない温かみを感じて、勿体ないやら有難いやらで、りんは胸が一杯になった。
入信後の増井りん、その歩み(明治7年頃〜昭和14年)
そして、家も子もすっかり人任せにして、
(増井)りんは 女一人、白熱的な布教を始めた。不思議なたすけは相ついで、
3年程の間に、道は 中河内、南河内の各村に伸び広がり、
求めずして 信者の結成ができた。勿論、親戚の反対、警察の弾圧、僧侶の攻撃はあったが、
さらさら気にも止めず、
又 彼女にたすけられた 熱心な 9人の周旋方は、
手分けして 各地に天理王命の神名を流した。その間、
(増井)りんのおぢばがえりは、ますます繁くなり、
明治10年頃、教祖より
「日を定めて、つとめるよう」
とのお言葉をいただき、
おやしきづとめが始まった。さらに 明治12年 6月頃、
「すぐ すぐ すぐ、用につかふとて引よせた。
すぐ すぐ、はやく はやく、おくれた おくれた。
さあさあ、たのしめ たのしめ たのしめ。」
との言葉により、
(増井りんは) その日より
教祖のお守役として、お側に仕えるようになった。
『稿本天理教教祖伝逸話篇』
65.用に使うとて
明治十二年六月頃のこと。
教祖が、毎晩のお話の中で、
「守りが要る、守りが要る。」
と、仰せになるので、取次の仲田儀三郎、辻忠作、山本利八等が相談の上、秀司に願うたところ、
「おりんさんが宜かろう。」
という事になった。
そこで、早速、翌日の午前十時頃、秀司、仲田の後に、増井りんがついて、教祖のところへお伺いに行った。
秀司から、事の由を申し上げると、教祖は、直ぐに、
「直ぐ、直ぐ、直ぐ、直ぐ。
用に使うとて引き寄せた。
直ぐ、直ぐ、直ぐ。
早く、早く。
遅れた、遅れた。
さあ/\楽しめ、楽しめ。
どんな事するのも、何するも、皆、神様の御用と思うてするのやで。
する事、なす事、皆、一粒万倍に受け取るのやで。
さあ/\早く、早く、早く。
直ぐ、直ぐ、直ぐ。」
と、お言葉を下された。
かくて、りんは、その夜から、明治二十年、教祖が御身をかくされるまで、お側近く、お守役を勤めさせて頂いたのである。
(増井)りんは
入信以来、教祖より「針のしん」のおゆるし、
「息のさづけ」「あしきはらいのさづけ」「肥のゆるし」等、
数々の重い理を戴いた。また、後年には、
婦人本部員として 別席取次を 晩年までつとめた。明治26年 5月18日の「おさしづ」により、
本席のお守役を15年間、
さらに 初代、2代真柱にも仕えた。97歳の高齢まで
元一日の心定めを貫き通した
65年間のみちすがらであった。昭和14年(1939) 12月17日、
(増井)りんは
おぢばで出直した。
真恵講の誕生(明治9年)
明治9年(には)、すでに
「松は枯れてもあんじなよ、末はたのもし、うちわけ場所」
とのお言葉を頂いていたが、
(増井)りんりんがおやしきに住込むようになってからは、
残された講社の修理と伝道は、
長男・(増井)幾太郎に 受け継がれた。
『稿本天理教教祖伝逸話篇』
47.先を楽しめ
明治九年六月十八日の夜、仲田儀三郎が、
「教祖が、よくお話の中に、
『松は枯れても、案じなし。』
と、仰せ下されますので、どこの松であろうかと、話し合うているのですが。」
と言ったので、増井りんは、
「お祓いさんの降った松は枯れる。
増井の屋敷の松に、お祓いさんが降ったから、あの松は枯れてしまう。
そして、あすこの家は、もうあかん。潰れてしまうで。
と、人々が申します。」
と、人の噂を、そのままに話した。
そこで、仲田が、早速このことを、教祖にお伺いすると、教祖は、
「さあ/\分かったか、分かったか。
今日の日、何か見えるやなけれども、先を楽しめ、楽しめ。
松は枯れても案じなよ。
人が何んと言うても、言おうとも、人の言う事、心にかけるやない程に。」
と、仰せ下され、しばらくしてから、
「屋敷松、松は枯れても案じなよ。
末はたのもし、打ち分け場所。」
と、重ねてお言葉を下された。
明治12年、
弱冠17歳の (増井)幾太郎は
講社に「真恵講」という名前をつけ、その講元となり、
役員・阪内万蔵を従えて、おぢばに講名簿を提出している。
増井幾太郎の転輪王講社世話係就任(明治13年〜昭和14年頃)
さらに 翌年(明治13年) 9月17日には
(増井幾太郎は)
教祖の嫡子・秀司より、(おやしきの) 転輪王講社 世話係の辞令を受け、
一路 荒道開拓を急いだ。当然、借財が かさんで、
明治14年には
増井家の家財道具一切、3日間の市を開き、借金の整理をしたこともある。その時は、親戚が殊の外やかましく、
親族会議に (中山)秀司も立会っている。(増井)りんは その頃、
すでに 教祖のお守役に専念していた。
真恵講の道の広がり(明治17年頃〜明治21年頃)
明治17年頃より
河内方面にも 警察の干渉は一段と激しく、
(増井)幾太郎は 2週間ほど留置された。しかし、(そのことにより) かえって 布教に筋金が入り、
(増井幾太郎は) 25歳で「神水のさづけ」を拝戴した。教線は、
大県村を中心に21ヵ村に伸びて、
その修理のため「真恵講」の下に
更に 第1号から第10号まで、
要所要所に 熱心な講元を置いて
布教活動は活気を呈した。
大縣支教会の開設(明治21年頃〜明治25年)
やがて 明治21年となり、
天理教は 神道本局に属して 地方庁より公認、
各地の講元は 俄に 分・支教会設立の計画を進めた。河内方面は
教興寺に 松村(吉太郎)(=後の高安分教会) 、
大県に 増井(幾太郎)(=真恵講)、
その中間(恩智〜柏原)に 板倉(槌三郎)、山本(利三郎) 両名(=後の中河分教会) が
(それぞれ) 教線を張っていた。(天理教教会本部公認に伴い、各地で分教会や支教会開設の運動が盛んになる中で)
両者(=松村 / 板倉&山本) 共に
(自らの教会へ)「真恵講」が所属することを望んだが、
(最終的に 真恵講は)
松村(吉太郎)の請に応じて、高安(分教会)に所属(することとした)。丹精した法善寺村の信徒は
全部、板倉・山本の両名(後の中河分教会) に所属させ(ることとし)て、
明治24年、
「真恵講」は、高安光道講 第3号と名を改めた。しかし、
その頃すでに 支教会設置の機運は熟しており、
(真恵講 改め 高安光道講 第3号も)
明治25年(1892) 1月22日に本部の許しを得て、
同年(明治25年) 9月19日、地方庁公認となった。
(=大縣支教会の開設)
初めての神殿ふしん(明治25年頃〜明治27年)
さて 支教会となると 昔ながらの増井家の居宅では手狭となり、
許しを得て 居宅の北側に神殿のふしんにかかった。しかし、途中 瓦を葺くことができず、
屋根に松茸が生えると冷評されながら 東奔西走、
やっと竣工した。
(神殿)落成奉告祭は 明治27年 5月15日執行。大縣にとって 最初のふしんである。
大縣支教会の道の広がり(明治27年頃〜明治31年頃)
(神殿落成)奉告祭の後、再び 教勢は活気を呈し、
九州、長野、伊賀、京都、紀州、摂津、淡路へ、
近くは 大阪市内、国分、清水、丹南、多治井、金田方面へ
伸長した。かくて 明治27年より31年までに
大阪で 5ヵ所、京都 2ヵ所、佐賀県 2ヵ所、長野県 1ヵ所、和歌山で 1ヵ所、福岡県に 1ヵ所、
計12ヵ所の 部内教会が設置された。
高安から分離、大縣分教会へ昇格(明治32年)
明治32年 10月27日、高安分教会長母堂・松村さく病気に付、
11月15日 おさしづを仰いだ。その結果、
大縣(支教会)は、高安より分離、
本部直属となり 分教会に昇格することとなった。明治32年12月29日のおさしづにより、速やかに事は運んだ。
信者詰所の新築(明治34年)
さて 本部直属となり、信者詰所が必要となったが、
(増井)りんと 増井丑松 夫婦は 本部神殿南側に居住していたので、
その隣接地を買収、
(明治)34年に
諸設備の整った 詰所の新築落成を見た。
大縣分教会昇格後のふし(明治35年〜明治37年頃)
しかし、こうした喜ぶべきことの反面、
かねて病床の身の 会長夫人(増井)きと が、
翌年(明治35年)3月、
5人の子供を残して出直した。さらに その年(明治35年)の暮には
一背信者の行動が因をなして、
錯雑事件が起きた。田中うめ、巽みつの両婦人役員は、
あくまでも純信仰の堅い信念を貫いて 全責任を負い、
事件は解決を見た。しかし、悪評は誤解を招いて、
(大縣分)教会は 火の消えた有様になった。
停滞からの復活(明治37年頃〜大正5年頃)
(増井幾太郎)会長は 身を挺して事情の解決に当たっていたが、
明治37年10月19日おさしづを仰ぎ、
後添えとして小東小玉を迎え、
心の支えを得て この難を乗り切った。明治41年 天理教一派独立の頃には
部内教会も活気を取り戻した。教祖30年祭の 大正5年(1916) 3月1日、教会に昇格。
部内教会も31ヵ所となり、
九州、四国、兵庫、和歌山、大阪、京都、長野
の各地に 教線は敷かれた。
詰所の移転〜教勢拡大(大正10年頃〜大正14年)
やがて 大正10年秋、教祖40年祭の発表で、
本部神殿のすぐ南側にあった大縣詰所は移転することになり、
間もなく
本部に近い守目堂に 現在の詰所敷地1,233坪を購入した。
大正14年2月、各棟のふしんを終了した。一方 教勢倍加も着々と進み、大正5年に31ヵ所であった部内教会は、
大正10年に 2ヵ所、11年に 4ヵ所、12年、13年 いずれも 4ヵ所、14年には 21ヵ所、15年に 6ヵ所と 計41ヵ所の新設を見、
教祖40年祭には 一躍、部内教会 72ヵ所を数えた。
増井幾太郎初代会長の出直(大正15年)
詰所も落成、部内教会も倍加されて 喜びの40年祭ではあったが、
以前より (増井幾太郎)会長の身体すぐれず、
部内一同の願いも空しく、
大正15年10月1日
(増井幾太郎会長は) 齢64歳をもって出直した。10歳にして父を失い、
12歳の時、母の病気から信仰に入り、
家を顧みない(増井)りんの 布教とおぢばがえり、そして おやしきづとめ(を助け)、
15歳頃より 母のあとを継いで 大縣の道に打込んだ(増井幾太郎)初代会長の功績は (何ものにも代え難いほど)大きかった(と言えるだろう)。
増井小玉2代会長の就任(大正15年)
2代会長 増井小玉は、
明治10年 5月10日、
奈良県生駒郡平群村字平等寺の旧家・小東政太郎の長女として生まれ、
明治37年 28歳で初代会長と結婚、
一度に5人の子供の母親となり、
(増井幾太郎)初代会長を助けた。大正15年11月3日付で2代会長の許しを得た。
大縣中教会へ昇格〜教勢倍加運動(昭和2年〜昭和6年頃)
明けて 昭和2年10月、
教規改正により (大縣)中教会と改称。その年(昭和2年)の11月28日
(増井小玉)会長は、母(増井)りんと相談の結果、
主なる役員16名を電報で招集、
(増井幾太郎)初代会長が 想いを残した大教会昇格と神殿建築を打出した。大教会昇格の序曲として、
再度の教勢倍加に乗出し
昭和2年 1ヵ所、
同(昭和)3年に 37ヵ所、
(昭和)5年と(昭和)6年に 各 1ヵ所、
計40ヵ所が新設、
部内教会は 一躍 112ヵ所となった。
神殿建築〜落成奉告祭(昭和3年〜昭和7年)
一方、神殿建築の方は
教勢倍加に心奪われているうちに、
昭和3年 6月、
突如 (増井)りんの右足が立たず一歩の歩行も叶わぬ(という)容態が生じた。(増井小玉)会長は
「建てねば立たぬ」と悟り、
精神定めて願ったところ、
忽ち全快をみた。(増井幾太郎)初代が生前 心に描いていた東屋敷は 1,700坪となり、神殿、教祖殿、客殿、会長宅、事務所、炊事場など
延560坪の建築は
満 3ヵ年の年月を要した。昭和7年 4月20日、
2代真柱を迎えて 遷座祭、
翌(4月)21日には
盛大に 落成奉告祭を挙行した。この日、90歳の (増井)りんは、
かくしゃくとしてこの盛儀に参列、
一同感激の祭典であった。この時、喜びの日を記念して、
山口佐逸、中西喜代造、原浩恩の手になる
『大縣中教会の沿革』を刊行した。
大教会への昇格〜太平洋戦争(昭和15年〜昭和20年)
さらに 部内教会の内容充実を待って、
昭和15年 1月28日、
大教会昇格をみた。昭和20年 6月1日、
第2回目の大阪空襲の朝、
(大縣大教会は)
事務所と炊事場を残し、重要建物総てを焼失した。部内教会も12ヵ所が戦災にあい、
会長の戦災死 1ヵ所、
引揚教会 1ヵ所、
また 後継者の戦死、信者の離散で
なす術もなき 終戦直後だった。
戦後復興(昭和21年〜昭和20年)
そのような中、
(一同は 大縣)大教会の復興へと立ち上がり、
同(昭和)21年 11月27日
お目標再下付を頂き、
ささやかながら竣工した仮神殿にて、
(昭和21年) 12月13日 鎮座奉告祭を勤めた。やがて部内教会も復興し、
いよいよ大教会神殿の本建築、並びに付属建物建築の声が高まった。(それを受け)
(増井小玉)2代会長は
これを3代会長の初仕事として
その職を3代会長に譲り、
昭和35年7月8日、齢84歳で出直した。
増井常信の生い立ち〜3代会長就任まで(〜昭和26年)
3代会長・増井常信は
大県の隣村・太平寺の素封家、
安田源造の次男として出生。安田家の信仰は、常信の祖父母の代からであった。
縁があって 昭和18年、
(安田)常信は (増井幾太郎)初代会長の3女・あさ子と結婚、
増井家の人となった。当時、太平洋戦争の最中とて、
あさ子の兄であり 会長の後継者たる(増井)義雄は 応召戦地にあった。その後 (増井)常信も海軍に応召。
(両者の)不在中に(大縣大教会は)戦災を受けた。(そして)
(増井)常信は 終戦まもなく帰還したが、
後継者の(増井)義雄は
翌(昭和)21年 3月 華中より病を押して帰還(したものの)、
惜しくも 戦病死した。(増井)常信は
失意の(増井小玉)2代会長をたすけて、
ただ黙々と 焼跡の整理と その復興に没頭した。そして 思いがけなく
昭和26年 1月26日
(増井常信は)3代会長の許しを得た。
戦災からの復興ふしん(昭和26年頃〜昭和28年)
(増井)常信は、
初仕事としての復興建築に寝食を忘れ、
部内また一丸となって
神殿並びに付属建物 延230坪の建築に取り組んだ。(神殿復興の建築は)
戦後の資材難を乗り越えて(見事に完成)
2年半後の昭和28年 10月13日、
2代真柱の臨席を得て 鎮座祭、
翌(10月)14日 落成奉告祭を執行した。また 明治9年 教祖より「打ちわけ場所」と言われた増井家の旧居宅は、
罹災後 ずっと畠になっていた。それを、(増井小玉)2代会長は 殊の外 残念に思い、
当時 田舎では珍しい洋風建物として再現し、
後に 住込役員の住宅になっている。
教祖80年祭頃〜90年祭活動(昭和37年〜昭和48年頃)
やがて 昭和37年を迎え、
(昭和37年)5月16日に たすけ委員長 中山善衛(3代真柱)を、
また (昭和37年) 10月16日の創立70周年記念祭には、
2代真柱(中山正善)を迎えて、
信者は勇みに勇み
教祖80年祭に向かって邁進した。さて
教祖90年祭発表後の昭和48年 1月28日、
(3代)真柱夫妻を迎えて、
同夜、2代真柱霊を(大縣大教会祖霊舎に)合祀。
続いて 教祖の御神座を納め、
また 赤衣も理にふさわしく、
正しく祀り替えた。翌日(1月29日)「教祖90年祭よふぼく決起大会」が開催された。
(その中で)
大縣(大教会)の よふぼく一人一人に 話しかけるように、
やさしく厳しくお仕込み頂く真柱の親心を戴いて、
一同(は)
この旬にこそ、と 大縣の脱皮前進を固く誓い合った。
〔現住所〕 〒582-0018 大阪府柏原市大県4丁目4番19号
〔電話〕072-971-4501(昭和50年12月31日調『天理教統計年鑑」昭和50年度版)
(『天理教事典』1977年版 P,106〜109)
おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。
41回目の今回は、
「大縣大教会」初期の歴史を勉強しました。
当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。
とても古い資料なので、
記載内容も 1970年代以前までとなっており、
かなり昔の歴史にとどまっています…
しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。
十分 私のニーズは満たされるので、
そのまま書写し続けております (^_-)-☆

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】41回目の当記事では
『天理教事典』の中の「大縣大教会」についての記述を書き写して勉強しました。
大縣大教会は、高安大教会から分かれた大教会ですね。
高安大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。
大縣大教会といえば、増井りん先生ですね。
増井りん先生は『稿本天理教教祖伝逸話篇』にお名前がたくさん出てくるので、
天理教初級者の私でも お名前はよく存じております。
ただ、私の中では、
増井りん先生は、
教祖の身の回りのお世話をなされた先生、というイメージが強く、
大縣大教会の創設に関する部分については よく知りませんでした。
増井りん先生が 教祖の身の周りのお世話をするために お屋敷に住み込むようになってからは、
長男の増井幾太郎先生が 河内の実家の責任者のようになられた。
それで、増井幾太郎先生は、
河内方面の信仰の基点として、信者をまとめて「真恵講」を結成。
それが後の「大縣大教会」へつながっていったのですね。
私は、勝手に
「大縣大教会」の初代会長は 増井りん先生だと
思い込んでおりました (^^ゞ
信仰の元一日は 身上をご守護頂いた 増井りん先生であることは間違いないながら、
【組織】としての「大縣大教会」の初代は、
長男の増井幾太郎先生だったということ。
今回の「大縣大教会」学習によって初めて知りました。

これまでに何度も読んで知っていたはずの
『稿本天理教教祖伝逸話篇』の中の増井りん先生の様々なご逸話でしたが、
今回の「大縣大教会」学習を通して、
改めて じっくり味わう機会を頂きました。
何気なく読み流してきた増井りん先生のご逸話、
歴史を踏まえながら拝読すると、実に「深い」ですね。
改めて感動させて頂きました。
そして、
それと同時に、
これまで知らなかった 増井りん先生のご長男
増井幾太郎初代会長のご経歴にも感動しました。
増井幾太郎先生は、
わずか10歳で父親を失い、
その2年後の12歳の時には、母親(増井りん)が失明するという
言葉も出ない程 辛く悲しい状況に陥られた。
そのような状況の中で 増井幾太郎先生は、
何とか母親を助けてもらいたいと駆けずり回り、
庄屋敷村の生神様を知った。
藁にもすがる思いで母親と共に心を定め、
11月の寒さの中もいとわず
母親と妹と一緒に「水垢離」をとり、必死の祈願をなされた。
その結果、
母である増井りん先生は 奇蹟的なご守護を頂かれたわけですが
以後 母親が家のことを顧みることなく布教に励まれるようになってからも、
増井幾太郎先生は
母が家のことを顧み無くなったことに対する不満を訴えることもなく、
その後を付いていかれたわけです。
これは、
母親の身上をおたすけ頂いたことの喜びが如何に大きかったか、
ということを現わしているように思われます。
そして、
母親がおやしきに住み込まれるようになった後は、
母と離れ、河内に残り、
たすかりの原点・元一日を忘れず、
道をそれることなく母のあとを継いで 大縣の道に打込まれたのでした。
何と言っても驚きなのは、
母の身上おたすけ祈願に当たって「水垢離」をとられたのが、
若干「12歳」であられたこと、
そして、
母親が、おやさまからお言葉をいただいておやしきへ住み込むようになり、
その後を受け継いで「講」を担当するようになったのは、
15歳頃の 若年であられた、
ということです。
自分が同年代の頃の生き様を思い返すと、穴があったら入りたい… (>_<)
自分のことしか考えられない私などは、
若くして 神様としっかり向き合うことを可能にする要因は
一体どこにあるのだろう…と思ってしまいます。
増井幾太郎先生のように
年若くとも 神様の方に心を向けて
揺るぎなく歩むことを可能にするものについて、
無い頭を絞って考えてみました。
その結果、私の頭の中に浮かんできたのは、
『稿本天理教教祖伝逸話篇』の中の増井りん先生が初めておぢばがえりした際 おやさまから頂いたお言葉に そのヒントがあるのではないか、
と いうことでした。
「さあ/\いんねんの魂、神が用に使おうと思召す者は、どうしてなりと引き寄せるから、結構と思うて、これからどんな道もあるから、楽しんで通るよう。
用に使わねばならんという道具は、痛めてでも引き寄せる。
悩めてでも引き寄せねばならんのであるから、する事なす事違う。
違うはずや。
あったから、どうしてもようならん。
ようならんはずや。
違う事しているもの。
ようならなかったなあ。
さあ/\いんねん、いんねん。
佐右衞門さん、よくよく聞かしてやってくれまするよう。」
増井りん先生も増井幾太郎先生も、
神が用に使わねばならん道具としての
深い深い「因縁」の魂の方であられたのですね。
若くして、水垢離をとられたり、一途に神様に向き合えるということその事が、
因縁によるものだ、と言えるのではないか…
と思ったりするのです。
そのような、
神様が
「どうしてなりと引き寄せねばならん」
と思召された魂の先生によって築き上げられたのが、
「大縣大教会」!!
当シリーズ8回目「敷島大教会」をまとめた際、
おやさまが「打ち分け場所」になると仰せられたとされる場所は、
大縣大教会(『逸話篇』47先を楽しめ)、
高安大教会(『逸話篇』102私が見舞いに)、
旧郡山大教会(『逸話篇』189夫婦の心)、
敷島大教会、
以上の4ヶ所だ と勉強しました。
確かに、
『逸話篇』(47.先を楽しめ) の中に、
大縣大教会の前身である増井家の屋敷のことを
「屋敷松、松は枯れても案じなよ。末はたのもし、打ち分け場所」
と おやさまが仰られていた、
と書かれてあります。
今回「大縣大教会」について勉強させて頂いて、
「大縣大教会」は、
おやさまが直接「打ち分け場所」であると示された教会であり、
そして、
神様が直々に引き寄せられた
おやしきに深い深い因縁のある増井先生が築き上げられた教会である、
ということを、
改めて 学ぶことが出来ました。
そのような歴史や由緒を知って今の「大縣大教会」を見ると、
何かしら、深い深い奥行きが感じられるような気がしてきます (^^)

その他にも知らないことばかりでしたが、
今回もまた、書き写しを通して いろいろと知ることができて、
とても勉強になりました。
有難いことでした。
「人に歴史あり」
組織にも歴史あり…
歴史を踏んで今がある――
だからこそ、
今を輝かせるためには
「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。
ということで――
今回は「大縣大教会」初期の歴史の勉強でした。
人生、死ぬまで勉強。
今後も、勉強し続けていきたいと思います。
ではでは、今回はこのへんで。

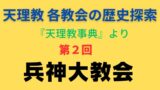
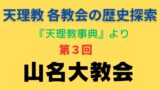
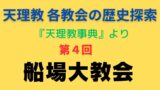
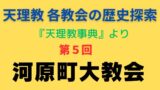
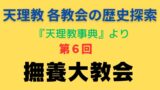
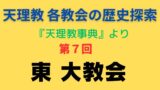
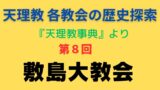
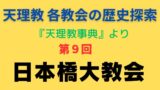
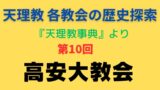
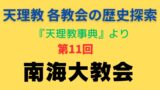
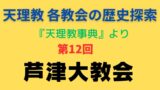
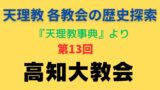
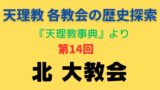
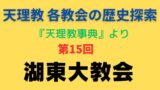
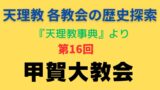
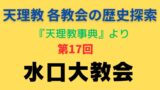
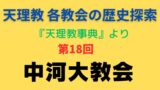
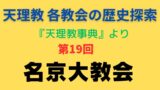
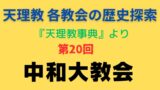
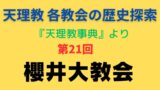
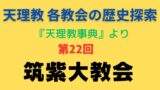
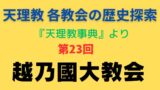
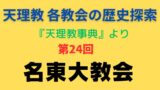
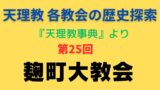
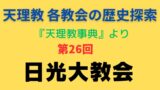
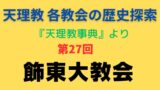
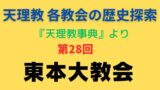
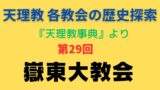
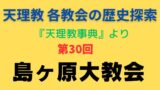
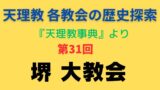
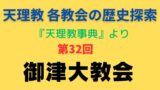

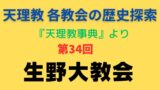
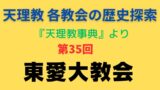
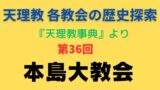
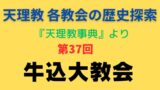
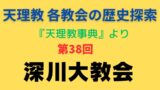
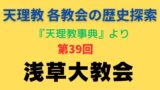
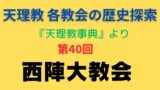
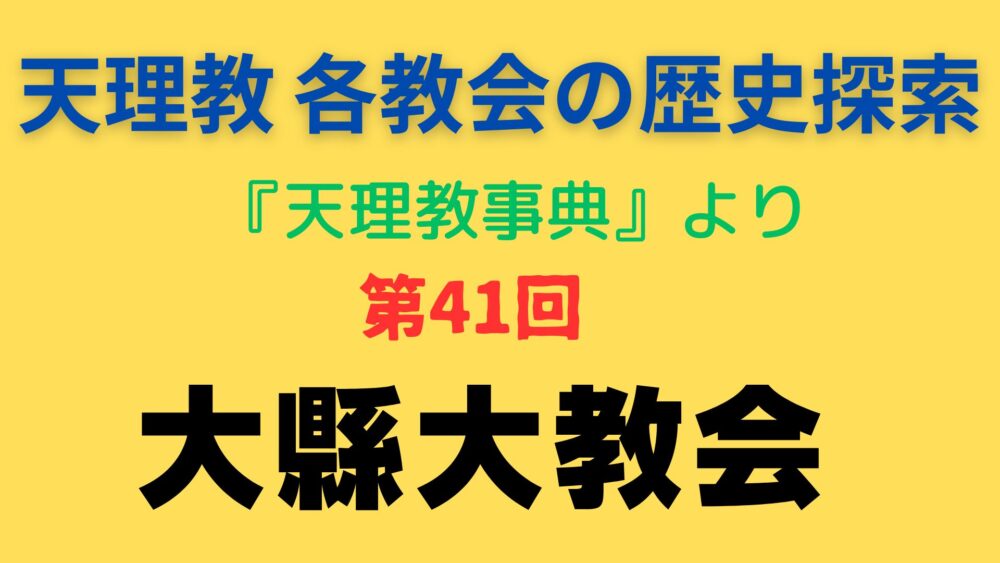
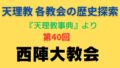
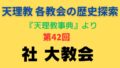
コメント