Dear everyone,
こちらは、
ふらふら彷徨う「さまよい人」による
『さまよいブログ』
= 彷徨う新米教会長の【自己学習ノート】です。
今回も、
『天理教事典』(1977年版)に記載された
各大教会の歴史、流れをそのまま書き写す
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】です。
私の教会にあるもの👇(=当シリーズ参考資料)
最新版👇
このシリーズを始めた理由については、
当シリーズ初回記事の冒頭に記述しています。
前回は、
教会番号49番「旭日大教会」の『天理教事典』記述を書写して
その歴史を勉強しました。
今回は、
教会番号50番「池田大教会」について勉強します。
- 池田大教会(いけだ だいきょうかい)
- 河合六兵衛から明石関助・クマ夫妻への伝道、入信(明治17年)
- 明石夫妻による大阪府池田槻木の「寄所」での布教活動(明治17年頃〜明治24年頃)
- 池田支教会の設立→地方庁の申請却下(明治25年)
- 宮田善蔵2代会長の就任、豊津支教会への改称を以ての地方庁申請(明治26年)
- 明石関助初代会長の復帰(3代)、池田支教会への再改称→悲願の地方庁公認(明治27年)
- 池田支教会のふしん、教会体裁の確立(明治29年〜明治34年頃)
- 明石クマ初代会長夫人の出直し〜明石関助初代会長の辞任(明治32年〜明治38年頃)
- 中腰藤吉4代会長就任→中腰四郎右衛門5代会長就任(明治38年)
- 再度の中腰藤吉会長就任(6代)(明治40年頃)
- 池田分教会への昇格(明治42年)
- 教会経理の悪化、中腰藤吉6代会長の辞任(明治42年頃〜大正2年)
- 宮田佐蔵の7代会長就任〜池田分教会の困窮時代(大正2年〜大正4年)
- 池田分教会の復活(大正4年頃〜大正15年頃)
- 芦津大教会への恩返し〜教会の移転(大正15年頃〜昭和6年頃)
- 教祖50年祭・立教100年祭に向かう年祭活動(昭和5年頃〜昭和12年頃)
- 分教会→中教会→池田大教会への昇格(昭和14年〜昭和16年)
- 宮田爽美8代会長の就任(昭和18年)
- 大阪大空襲のふし〜戦災からの復旧活動(昭和20年〜昭和23年)
- 戦後復興〜大躍進(昭和23年頃〜昭和31年)
- 量的拡大から内容充実への方針転換(昭和26年〜昭和41年)
- 双名島大教会の分離(昭和41年〜昭和46年)
- 神殿ふしん、創立80周年記念祭(昭和47年)
- 教祖90年祭活動始動〜宮田幸彦9代会長の就任(昭和48年)
- おわりに
池田大教会(いけだ だいきょうかい)

河合六兵衛から明石関助・クマ夫妻への伝道、入信(明治17年)
井筒梅治郎を講元として結ばれた真明組は、船着場を近くに控えていたので、
教えは海を渡り川を遡って伝わったものが多かった。
「池田」もその一つである。親神様のお話は、真明組の近くの江子島(えのこじま) に住む 河合六兵衛に伝えられた。
河合(六兵衛)は、
大阪府豊島郡小曽根(おぞね)村大知渡場 (わたしば) の出身で、
この村は 大阪の北を流れる神崎川の北岸にあり、
渡船場のある水郷で 村人は農業の外に船を持ち、
大阪の川筋を 隈なく運漕していた。河合(六兵衛)は 早くより 大阪で廻船業をしていたが、
渡場とは 常に 水上を往復して布教を怠らなかった。中でも (河合六兵衛の) 姪夫婦の 明石関助・クマ夫妻が 熱心に教えに耳を傾け
明治17年(1884) 入信した。
明石夫妻による大阪府池田槻木の「寄所」での布教活動(明治17年頃〜明治24年頃)
(明石)夫妻は ひたむきに信仰を深め、
相競って 熱心に神名を流して歩いたので
渡場は勿論、近在の村々にも 信者が出来はじめた。親戚村人の反対攻撃も(明石)夫妻には物の数ではなく、
度重なる警察への拘留にも信仰の火は衰えず、
教線は 次第に北上して 遂に 北摂の要衝「池田」に達した。明治20年(1887)、
(明石)夫妻は「池田」の町はずれ 槻木(つきのき) に居を移し、
ここを「寄所」として 布教活動を続けた。その結果、不思議なたすけが次々とあらわれ、
おたすけに手が廻り兼ねて、真明組から 河合六兵衛の応援を仰いだ。河合(六兵衛) は 半月、1ヵ月と逗留して、
明治23年には「池田」へ寄留手続までした程であったが、
翌(明治)24年11月、惜しくも 教会設置を見ずして出直した。
池田支教会の設立→地方庁の申請却下(明治25年)
かくして 官憲の圧迫、仏教の攻撃にも拘らず、
「池田」周辺に 教線が張られていった。真明組が 再三 地方庁より設立願いを却下された末「芦津分教会」として晴れて許された喜びに、「池田講社」も 信徒相語らい相結び、
明石(関助)講元を会長に、明治25年(1892) 2月12日 (天理教教会本部より)「池田支教会」の設立が許された。
(それで) 直ちに 地方庁に(公認を) 出願した。
しかし、不幸にも(地方庁の公認は) 却下の憂目を見るに至った。出願した場所は池田の場末で、教会の場所には不適であったので、
(地方庁の) 却下を機に 教会に相応しい屋敷を物色したところ、
田中町の大和屋という 造り酒屋の土地を買受けることになった。同年(明治25年) 8月23日 (天理教教会本部より) 教会移転設置再願の許しを得たので、 地方庁に(教会設立を) 出願したが、
これまた、不幸にして (明治25年) 9月29日 却下となった。再度の (地方庁の公認申請却下という) 悲運に直面して、
明石(関助) 会長始め 一同の落胆は大きく、
日の浅い信者の足は途絶え、熱心な者もいずんだ。却下の理由が 教会長不適格 (義侠心に篤いための誤解等) によるらしい との事が判って、
一徹な性格の明石(関助)会長は、郷里の渡場に引き籠ってしまった。
宮田善蔵2代会長の就任、豊津支教会への改称を以ての地方庁申請(明治26年)
(事) ここに (至るに) おいて、(池田支教会は)
芦津分教会の指図を仰いで、
当時 大阪市南区塩町通1丁目で足袋屋を営んでいた宮田善蔵 (芦津分教会理事兼信徒総代) を後任者に推し、
「豊津支教会」と改称して
明治26年(1893) 1月31日、その許しを得て 三願した。宮田善蔵は、明治18年夏入信以来 熱心に信仰を深め、
芦津分教会設置や普請に献身奉公し、
かねて布教専従になる意志を十分に持ちつつも その機を得 (てい) なかった。(宮田善蔵は)「池田」の事情治め方を機に 家業の整理、池田へ移転の準備、教勢の再建に着手した。
(しかし) 志半ばにして
(明治26年) 4月5日、
担任者(が)その教会に常住せざる旨を以て (申請はまたも)却下された。
(宮田善蔵を中心とした) 総ての努力も挫折し、水泡に帰した(のであった)。(2代会長・宮田善蔵は、明治32年 家業を廃し、家族と共に芦津分教会に住み込み、明治40年出直した。)
『教祖伝逸話篇』
165. 高う買うて
明治十八年夏、真明組で、お話に感銘して入信した宮田善蔵は、
その後いくばくもなく、今川聖次郎の案内でおぢばへ帰り、教祖にお目通りさせて頂いた。
当時、善蔵は三十一才、大阪船場の塩町通で足袋商を営んでいた。
教祖は、結構なお言葉を諄々とお聞かせ下された。
が、入信早々ではあり、身上にふしぎなたすけをお見せ頂いた、という訳でもない善蔵は、
初めは、世間話でも聞くような調子で、キセルを手にして煙草を吸いながら聞いていたが、
いつの間にやらキセルを置き、畳に手を滑らせ、気のついた時には平伏していた。
が、この時賜わったお言葉の中で、
「商売人はなあ、高う買うて、安う売るのやで。」
というお言葉だけが、耳に残った。
善蔵には、その意味合いが、一寸も分からなかった。
そして思った。
「そんな事をしたら、飯の喰いはぐれやないか。百姓の事は御存知でも、商売のことは一向お分かりでない。」
と思いながら、家路をたどった。
近所に住む今川とも分かれ、家の敷居を跨ぐや否や、激しい上げ下だしとなって来た。
早速、医者を呼んで手当てをしたが、効能はない。
そこで、今川の連絡で、真明組講元の井筒梅治郎に来てもらった。
井筒は、宮田の枕もとへ行って、
「おぢばへ初めて帰って、何か不足したのではないか。」
と、問うた。
それで、宮田は、教祖のお言葉の意味が、納得出来ない由を告げた。
すると、井筒は、
「神様の仰っしゃるのは、他よりも高う仕入れて問屋を喜ばせ、安う売って顧客を喜ばせ、自分は薄口銭に満足して通るのが商売の道や、と、諭されたのや。」
と、説き諭した。
善蔵は、これを聞いて初めて、成る程と得心した。
と共に、たとい暫くの間でも心に不足したことを、深くお詫びした。
そうするうちに、上げ下だしは、いつの間にやら止まってしまい、ふしぎなたすけを頂いた。
明石関助初代会長の復帰(3代)、池田支教会への再改称→悲願の地方庁公認(明治27年)
3度に亙る地方庁却下は 教勢の萎靡沈滞となって現れたが、
心ある人々によって、(再び) 初代・明石(関助)会長を中心に 再建の努力が重ねられ(るに至っ)た。遅々として再建の業が進まぬ中(にも)、次第に信者の心もよって来たので、
明治27年2月12日、名称を「池田」に復し、
会長を明石関助に戻して (本部の)許しを得、
(改めて地方庁へ公認の申請を行なった。)
(すると)
(明治27年) 3月12日、(ついに) 知事の認可を得ることが出来た。
(ここにおいてようやく)
3年来の悲願が達成された(のであった)。(教会)設置許可に勢いを得て 勇み立った一同は、
(明治27年) 旧6月1日 仮祝典を終えた。
池田支教会のふしん、教会体裁の確立(明治29年〜明治34年頃)
(そして、明石)会長夫妻を先頭に 昼夜分かたず おたすけに努力を傾けた結果、
神殿建築の気運が漲り、
明治29年(1896) 2月3日 普請の許しを得て、
池田布教10年にして、神殿普請の念願が叶えられた。内務省秘密訓令の嵐の中にも拘らず建築は進み、
翌(明治)30年9月 付属建物の普請願の許しも得、
(明治)31年の春、(無事に) 竣工した。教会設置以来、足掛け7年振りで神様を鎮座、
盛大に開筵式がつとめられた(のであった)。開筵式も終わり、(その後) 内容の充実に努力が向けられ(るようになった。)
池田を中心として、猪名川沿岸の大阪に通ずる能勢街道に点々と教えが延び、
やがて (それが) 線に結び合わされる勢いとなった。明治32年10月、庄内出張所、続いて豊止、新庄の両出張所が設けられた。
また、教祖殿建築の議が起こり、
隣地を買収して、
明治34年5月、教祖殿 及び 会長役員居宅建築の許しを得て (ふしんに) 着工(した。)
(そして、それは) 部内の心をひとつに結集して 遂に完成。
教会の体裁が ここに整えられるに至った。
明石クマ初代会長夫人の出直し〜明石関助初代会長の辞任(明治32年〜明治38年頃)
明治32年(1899)12月、
初代会長入信当初から常に表裏一体、心をあわせて信徒の育成に大きな力となっていた 会長夫人・明石クマが 惜しくも出直した。このため 教勢が沈滞の兆を見せ始め、
年と共にその色が濃くなっていった。信仰の好伴侶であった夫人を失ってより、
老齢となった明石(関助)会長は、次第に 辞意を固めるに至った。そこで、(明治38年)
理事 兼 豊止出張所長・中腰四郎右衛門の長男・藤吉を後任者に推し、
清新の気をもって 教勢の挽回を図る事となった。(ちなみに) 明石(関助) 会長は 辞任後、芦津詰所において多年勤務し、
(後の) 大正14年(に) (支教会から昇格した)池田分教会に帰り、
昭和4年 87歳をもって出直(したのであった)。
中腰藤吉4代会長就任→中腰四郎右衛門5代会長就任(明治38年)
(そもそも) 中腰家は、
池田より北へ2里(の) 豊能郡止々呂美(とどろみ) 村 大字下止々呂美の旧家であった。明治21年に (中腰) 四郎右衛門 妻・キミの病気から入信(していた)。
(中腰家)夫婦親子 揃って 明石(関助)会長を輔け、
教会に尽くして 豊止出張所を設け(てい)たが、
(池田支教会を担当することとなり)
明治38年、一家を挙げて (池田)支教会へ移り住む事となった。(池田支教会は) 中腰藤吉を 後任者に(定めて)、
明治38年(1905) 4月5日 本部の許しを得たが、
(しかし) 地方庁の(方は) 許すところとならず、(またもや) 障壁に逢着してしまった。そこで、
父 (中腰)四郎右衛門を 後任会長として (改めて)出願(することと)し、
同年(明治38年) 6月25日 (本部の)許しを得た。しかし、地方庁への出願は差し控え、当分の間(は) 豊止出張所 兼任で (池田支教会)会長 臨時代理の届出をして、再願を準備することにした。
この間、一同は 教勢の再興に努め、
中腰藤吉は 馬町布教所を開設した。
再度の中腰藤吉会長就任(6代)(明治40年頃)
明治40年(1907) 5月10日、
再び (中腰)藤吉 前会長を後任会長として (本部の) 許しを得て、地方庁へ申請。(その結果、改めて) 知事の認可を得ることが出来た(のであった)。
風雪に耐え 試練の冬も凌ぎ、遂に、愈々教勢の拡張に邁進する機が熟した。
時 あたかも教祖30年祭活動に入った折とて、
(中腰藤吉) 会長は その根強い信念と真実により、
部内教会信者を督励して布教活動に挺身した(のであった)。(中腰四郎右衛門会長は 明治42年に67歳で出直。)
池田分教会への昇格(明治42年)
明治41年秋 天理教一派独立に伴い、
芦津分教会は大教会と改称されて、
部内教会も教勢に応じて改称する事となった。当時、池田支教会は部属2ヵ所を数えるのみであったので、
大教会においては 「池田」は支教会のままと内定していたのを、
再三 懇願の末に「分教会」に改称出願を諾せられ、
明治42年(1909) 1月 その許しを得た。「池田」の内容からすれば、分教会に改称は 実に無理の中の無理であったが、
何でもどうでも の一念こそ、後年の躍進発展の種となったのである。
教会経理の悪化、中腰藤吉6代会長の辞任(明治42年頃〜大正2年)
ここにおいて、分教会に相応する内容を整えるため、
挙げて 年祭活動と教会新設に精進した結果、
明治42年〜44年に4ヵ所の教会を新設、
おぢばの神殿普請に際して(は) 力限りの実を挙げた。しかし、教会経理が 漸次悪化し(てしまい)、
会長・役員の苦心努力も空しく、
大正2年7月 遂に 差し押さえとなった。万策つきて 中腰(藤吉)会長は その責を負い 辞任した。
(ちなみに)
中腰藤吉は (池田分教会長辞任後) 兼任していた馬町宣教所長に専念したが、
(その後) 大正4年、双名島宣教所長に転じ、
苦節30年、支教会より分教会に昇格、
部属18教会を増設して、 昭和26年 80歳で出直した(のだった)。
宮田佐蔵の7代会長就任〜池田分教会の困窮時代(大正2年〜大正4年)
(池田分)教会の差し押さえは 上級・芦津大教会の救援によって事なきを得たが、
後任会長は (芦津)大教会より迎えることとなった。(芦津)大教会でも この難局に喜んで当たる人はなく、
遂に (芦津)大教会長の指名によって、
理事・宮田佐蔵 (宮田善蔵 長男) が 後任会長として
(大正2年) 10月30日 許しを得た。住み込みの役員は 既に四散、
部属教会も (池田)分教会と苦難を共にして 困窮の極に達し、
教信徒は 前途を危惧して寄りつかず、
日々の神饌燈明にも事欠く有様であった。本部仮神殿の落成は 目睫の間にあり、
教祖30年祭は切迫するが 教勢の再建は遅々として進まない。一方、(宮田佐蔵)会長は (芦津)大教会理事の職に在り、
池田(分教会) のみに没頭する事は出来ない(という時代が続いた)。
池田分教会の復活(大正4年頃〜大正15年頃)
その間、心ある人々が互いの心を結びつつ、
(宮田佐蔵)会長の意を体して 再建に努力した結果、
旧地盤の信徒が再び集まり、
布教地開拓・事情教会の整理に 徐々ながらも効が見え始め、
大正4年(には) 新設 1、同(大正)5年に(は) 3ヵ所の 教会の復興整理を遂げた。経理状態は 依然窮乏の中にあったが、
同(大正)8年、(大正)9年に 4教会を増設するに至り、
部属教会 11ヵ所に達した。大正10年(1921)、教祖40年祭の提唱があり、
ぢばの声に呼応して 教勢倍加運動に突入した。布教地開拓と修理肥の努力は 漸く実を結び始め、
(教祖40)年祭(=大正15年) にいたる 4ヵ年に 12教会を新設した。この間 経理面も漸く正常に復し、
本部境内の拡張と 芦津詰所の移転建築には、
相応の用を果たし得られるに至った。
芦津大教会への恩返し〜教会の移転(大正15年頃〜昭和6年頃)
10年来 会長はじめ役員の脳裡より消えやらぬは、
以前 芦津大教会より救って頂いた御恩返しの一事であった。芦津詰所移転建築に生じた負債に対して、
督促の急なるを知った 大正15年(1926)末、
衆議一決、池田分教会の土地建物をもって償還にあてることを願い、幸い容れられたので
一時借入金をもって返済、多年の宿願を果たすことが出来た。さて、借入金償還のための土地の処分と、移転地の物色が急がれたが、
何れも交渉は成立せず、
止むなく 方面を変えて
大阪市東淀川区三国本町に移転地を買収。昭和2年12月9日、移転建築の許しを得て、
同(昭和)4年6月10日仮遷座祭、翌11日 仮奉告祭を執行した。(教祖)40年祭 倍加運動の余勢は、
内容充実の声と共に 教師教徒の激増となり、
(池田)分教会の移転建築に併行して、
昭和4年末までに 部内11教会の建築を見るに至った。仮遷座祭後、引続き 教祖殿 及び 客室を建築する予定のところ、
折柄の不況の余波を受けて着手し得ず、
漸く 昭和5年春着工(した)。
途中、数回工事休止を余儀なくされ(たが)、遂に 昭和6年夏(に)竣工(した)。(ついに) 5年に亙る宿望を遂げ(はし)たが、
この間に生じた負債のために
(池田分教会は) その後10年間、返済に 苦心を重ねた。
教祖50年祭・立教100年祭に向かう年祭活動(昭和5年頃〜昭和12年頃)
昭和5年(1930) 10月、
教祖50年祭、立教100年祭の発表により
昭和普請、「人類の更生」の活動に入った。池田(分教会) は、当初1ヵ年(は) 移転建築未完のため 力を割かれたが、
昭和7年に入るや、全力を挙げて 両年祭の活動に没頭、
着々と その実を挙げていった。創立以来、幾多の事情で遅れがちであった 池田(分教会) の教勢も、
漸く その遅れを取り戻した。
分教会→中教会→池田大教会への昇格(昭和14年〜昭和16年)
昭和14年(1939) 4月下旬、
芦津大教会長に 召集令状が下った。(芦津大教)会長は、西宮・池田の両分教会を分離昇格させる心を定めた。
(昭和14年) 7月7日、(池田分教会は) 芦津より分離して 中教会に昇格改称の許しを得た。
(昭和14年) 8月に 丹波市町三島に 信徒詰所を開設。
次いで 翌(昭和)15年2月14日 【大教会】に昇格を許され、
翌(昭和)16年3月12日に 大教会昇格。
(そして) 創立50周年記念祭を2代真柱臨席の下に執行した。
宮田爽美8代会長の就任(昭和18年)
「革新」の時代は 天理教にとり隠忍の時代であった。
池田(大教会) も その中にあって、
内容の充実と 部内教会の修理に ひたすら力を注いだ。昭和18年(1943)初頭、
(宮田佐蔵)会長が 本部准員に専務のため辞任(した。)
(そして) 長男の(宮田)爽美を後任会長として、
(昭和18年)3月27日 任命の許しを得た。(ちなみに)
(その後) 7代会長・宮田佐蔵は
教会本部准員として おぢばに勤務し、
昭和22年 出直した。
大阪大空襲のふし〜戦災からの復旧活動(昭和20年〜昭和23年)
昭和20年(1945)、
(宮田爽美)会長が (軍役)応召 (代務者・宮田佐蔵) して不在中、
(昭和20年) 6月7日 大阪北部へ大空襲があった。(池田大教会は) 来襲の爆撃機の投下した焼夷弾のため、
延500余坪の教会建物は鳥有に帰し、僅かに 炊事場が残った(ばかりだった)。(大阪大空襲を受けても) 幸い無事であったお目標を
(池田大教会は) 取り敢えず ここに奉遷し、
部内戦災教会20ヵ所の慰問激励と仮事務所の物色に努力した(のだった)。終戦になり、(昭和20年) 9月12日 (宮田爽美)会長が復員 帰会。
次いで、同(昭和20年9月) 24日、大阪市東淀川区下新庄町にお目標を奉遷して、仮事務所を開設した。昭和21年(1946) 3月、
「池田大教会の名称を親神様から許された限り、池田の何処かに帰るべき場所は、必ず明けて待っていて下さる筈」
と、会長役員一同は『池田』復帰の心を定めて、土地探しに取り掛かった。しかし 事に当たって、(物事は) 信念通りに容易に運ぶものではなく、
幾度か 信念の揺らぐ危機があった。(しかし、多くの紆余曲折を経て)
同年(昭和21年) 11月、池田市満寿美町の一角に 700余坪を得(ることが出来)た。これに力を得て、(昭和21年) 12月16日 移転建築の許しを得て、
昭和22年2月22日 地鎮祭、4月1日 起工式、6月8日 上棟式、と工事は捗り、
同(昭和)23年3月22日 お目標 仮遷座と共に 付属建物の移転建築に着工し、5月中旬に竣工(した)。
(そして) 真柱夫妻を迎えて (昭和23年) 5月29日 鎮座祭、翌30日 会長就任移転建築奉告祭を執行した。
戦後復興〜大躍進(昭和23年頃〜昭和31年)
(池田)大教会の復興建築は一応成ったので、
部内戦災教会の復興促進、別席人の増加、布教所の増設等に向かって 努力を重ねた。
その結果、別席人や修養科生は 年と共に増加。戦災教会の7割が復興を完了し、布教所増設(を掲げて運動した活動の成果) は
昭和26年の春、教会20ヵ所の新設(という姿) となって現われた。別席人・修養科生と 帰参者の増加(という現象)は、信徒詰所の狭隘と(いう姿と)なった。
(そのため) 昭和26年(1951) 6月26日 その移転建築の許しを受け、
翌年(昭和27年) 3月1日 竣工成った新詰所に移り、
4月26日 真柱夫妻と真柱後継者・中山善衞の臨席のもと 詰所開きを行った。教祖70年祭の期日も発表され、
喜び勇んで 三年千日の年祭活動に踏み出した。(池田大教会は) この3年間に、教会23ヵ所の増設を見た。
教祖60年祭には 59ヵ所であったが、
(教祖)70年祭には 119ヵ所となり、10年間に倍増している。尚、教祖70年祭の昭和31年には、
更に (教会) 7ヵ所の増設となった。(教祖60年祭から70年祭に至るこの時期は)
教祖40年祭に倍加を遂げ、続く(教祖50年祭までの) 10年(間)に倍加 (したという大躍進の時代) に続く、
第3の開花期であった。
量的拡大から内容充実への方針転換(昭和26年〜昭和41年)
昭和26年、5教会 新設出願の波紋が「池田」部内を揺るがした。
(結果的には) 互いに 相競う結果として【倍加】という御守護を見たが、
いずれも 多少の無理しての教会設置で、
その内容は 十分なものではなかった。(その反省を踏まえ、池田大教会は)
ここで 教祖70年祭後の目標として、
教会個々の内容充実(という方針を掲げて) 一層努力した。かくして
表面平静に見える水面の下で、
絶えず 足掻きが続けられ 教祖80年祭を迎えた。(教祖70年祭から80年祭の)
この10年間の教会増加は11ヵ所に止まったが、
(教会)内容充実の努力は 徐々ながらも 着実な足跡を残した。
双名島大教会の分離(昭和41年〜昭和46年)
昭和41年(1966) 秋、
(池田大教会は)
38ヵ所を数える 双名島分教会に
「3年を区切って 教会数50を満たし、大教会となって『おぢば』直々の御用を果たすように」
と要請した。(その結果、双名島分教会は)
3年の期限は超えたが 12教会を新設して 50ヵ所となったので、
昭和46年11月に「双名島大教会」として許しを受け、
池田(大教会)から分離して、本部の直属となった。
神殿ふしん、創立80周年記念祭(昭和47年)
(かつての) 昭和22、23年の移転普請は、戦災後の応急のものであった。
(その後) 広い敷地を求めて移転する動きが出た(こともあった)が、
(宮田爽美)会長の病気などで中挫した(のであった)。(池田大教会一同は)
現在の敷地を本拠とするのが神の思召(だ)と悟り、
将来の神殿の構想を中心に (神殿ふしんの) 計画を立てた。昭和47年初頭から その第1期工事に着手し、
(同年内に) 鉄骨鉄筋コンクリート3階建1棟を完成(した)。(そして)
同(昭和47年) 12月16日 真柱夫妻を迎えて、
教会創立80周年記念祭を執行した。
尚、その前夜に 2代真柱の霊を 祖霊殿に合祀(した)。
教祖90年祭活動始動〜宮田幸彦9代会長の就任(昭和48年)
明けて 昭和48年(1973)は、
教祖90年祭活動の 三年千日の旬に入った。(昭和48年) この年頭に (宮田爽美)会長は
「時 あたかも御年祭の旬に入り、この際、清新の気を以て、旬の御用を迎えてほしい」
と 辞意を表明。ここにおいて (宮田爽美)会長の長男・幸彦を後任会長として
(昭和48年) 6月26日 許しを得、
(昭和48年) 9月29日 真柱夫妻臨席の下に 9代会長就任奉告祭を執行。若き (宮田幸彦)会長を芯に、(教祖90)年祭に向かい 心の成人を期して(新体制が)発足した。
(教祖80年祭から90年祭直前の)
この9年間に、17ヵ所の教会新設をみた。〔現住所〕〒563-0012 大阪府池田市東山町1081
〔電話〕072-751-3312(昭和50年12月31日調「天理教統計年鑑」昭和50年度版)
(『天理教事典』1977年版 P,41〜44)
おわりに

天理教各大教会の歴史を知りたいとの思いで始めた
【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】。
50回目の今回は、
「池田大教会」初期の歴史を勉強しました。
当シリーズの 参考教材は『天理教事典』の【1977年版】。
とても古い資料なので、
記載内容も 1970年代以前までとなっており、
かなり昔の歴史にとどまっています…
しかし、私が知りたいのは 各大教会の初期の歴史。
十分 私のニーズは満たされるので、
そのまま書写し続けております (^_-)-☆

【天理教 各教会の歴史探索シリーズ】50回目の当記事では
『天理教事典』の中の「池田大教会」についての記述を書き写して勉強しました。
池田大教会は、芦津大教会から分かれた大教会ですね。
芦津大教会については、以前勉強して記事を投稿しました。
今回は、池田大教会について勉強したわけですが、
私は、これまで池田大教会の方とのご縁が皆無でしたので、その歴史を全く知りませんでした。
今回、『天理教事典』「池田大教会」の解説文を読んで、
地方庁の認可を受けるために とてつもなく苦労をされたのだということを初めて知りました。
これまで約50回天理教大教会の歴史勉強シリーズを重ねる中で、
お道の初期 どこの教会も、政府の公認を受けるにあたって、多かれ少なかれ 様々な苦労を重ねてきたことを知りました。
『天理教事典』解説文を読むと、
「池田支教会」が公認を受けるまでの苦難の道中は、その中でも 特筆すべきレベルだったのではないだろうか、と私の眼には映りました。

公認を受けるまでの流れを箇条書きにしてみます。(敬称略)
- 真明組の河合六兵衛から、明石関助・クマ夫妻ににをいが掛かり、明治17年に明石夫妻が入信した。
- 河合六兵衛の出身地、大阪府豊島郡の渡場から道は広がり、明石夫妻は、明治20年に大阪府池田市槻木町に「寄所」(池田講社)を設け 布教活動に励んだ。
- 明治24年に上級・芦津分教会が地方庁から公認されたのを受けて、池田講社一同は教会設立に動き、明治25年2月12日に本部より「池田支教会」設立のお許しを受けた。
- 本部のお許しを受けたので、続けて地方庁に出願したが却下された。
- 却下を機に 教会に相応しい屋敷を物色し、田中町の大和屋という 造り酒屋の土地を買受けた。
- 約半年後の明治25年8月23日に本部の教会移転設置再願の許しを得て、再度、地方庁に教会設立を出願したが、明治25年9月29日 却下となった。
- 再度の 地方庁の公認申請却下で、一同の落胆は大きく、日の浅い信者の足が途絶えた。
却下の理由が 教会長不適格 (義侠心に篤いための誤解等) によるものらしいと判明し、明石関助初代会長は郷里の渡場に引き籠ってしまった。 - 上級・芦津分教会と相談の上、当時 芦津分教会理事兼信徒総代であった宮田善蔵に担任変更し、名称も「豊津支教会」に改称。
明治26年1月31日に本部のお許しを得て、地方庁へ3度目の教会設立を出願。
しかし、同年4月5日に却下された。 - 3度にわたる却下の後、心ある人々によって再建の努力が重ねられた。
その結果、名称を「池田支教会」へ戻し、また会長も明石関助に戻して、改めて申請することとなった。 - 明治27年2月12日本部のお許しを得て、地方庁へ公認を出願。
その結果、明治27年 3月12日、ついに知事の認可を得ることが出来た。
以上が、最初に「池田支教会」が公認を受けるまでの大まかな流れですが、
その後、明治38年に明石関助会長の後を受けて、中腰藤吉先生が後任会長に就任する際にも、
なかなか地方庁の公認が出ず、苦労しておられます。
その対策のためだろうと思うのですが、
中腰藤吉先生のお父様・中腰四郎右衛門先生が ワンポイントリリーフみたいな形で 担任となられたり…
最終的に、明治40年、
再び、中腰藤吉先生を担任として本部のお許しを受け、改めて地方庁へ申請して、ようやく公認を受けられているわけですが、
最初の公認といい その後の公認といい、
本当に複雑な経緯をたどられています。
このような大きな壁を乗り越えて、
「池田大教会」は産声を上げたのですね。
差し止められても、差し止められても、
へこたれることなく公認を求めて前進し続けられた先人先生方。
諦めることなく活動し続けられた原動力は一体何だったのだろう…
という思いが湧き上がってきます。
月並みですが、それはやはり、
何としても、自分たちの身近に 神様とつながる拠点を持ちたい、
という 熱い想いだったのでありましょう。
気付いた時には身近に天理教の教会があって、時に 面倒くさがりながら 何となく参拝している 今の私のような者は、
苦難を乗り越えて やっと教会を設立された 当時の先生からすると、
なんという罰当たりな奴!
という感じですよね。
今生において「天理教の教会」にご縁を頂いた者として、
「教会」というのは、先人先生方の並々ならぬご苦労の上に誕生したものである、
という歴史を忘れないようにしなければ…
今回「池田大教会」産みの苦しみの歴史を学んで、改めてその思いを強くしています。

その他にも、知らないことばかりでした。
今回もまた、書き写しを通して多くのことを知ることができ、とても勉強になりました。
有難いことでした。
「人に歴史あり」
組織にも歴史あり…
歴史を踏んで今がある――
だからこそ、
今を輝かせるためには
「元一日」を振り返るということが不可欠なのでしょう。
ということで――
今回は「池田大教会」初期の歴史の勉強でした。
人生、死ぬまで勉強。
今後も、勉強し続けていきたいと思います。
ではでは、今回はこのへんで。

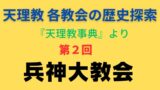
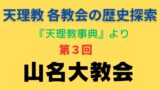
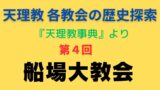
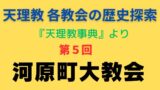
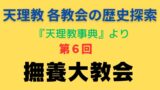
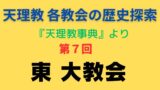
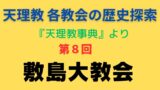
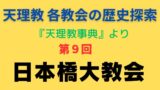
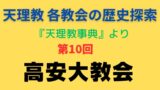
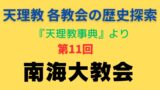
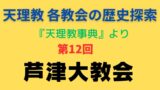
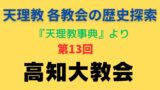
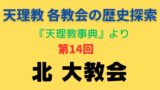
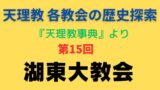
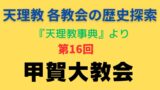
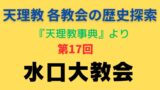
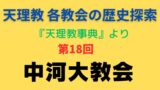
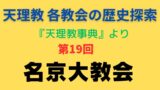
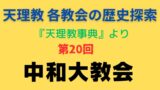
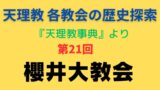
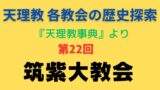
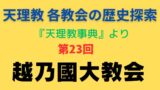
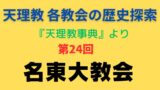
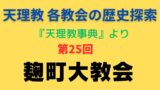
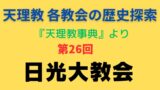
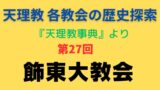
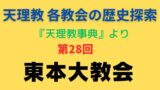
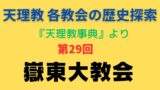
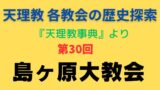
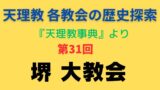
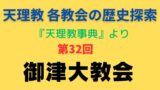

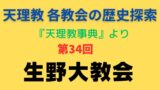
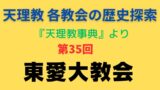
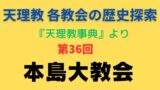
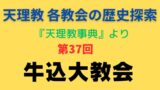
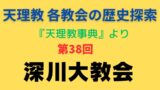
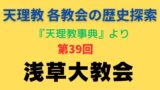
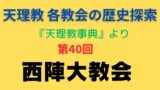
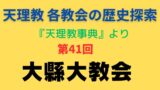

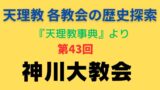
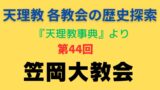
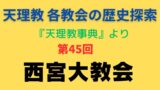
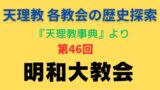
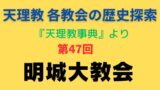
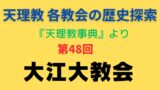
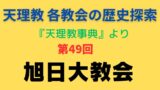
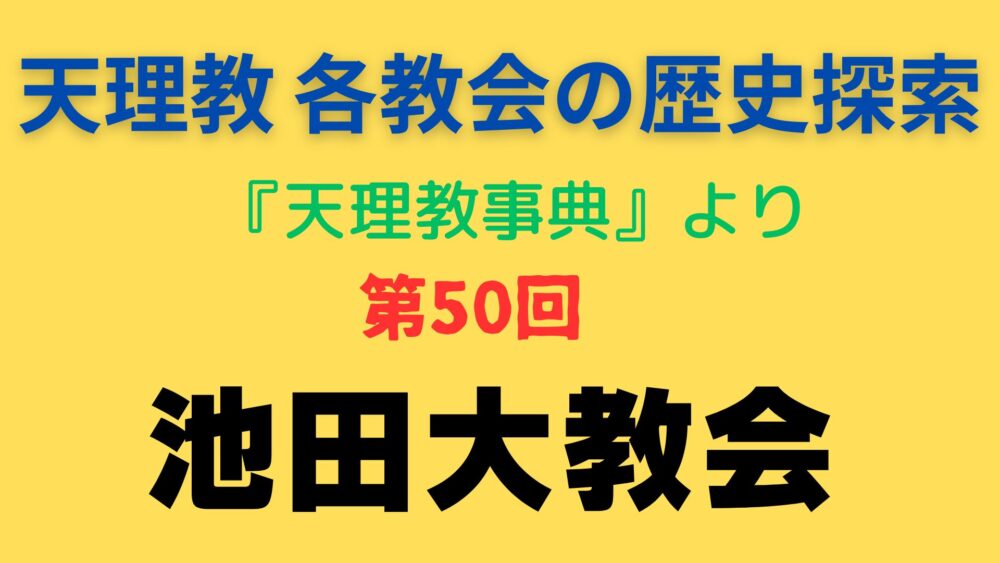
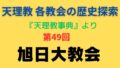
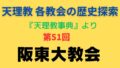
コメント